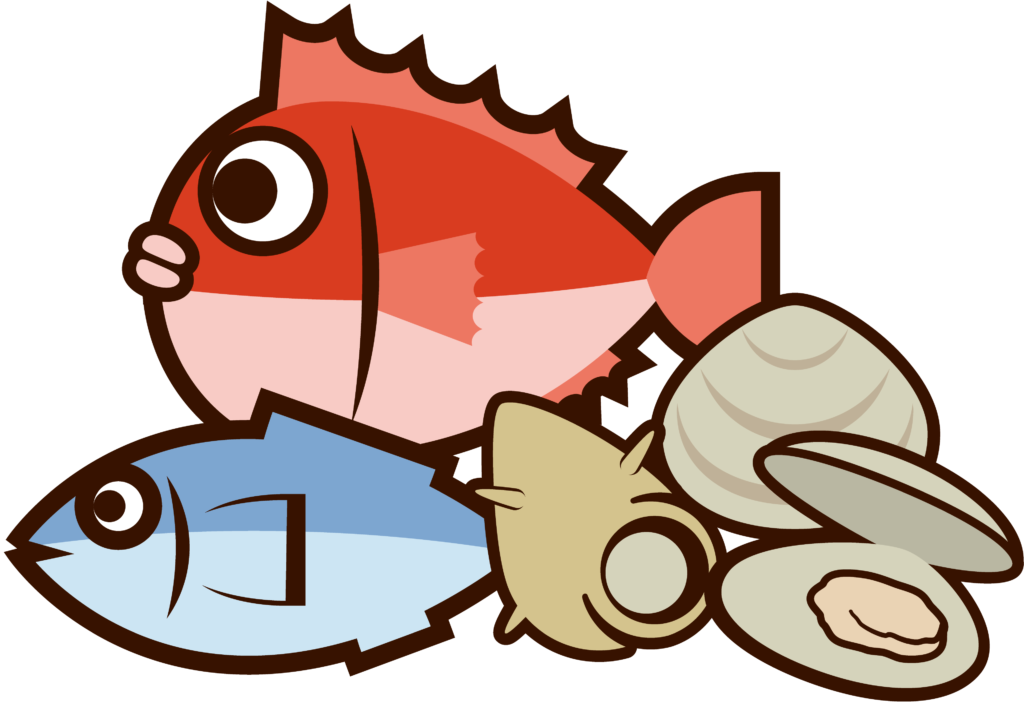バウムクーヘンが日本で初めて紹介された場所は「原爆ドーム」

バウムクーヘンは、1919年に広島県物産陳列館(現在の原爆ドーム)で開催されたドイツ作品展示即売会において、日本で初めて紹介されました。この展示会は、ドイツと日本との文化的な交流の一環として行われ、バウムクーヘンはそこで初めて日本の人々にお披露目されたのです。つまり、実は広島が日本においてバウムクーヘン誕生の地となったのです。
バウムクーヘンが日本で知られるまでの歴史
第一次世界大戦中、日本は連合国としてドイツと敵対していましたが、多くのドイツ人兵士が捕虜として日本に収容されました。
その中でも、徳島県鳴門市にあった板東俘虜収容所は比較的人道的な待遇を提供しており、捕虜たちに音楽や演劇、料理などの文化活動が許されていました。
その収容所にいた一人の菓子職人、カール・ユーハイムがバウムクーヘンを日本に伝える役割を果たしました。
ユーハイムはドイツで本格的な技術を学んだ菓子職人であり、彼の技術が日本に新しい菓子文化をもたらすことになったのです。
広島で行われた展示会にて披露
カール・ユーハイムが広島で行われた展示会にて披露したバウムクーヘンは、その独特の製法で注目を集めました。
バウムクーヘンは、棒に巻きつけた生地を一層ずつ焼き重ねていくことで作られ、切り口が木の年輪のように見えることから「木のケーキ」と呼ばれています。
この美しい見た目と奥深い味わいは、当時の日本人を魅了し、バウムクーヘンはその後日本でも広まりました。
人気のバウムクーヘンメーカー「ユーハイム」の生い立ち
ユーハイムは、展示会での成功を経て、1922年に横浜で洋菓子店「ユーハイム」を開業しました。
横浜は外国人居留地があり、西洋文化が受け入れやすい環境でした。しかし、1923年の関東大震災によって横浜の街は壊滅的な被害を受け、ユーハイムの店舗も焼失してしまいました。
その後、ユーハイムは再起を図るため神戸へ移転します。神戸は国際的な港町で、異国文化に寛容な土地柄があり、再スタートに適した場所でした。
神戸で再び洋菓子店を開店したユーハイムは、徐々に人気を集め、バウムクーヘンは日本人の間で広く知られる存在となりました。昭和初期には宮内庁御用達となり、その名声は全国に広がっていきました。
ユーハイムは戦後、全国に店舗を拡大し、現在では百貨店や商業施設を中心に多くの直営店を展開しています。
戦後のバウムクーヘン文化の広がり
伝統的なバウムクーヘンは、職人が一層ずつ生地を重ねて焼き上げるという手間のかかる技術が必要です。
現代では機械化が進み、大量生産が可能となっていますが、依然として高級店では手作業で焼き上げる店舗も多く、製造過程を見学できる施設も人気を集めています。
第二次世界大戦後、日本は復興と共に洋菓子文化を取り戻し、バウムクーヘンもその一環として広まりました。全国の洋菓子店で製造が始まり、次第に日本独自のバリエーションが生まれています。
抹茶や柚子、小豆など、和の素材を活かした「和風バウムクーヘン」も登場し、贈答品や引き出物として親しまれるようになりました。
また、「輪が続く」という形状から、縁起の良い菓子としても広まりました。
まとめ
バウムクーヘンが日本に伝わった背景には、戦争という厳しい時代がありました。
それでも、異なる文化が交わることで、人々の間に新たなつながりが生まれたことは非常に貴重な歴史的事実です。
広島で披露されたバウムクーヘンが、後に原爆ドームという平和の象徴的な場所と結びついたことは、平和と文化交流の大切さを教えてくれます。
美しい年輪が重なっていくバウムクーヘンは、異なる文化が交わり、共に未来を築く希望の象徴として、多くの人に語り継がれています。