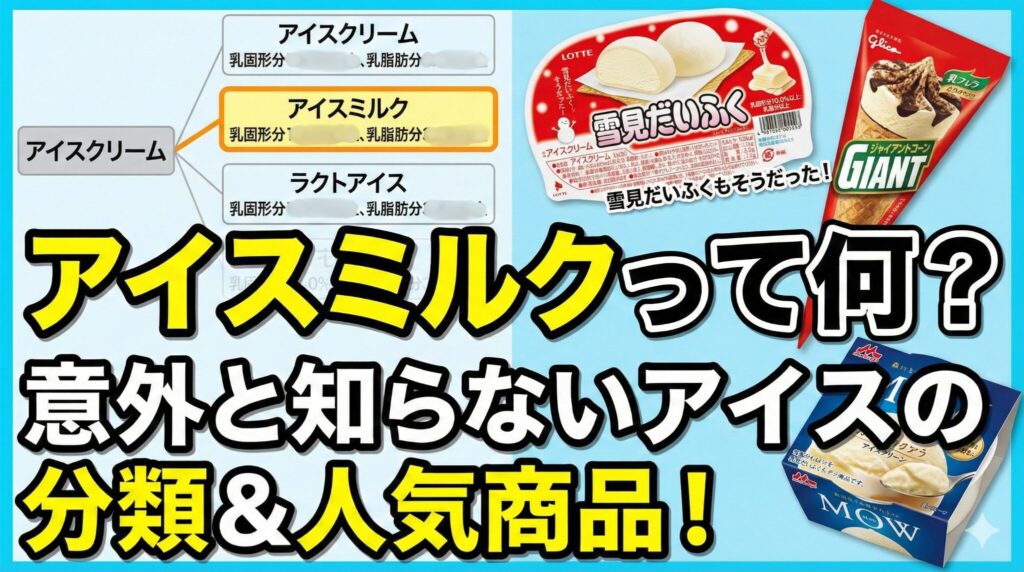コッペパンとは|日本独自の進化を果たしたパン
学校給食や町のパン屋さんで親しまれてきたコッペパン。このシンプルでどこか懐かしいパンが、2017年から2018年にかけて、再び大きな注目を集めました。その親しみやすい見た目とは裏腹に、コッペパンには実は意外なほど興味深い歴史と語源が隠されています。
コッペパンとは
コッペパンは、その名の由来にもなった独自の製法と形状を持つパンです。私たちが普段目にするパンとは違い、細長い楕円形をしており、間に切れ目を入れて具材を挟むのに最適な形をしています。このパンの起源を理解するためには、まずフランスパンについて知る必要があります。私たちが「フランスパン」と呼んでいるものは、実は単一の種類ではなく、たくさんの異なる形と名前を持つパンの総称なのです。
コッペパンの名前の由来
コッペパンの名前は、フランスパンの一種である「クープ」から来ていると言われています。最も有名なフランスパンは細長いバゲットですが、パリジャンという太めのものや、バタールという短めのものなど、さまざまな種類があります。
この中で、コッペパンの語源となったのが「クープ」です。クープは長さが約20センチと小ぶりで、最も重要な特徴は、焼く前に表面に一本の切れ目を入れることにあります。この「切る」という作業をフランス語では「coupe(クープ)」と呼び、動詞の「couper(クーペ)」の過去分詞である「coupé(クーペ)」が、日本では「コッペ」と聞こえるようになり、パンの名前になったと考えられています。
日本におけるコッペパンの歴史
コッペパンが日本で作られるようになったのは、およそ100年前のことだとされています。このパンは、日本人の食文化や生活スタイルに合わせて独自に進化を遂げました。
日本独自の進化
当時のコッペパンが、フランスパンと同じ硬い生地で作られていたかどうかは定かではありません。しかし、昭和の時代に学校給食などで広く食べられていたコッペパンは、フランスパンのような硬い生地ではなく、普通のパン生地で作られた柔らかいものでした。これは、日本人の食文化や好みに合わせて変化していった結果だと考えられています。
約20センチという手頃な長さは、フランスの本来のクープと同様に、日本人にとって扱いやすいサイズでした。バゲットのように60センチもあると、家庭で保存したり食べきったりするのは大変ですが、コッペパンのサイズなら一人でも無理なく消費できます。この適度な長さは、中に具材を挟んでサンドイッチのように食べるのにも最適で、手軽な軽食として定着していったのです。
コッペパン再ブームの背景
長い間、日本の食卓に親しまれてきたコッペパンですが、2017年から2018年にかけて、再び大きな注目を集めました。
この再ブームの背景には、日本のパンブームの歴史があります。1960年代半ば過ぎには本格的なフランスパンブームが起こり、その後も1970年代前半のデニッシュ・ペストリーブーム、そして2015年の高級食パンブームなど、様々なパンが流行しました。
こうした一連のパンブームを経て、消費者も業界も「次は何か新しいものはないか」と模索していた時期に、改めて見直されたのが、古くから日本になじみのあるコッペパンでした。「そうか、こんな身近なものがあったじゃないか」という再発見の気持ちが、ブームの火付け役となったと考えられています。
ブームの仕掛け人は?
このコッペパンブームの仕掛け人については、実ははっきりとした答えがありません。大阪、神戸、仙台、東京近郊など、様々な地域がその起源を主張していますが、真相は定かではありません。しかし、このことは、コッペパンが日本全国で同時多発的に見直されたことを示しているとも言えるでしょう。
コッペパンのこれからに期待
ブームが始まると、各地にコッペパン専門店が次々とオープンしました。これらの専門店では、従来の懐かしいコッペパンだけでなく、現代の多様な食材や調理法を取り入れた新しいスタイルのコッペパンが提供されるようになりました。
クリーム系、総菜系、スイーツ系など、様々な具材を使った創作コッペパンが登場し、若い世代にも新鮮な魅力として受け入れられています。コッペパンの適度なサイズと使い勝手の良さは、軽食からしっかりとした食事まで幅広いニーズに対応でき、忙しい現代人のライフスタイルにもよく合っています。
今後も、日本人の創意工夫によって、コッペパンがどのような新しい進化を遂げていくのか、その展開が大いに期待される食文化の一つと言えるでしょう。