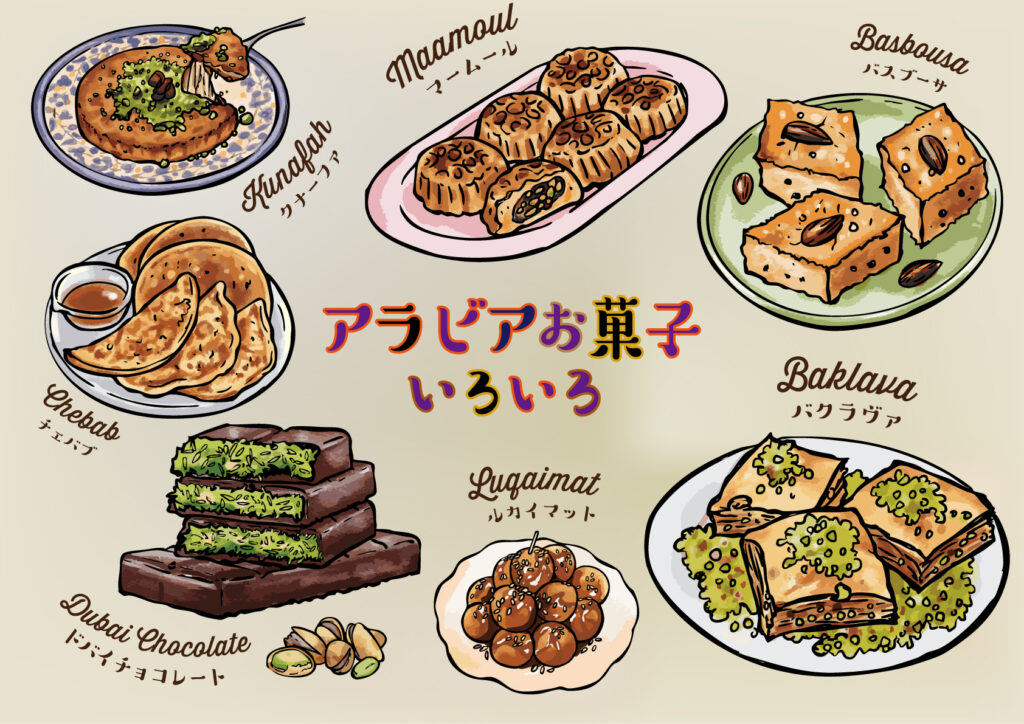駄菓子とは|語源で分かる日本のスイーツ文化の流れ

駄菓子とは何か
駄菓子とは、安価な価格で買うことができるお菓子を指す言葉です。
現在でも、多くの駄菓子は10円から数十円程度で販売されています。
たとえば、500円あれば、10個以上の駄菓子を自由に組み合わせて買うことができます。
この説明だけだと、安価なものが全て駄菓子に当てはまるように感じるかもしれません。
しかし、駄菓子という言葉には、単に値段が安いだけでなく、どこか懐かしい、素朴な味わいを持つお菓子というニュアンスが含まれています。
歴史的な背景から見ても、駄菓子は庶民の生活の中で育まれてきた、大切な存在と言えます。
駄菓子の語源
「上菓子」との対比から生まれた「駄菓子」
この呼び方は、高価な材料で作られた高級なお菓子である「上菓子」と区別するために使われ始めました。
「上菓子」は、文字通り「上等なお菓子」「高級なお菓子」という意味で、公家や大名などの限られた人々が食べるものでした。
それに対して、庶民が日常的に口にする、比較的安価な材料で作られたお菓子には、「上菓子」と区別するための言葉が必要でした。
そこで、「上」の対義語である「駄」という字が選ばれ、「駄菓子」という呼び名が生まれました。
この「駄」は、値打ちがない、というような意味合いで使われます。
「駄」という文字が持つ意味
この「駄」という字は、「粗悪な」「劣った」という意味合いで使われることがありますが、この場合は駄菓子の品質が悪いことを意味しているわけではありません。
これはあくまでも「上菓子」との相対的な関係を示すための言葉です。
駄菓子は上菓子に比べて材料や製造方法が簡素でしたが、庶民にとっての栄養源であり、小腹を満たしたり、エネルギーを補給したりする重要な役割を果たしていました。
駄菓子が生まれるまでの歴史
「お菓子」という言葉の起源
お菓子の原型を理解するために、まず「お菓子」という言葉の由来を考えてみましょう。
「菓」という漢字は、元々「果物」を意味していました。
日本の昔の記録を見ると、奈良時代には果物が「くだもの」や「かし」と呼ばれていました。
時代が流れるにつれて、この言葉の意味は広がり、甘みを楽しむために作られた食品全般を指すようになりました。
日本の伝統的な和菓子や、西洋から伝わった洋菓子も、すべて「お菓子」という大きなカテゴリーに含まれます。
江戸時代のお菓子事情
庶民が食べていた安価な材料のお菓子
駄菓子の歴史を遡ると、江戸時代にたどり着きます。
当時の日本では、現在とは異なる食の事情がありました。
米を使ったお菓子は非常に高価で、一部の富裕層しか口にできませんでした。
その代わり、庶民が食べていたのは、麦、ひえ、あわ、屑米といった安価な材料で作られたお菓子でした。
これらのお菓子は、貴重なエネルギー源としても重宝されました。
甘味料の事情
さらに、白砂糖は非常に貴重で高価なものでした。
そのため、甘みを得るために黒砂糖や水あめが使われていました。
これらの限られた材料で作られたお菓子は、当時のお金の単位で1文という非常に安価な価格で売られていました。
この1文を現在のお金に換算すると、だいたい数十円程度になります。
この価格帯は、現在の駄菓子屋で見かける商品の価格帯とほとんど変わりません。
呼び名の変化
このような安価なお菓子は「一文菓子」あるいは「雑菓子」と呼ばれていました。
「雑菓子」という呼び名は、「いろいろな材料を混ぜて作る」という意味合いからきています。
時代が進んで貨幣制度が変わると、呼び名も「一厘菓子」「一銭菓子」と変化しましたが、安価で庶民的であるという基本的な性格は変わりませんでした。
駄菓子の進化
西洋菓子の流入
明治維新後、日本に西洋の文化が流入し、お菓子の世界にも大きな影響を与えました。
ビスケット、チョコレート、ドロップといった西洋のお菓子が次々と日本に入ってきました。
これらの新しいお菓子は、日本の駄菓子に新たな風を吹き込み、より多様な商品が生まれるきっかけとなりました。
製造技術の進歩
日本の製糖業が発達し、砂糖の安定供給と価格の低下が実現しました。
これにより、駄菓子の種類は飛躍的に増加しました。
従来のきな粉餅、おこし、あんこ玉、かるめ焼きなどに加えて、ガムやグミ、キャラメルといった新しいタイプの駄菓子も作られるようになりました。
また、機械化も進み、職人の手作業に頼っていた製造工程が効率化され、駄菓子の大量生産が可能になりました。
おまけ付きキャラメルの登場
おまけの始まり
大量生産が可能になると、お菓子におまけのおもちゃを付ける工夫も始まりました。
お菓子そのものだけでなく、小さなおもちゃが付いてくることで、子どもたちにとって駄菓子はさらに魅力的なものになりました。
特に昭和初期におまけ付きのキャラメルが登場すると、その人気は爆発的に広まりました。
キャラメルの普及
第二次世界大戦後には、100社以上のメーカーがキャラメル製造に参入したと言われています。
各社がおまけにも様々な工夫を凝らし、収集を楽しむ子どもが増えました。
キャラメルは現在に至るまで、駄菓子の代表として多くの人に愛されています。
駄菓子屋の社会的機能
子どもたちのコミュニティ
第二次世界大戦後、砂糖の統制が撤廃されると、駄菓子屋は子どもたちにとって大切な場所になりました。
駄菓子屋は、単に商品を買う場所ではなく、地域の子どもたちが集まるコミュニティの場でした。
学校帰りには、子どもたちが駄菓子屋に立ち寄り、店のおばちゃんと話をしたり、友達と一緒にお菓子を選んだりする姿が見られました。
コミュニケーションと教育
駄菓子を友達と分け合ったり、おまけのおもちゃを交換したりすることで、子どもたち同士のコミュニケーションが生まれました。
また、限られたお小遣いで何を買うか考え、計算しながら商品を選ぶことは、お金の使い方や算数の概念を学ぶ良い機会にもなっていました。
駄菓子屋は、子どもたちが社会のルールを学ぶ小さな学校のような役割も果たしていたと言えます。
駄菓子が地域経済に貢献
地域の特産品を使った駄菓子
駄菓子は、地域経済の発展にも貢献しました。
日本各地で作られる駄菓子の多くは、その地域の特産品を原料にしていました。
たとえば、埼玉県の五家宝は、地元産の大豆から作ったきな粉を原料とする駄菓子がもとになっています。
現在では、県を代表する銘菓として知られています。
地域に根差した駄菓子は、地元の人々にとってはなじみ深い味であり、観光客にとっては地域の文化に触れるきっかけにもなりました。
駄菓子が文化を継承
仙台駄菓子や飛騨駄菓子のように、昔ながらの製法で作られたお菓子が、観光土産として重宝されている例もあります。
駄菓子は、祭りや縁日でも欠かせない存在でした。
駄菓子のつかみ取りやくじ引きの景品、綿あめやカルメ焼きの屋台は、今でも祭りの風景の一部となっています。
駄菓子は、単なる食べ物ではなく、地域の伝統や文化を現代に伝える役割も担っているのです。
現代の販売形態の変化
駄菓子屋の減少
高度経済成長期以降、社会構造の変化とともにスーパーマーケットやコンビニエンスストアが普及しました。
これにより、個人経営の駄菓子屋は徐々に数を減らしました。
昔ながらの駄菓子屋は、時代の流れとともに姿を消していくことになりました。
代替店の普及
しかし、駄菓子の需要はなくなっていません。
現在では、スーパーマーケットやショッピングセンターの駄菓子コーナー、コンビニエンスストアなどで駄菓子が販売されています。
駄菓子は、新たな販売ルートを見つけることで、現代でも多くの人々に親しまれています。
購入者層の変化
駄菓子の購入者層も変化しています。
かつては子どもたちが主な顧客でしたが、現在は幅広い年代に広がっています。
コンビニエンスストアでの調査によると、駄菓子の購入者の大半は、20代から30代の大人であるというデータがあります。
これは、駄菓子が持つ懐かしさや手軽さが、昔を懐かしむ大人たちにも受け入れられていることを示しています。
新たな商品展開
近年の少子化により、駄菓子の販売量は減少傾向にあります。
製造メーカーは、この状況に対応するため、様々な工夫を凝らしています。
たとえば、商品にバーコードを付けて流通を効率化したり、1袋に4連や5連のパックにして販売単価の向上を図ったりしています。
また、ショッピングセンターへの出店を増やすなど、家族で来店する顧客をターゲットにした展開も進められています。
価格動向
駄菓子の価格も、時代の変化とともに上昇しています。
長年10円だった「うまい棒」が15円に値上げされるなど、インフレの影響が見られます。
原材料や人件費の高騰が、価格に反映されているのです。
それでも、「子どもが気軽に買える価格帯」という駄菓子の基本的な性質は保たれています。
現代における駄菓子の定義
明確な基準の不在
現代において、駄菓子の明確な定義はありません。
一般的には、50円以下の小分けで販売されているお菓子を指すことが多いです。
しかし、メーカーや販売店によって、その基準は異なります。
「中菓子」の存在
ただし、駄菓子屋で販売される商品には、小袋のスナック菓子や小さなカップ麺なども含まれます。
これらの商品は、本来「中菓子」という少し上位のカテゴリーに分類されます。
しかし、小中学生のお小遣いで買える価格帯であるため、販売現場では駄菓子として扱われています。
このように、時代の変化とともに、駄菓子の定義も柔軟に変化していると言えます。
まとめ
駄菓子は、単なる安価な菓子というだけではありません。
江戸時代から現代まで、常に時代の変化に適応しながら存在し続けてきました。
子どもたちの成長過程において貴重な体験を提供し、地域のコミュニティ形成に貢献し、日本の食文化の一部として重要な役割を果たしてきました。
販売形態や製造方法は変わっても、駄菓子が持つ本質的な価値は今後も受け継がれていくものと考えられます。