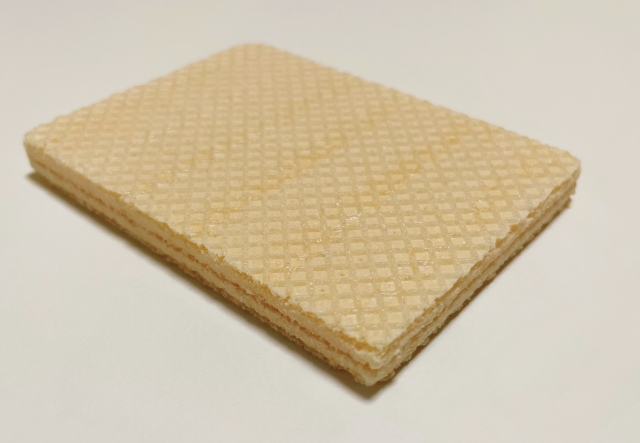ジャーマンケーキとは|ケーキの特徴や沖縄で普及した歴史
ジャーマンケーキとは
ジャーマンケーキは、アメリカで生まれ、日本では沖縄県を中心に親しまれているチョコレートケーキです。
しっとりとしたチョコレートスポンジに、ココナッツと練乳を合わせたフィリングを重ねる構成が特徴で、口に入れるとシャリッとした食感が広がります。
普通のチョコレートケーキとは異なる、南国らしい甘さと軽い口当たりが魅力です。
ドイツのケーキではない
「ジャーマンケーキ」と聞くと、ドイツ菓子を連想する人もいます。しかし、このケーキとドイツ文化のあいだに関連性はありません。ドイツの地域菓子や伝統的なチョコレートケーキとはまったく別物です。
名前の背景には、チョコレートづくりに大きな功績を残したアメリカ人開発者の存在があります。
名称の誤解が生まれた背景には “German=ドイツ” という英単語の印象がありますが、由来をたどると国名ではなく、ある人物の姓に行き着きます。
なぜジャーマンと言うのか
ジャーマンケーキの名称は、アメリカの菓子材料メーカー「ベーカーズチョコレート社」に勤務していたサミュエル・ジャーマン(Samuel German)の功績に由来します。
1852年、彼は家庭でも扱いやすいチョコレートを目指し、ビターよりも甘味を加えた「焼き菓子向けダークチョコレート」を開発しました。
このチョコレートは、ケーキ生地に混ぜやすく、風味も安定していることから、家庭用製菓材料として広まりました。
ジャーマンは開発者の名前
会社は開発者を称える意味を込め、この製品を「ベーカーズ・ジャーマンズ・スイート・チョコレート」という商品名で販売しました。
つまり、ケーキ名の「ジャーマン」とはサミュエル・ジャーマン氏の姓を指すものであり、「ドイツ風」という意味ではありません。
ジャーマンケーキは「ジャーマン氏が生み出したチョコレートを使ったケーキ」という位置付けで誕生した、アメリカ発祥のチョコレートケーキなのです。
ジャーマンケーキが普及した経緯
主婦によるレシピ投稿
サミュエル・ジャーマン氏が開発したチョコレートが発売されてから約100年後の1957年、アメリカ・テキサス州ダラスで大きな転機が訪れます。
地元に住む一人の主婦が、ジャーマン氏のチョコレートを使った自作のケーキレシピを地方新聞へ投稿したのです。
このレシピは、チョコレートケーキの濃厚さに加えてココナッツと練乳のフィリングを組み合わせたユニークな構成で、多くの読者の関心を集めました。
家庭の味として親しみやすく、作りやすかったことも注目された理由と考えられます。
企業による宣伝活動
この反響にいち早く目を留めたのが、当時ベーカーズチョコレートの商標を持っていたゼネラルフーヅ社でした。
同社は、このレシピを自社製品のプロモーションに活用することを決め、アメリカ各地へ積極的に広めていきました。
新聞、雑誌、レシピブックなどを通じて紹介された結果、ジャーマンケーキは短期間で全国的な知名度を獲得します。
家庭向け商品の宣伝とレシピ普及が相乗効果を生み、ケーキそのものの人気に拍車がかかりました。
現在では、こうした歴史を象徴するように、アメリカでは毎年6月11日が「ジャーマンケーキの日」として制定されています。
ジャーマンケーキの構造と特徴
ジャーマンケーキの基本構造は、チョコレート味のスポンジケーキを複数段に重ね、その間にクリームを挟み、最上部に特別なフィリングを塗ったものです。
ジャーマンケーキは、主にチョコレートスポンジ、バタークリーム、そしてココナッツフィリングの3つの要素から成り立っています。
チョコレートスポンジは、通常2段または3段に重ねて使われます。
スポンジ
ベースとなるチョコレートスポンジは、ふんわりとした軽やかな食感に仕上げられています。
見た目の印象よりも重すぎず、食べやすいのが特徴です。
バタークリーム
スポンジの間に挟まれるクリームは、多くの場合バタークリームが使用されます。
このバタークリームは、多くの場合バニラ味で、チョコレートスポンジの風味を引き立てる役割を果たしています。
ココナッツフィリング
ジャーマンケーキを特徴づける要素は、最上部にたっぷりと塗られるココナッツフィリングです。
このフィリングは、細かく刻んだココナッツを練乳と一緒に煮詰めて作る白いペースト状のものです。
甘さとともにココナッツ独特の風味と香りを持っています。
このフィリングを作る際、重要なのは、ココナッツの食感を完全になくしてしまわず、シャリシャリとした歯応えを残すように調理することです。
この独特の食感が、ジャーマンケーキを他のチョコレートケーキと区別する要素となっています。
チョコレートの滑らかさ、クリームの柔らかさ、そしてココナッツのシャリシャリ感が口の中で組み合わさることで、他のケーキでは味わえない独特の食体験が生まれます。
ジャーマンケーキのバリエーション
ジャーマンケーキには、製造する店によっていくつかのバリエーションが見られます。
店によっては、ココナッツフィリングに砕いたクルミなどのナッツ類を加えることがあります。
ナッツ類を加えることで、フィリングの食感にさらに変化と香ばしさが生まれます。
また、スポンジの側面には、細かいスポンジのクラム(パン粉のような細かい破片)をまとわせることで、見た目と食感に変化を付ける場合もあります。
ただし、このココナッツの風味と食感は好みが分かれる要素でもあります。
ココナッツが好きな人にとっては魅力的な特徴となりますが、苦手な人には敬遠される場合もあります。
ジャーマンケーキが沖縄で普及した歴史
アメリカで誕生したジャーマンケーキが、遠く離れた日本の沖縄県で広く親しまれるようになった背景には、特殊な歴史的経緯があります。
第二次世界大戦後:アメリカ統治下の沖縄
第二次世界大戦終結後の沖縄は、日本本土とは異なる歴史を歩みました。
沖縄は、1972年の日本復帰まで、約27年間にわたってアメリカの統治下に置かれました。
アメリカ統治下の沖縄には、アメリカの生活様式や食文化が大量に流入しました。
缶詰のコンビーフやランチョンミート、タコス、ステーキといった料理が沖縄の食卓に並ぶようになったのも、この時代です。
これらの食べ物は、現在でも沖縄の食文化に深く根ざしており、本土とは異なる独特の料理文化を形成しています。
この文化的変化の中で、パンやケーキなどの洋菓子も沖縄に広まっていきました。
ジミーベーカリー創業者「稲嶺盛保」
沖縄へのジャーマンケーキの普及には、ジミーベーカリーの創業者である稲嶺盛保さんの存在が深く関わっています。
稲嶺さんは1930年に那覇市で生まれ、戦後の16歳の時から北中城の米軍基地で働いていました。
戦時中と戦後の混乱期を経験した沖縄の人々にとって、基地内の食堂に並ぶボリュームのある料理やケーキは、当時の沖縄にはない「豊かな食」に見えたのです。
稲嶺さんは、基地内での仕事を通じて、アメリカの食文化に強い憧れを抱き、「フェンスの外の沖縄にも、このような豊かな食を届けたい」という想いを持つようになりました。
ジミーグロセリーの設立
1956年、稲嶺さんは貯めた資金でアメリカの食品を販売する「ジミーグロセリー」という小さな商店を宜野湾市に開きました。
「ジミー」という店名は、基地で働く際、アメリカ人から稲嶺さんが呼ばれていた愛称から採用されました。
稲嶺さんは、単に商品を販売するだけでなく、本格的なアメリカ式のパンやケーキの製造販売も開始することを決めました。
そのために、戦前にパンや菓子の職人として働いていた経験のある米兵をアルバイトとして雇い、本場のレシピを学びました。
ジャーマンケーキもこの時期に沖縄で作られ始めたとされています。
沖縄住民への定着
ジャーマンケーキは、最初、基地関係者の間で評判となり、その後、徐々に基地の外の沖縄住民の間にも広がっていきました。
当時の沖縄の人々にとって、ジャーマンケーキは衝撃的な体験でした。
従来の沖縄には、サーターアンダギーやちんすこうといった伝統的な菓子はありましたが、チョコレートとココナッツを組み合わせたこのようなケーキは存在していませんでした。
特に、ココナッツフィリングの独特な食感は、多くの人にとって初めてでした。この新しい味は次第に受け入れられ、沖縄の人々の間に定着していきました。
1958年、稲嶺さんの店は「ジミーベーカリー」と名前を変更し、ジャーマンケーキは看板商品の一つとして、着実に沖縄の人々に親しまれるようになっていきました。
本土復帰後の変化:材料の切り替え
1972年の日本復帰の際、通貨がアメリカドルから日本円に変わり、材料を量る単位もポンドやオンスからキログラムやグラムに変更されました。
また、小麦粉などの主要な材料も、それまでのアメリカ産から日本産に切り替わりました。
これらの材料の変化は、ケーキの味や食感に影響を与える可能性があったため、ジミーベーカリーの従業員たちは、全てのレシピを見直し、試行錯誤を重ねながら、愛されてきた味を守る努力を続けました。
この時期の取り組みが、現在まで続くジャーマンケーキの品質維持につながっています。
1976年、ジミーベーカリーはスーパーマーケット業態に転換し、現在の「ジミー」となりましたが、ジャーマンケーキの製造販売は途切れることなく続けられています。
現代沖縄でのジャーマンケーキ
現在の沖縄において、ジャーマンケーキは県民にとって非常に身近な存在です。
洋菓子店はもちろん、スーパーマーケットのベーカリーコーナー、コンビニエンスストアでも販売されており、沖縄で生活する人でこのケーキを知らない人はほとんどいません。
家庭と地域の集まりでの役割
沖縄の家庭や地域社会において、ジャーマンケーキは特別な役割を果たしています。
家族の集まり、お祝いの席、誕生日、お盆、年末年始、冠婚葬祭など、人々が集まる様々な機会にこのケーキが登場します。
沖縄には、季節ごとに家族や友人が集まる風習があり、そのような場面で大人数が分けて食べられるホールケーキが重宝されます。
実際、沖縄の店舗では一人用のカットケーキよりもホールケーキの方が売れ行きが良いという傾向が見られます。
集まった人々がケーキを切り分けて一緒に食べることで、コミュニケーションが生まれ、絆が深まるという側面もあるでしょう。
販売形態の多様化
現在は、伝統的な円形のホールケーキに加えて、一人用のカットケーキ、個包装されたマドレーヌ型のもの、四角い箱型のもの、パウンドケーキタイプのものなど、用途や好みに応じて選択できる多様な形態で販売されています。
これは、核家族化の進行や、進学や就職で県外に出る人が増えたことによる配送に適した商品へのニーズに応えるためです。
まとめ
ジャーマンケーキは、戦後復興期に基地で働く一人の青年が抱いた「豊かな食を届けたい」という純粋な想いから始まり、70年近い年月をかけて沖縄の日常生活に深く溶け込んでいきました。
このケーキの歴史は、アメリカ統治下での文化的影響、本土復帰に伴う変化、その後の社会発展といった戦後沖縄の歴史的変遷と重なっています。
沖縄県外に住む沖縄出身者の中には、故郷を離れて初めて「ジャーマンケーキが沖縄でしか売られていない」という事実を知る人も多く、わざわざ沖縄から取り寄せる人もいます。
これは、ジャーマンケーキが沖縄のアイデンティティや故郷への思いと結びついていることを示しています。
本土ではほとんど知られていないこのケーキが、沖縄では当然の存在として受け入れられ続けているのは、沖縄の人々の生活様式や価値観と深く結びついているからだと言えます。
このように、ジャーマンケーキはアメリカで生まれ、沖縄で育った特別なケーキであり、多くの人々の思いと努力が込められた食文化の産物なのです。