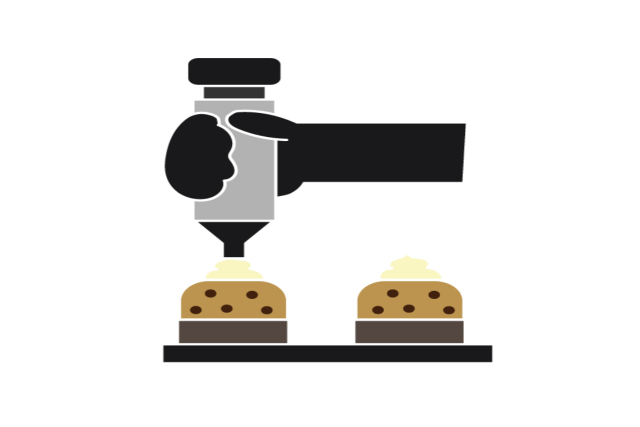農産物とは|定義・意味、かんたん説明【食品表示法基準】

農産物の表示は食品表示法に基づいて定められています
食品表示は消費者の食品選択の権利を保護するだけでなく、生産者と消費者の信頼関係を築く重要な架け橋となっています。
この記事では農産物の表示に関する基本的な知識をわかりやすく解説します。
農産物とは何か
農産物とは、食品表示基準の別表第2の1に掲げられているものを指します。
これにはきのこ類、山菜類、たけのこも含まれます。農産物は大きく分けて以下のような種類があります。
- 米穀
- 麦類
- 豆類
- 野菜
- 果実
米穀について
米穀には収穫後に調整、選別、水洗いなどを行ったもの、単に切断したもの、精麦や雑穀を混合したものが含まれます。
重要ポイント:
- 「消費者に販売するために容器包装に入れたもの」については、別途「玄米及び精米」としての表示ルールが適用されます
- 精米の鮮度は品質に直結するため、精米時期の表示は消費者にとって重要な情報となります
麦類について
麦類には収穫後に調整、選別、水洗いなどを行ったもの、単に切断したものが含まれます。
以下のような穀物が該当します
- 大麦
- はだか麦
- 小麦
- ライ麦
- えん麦
これらは私たちの食生活において重要な穀物であり、パンや麺類の原料として使用されています。特に小麦は多くの加工食品の基礎となる重要な農産物です。
雑穀について
雑穀には収穫後に調整、選別、水洗いなどを行ったもの、単に切断したものが含まれます。
以下が雑穀に該当します
- とうもろこし
- あわ
- ひえ
- そば
- きび
- もろこし
- はとむぎ
- その他の雑穀
雑穀は主食である米や麦以外の穀物を指し、栄養価が高いことで知られています。近年は健康志向の高まりから、雑穀を日常的に摂取する消費者が増えています。ビタミン、ミネラル、食物繊維などが豊富に含まれており、バランスの取れた食生活に貢献します。
豆類について
豆類には収穫後に調整、選別、水洗いなどを行ったもの、単に切断したものが含まれます。ただし未成熟のものは除かれます。
以下が豆類に該当します
- 大豆
- 小豆
- いんげん
- えんどう
- ささげ
- そら豆
- 緑豆
- 落花生
- その他の豆類
豆類はタンパク質や食物繊維が豊富な食品です。特に大豆は「畑の肉」とも呼ばれ、良質なタンパク質源として日本の食文化に欠かせない存在です。また、遺伝子組換え技術が用いられることもある農産物であるため、表示に関する特別なルールが適用されることがあります。
野菜について
野菜には収穫後に調整、選別、水洗いなどを行ったもの、単に切断したもの、単に凍結させたものが含まれます。
以下の野菜に分類されます
- 根菜類(にんじん、じゃがいも、大根など)
- 葉茎菜類(キャベツ、ほうれん草、ねぎなど)
- 果菜類(なす、トマト、きゅうりなど)
- 香辛野菜及びつまもの類(わさび、しょうがなど)
- きのこ類(しいたけ、しめじ、まいたけなど)
- 山菜類(わらび、ぜんまい、ふきなど)
- 果実的野菜(スイカ、メロンなど)
- その他の野菜
野菜は毎日の食事に欠かせない食材です。ビタミン、ミネラル、食物繊維などの栄養素を豊富に含んでおり、健康的な食生活の基礎となります。また、きのこ類については栽培方法(原木栽培・菌床栽培)の表示が求められる場合があります。
果実について
果実には収穫後に調整、選別、水洗いなどを行ったもの、単に切断したもの、単に凍結させたものが含まれます。
以下のように分類されます
- かんきつ類(みかん、レモン、グレープフルーツなど)
- 仁果類(りんご、梨など)
- 核果類(もも、すもも、あんずなど)
- しょう果類(バナナ、パイナップルなど)
- 殻果類(くるみ、アーモンドなど)
- 熱帯性及び亜熱帯性果実(マンゴー、パパイヤなど)
- その他の果実
果実はビタミンや食物繊維が豊富で健康維持に役立ちます。特に一部の果実については、防かび剤などの添加物が使用されることがあるため、添加物の表示が必要となる場合があります。
その他の農産食品について
その他の農産食品には収穫後に調整、選別、水洗いなどを行ったもの、単に切断したもの、単に凍結させたものが含まれます。
以下のように分類されます
- 糖料作物(さとうきびなど)
- こんにゃくいも
- 未加工飲料作物(コーヒー豆、茶葉など)
- 香辛料原材料(唐辛子、コショウなど)
- 他に分類されない農産食品
これらは様々な用途で使用される農産物であり、それぞれ特有の表示ルールが適用される場合があります。
農産物の表示義務事項
農産物を消費者向けに販売する際には、表示が必要な事項があります。
基本的な表示事項と、特定の条件下で必要となる表示事項を理解しましょう。
基本的な表示事項
消費者向けに販売する際に必ず表示が必要になる事項は「名称」と「原産地」です。これらは最低限必要な情報として定められています。
名称の表示について
名称については、その内容を表す一般的な名称を表示する必要があります。
例えば「りんご」「じゃがいも」「にんじん」などのように、一般的に認識されている名前を使用します。特殊な呼び名や商品名だけではなく、一般的な名称を表示することが重要です。
例えば、「とちおとめ」という品種のいちごを販売する場合、「とちおとめ」だけでなく「いちご」という一般的な名称も表示する必要があります。消費者が一目で何の食品かを理解できるようにするためです。
原産地の表示について
原産地については、国産品には都道府県名を、輸入品には原産国名を表示する必要があります。
ただし、国産品は市町村名その他一般に知られている地名を、輸入品は一般に知られている地名をもってこれに代えることができます。
国産品の原産地表示例:
- 都道府県名:「北海道」「東京都」「鹿児島県」
- 一般に知られている地名:「下仁田」「銚子」「石垣島」「伊豆・下田」「世田谷」「桜島」「甲州」「信州」
輸入品の原産地表示例:
複数の原産地で同じ種類の農産物を混合している場合は、全体重量に占める割合の高いものから順に表示する必要があります。例えば、国産のにんじんとアメリカ産のにんじんを混合して販売する場合、重量の割合が多い原産地を先に表示します。
原産地が異なる数種類の農産物の詰め合わせは、それぞれの農産物の名称に原産地を併記する必要があります。例えば、野菜の詰め合わせセットでは「にんじん(北海道産)」「じゃがいも(長崎県産)」「玉ねぎ(兵庫県産)」のように表示します。
特定条件下での表示事項
一定の要件に該当する場合に表示が必要になる事項があります。これらは特定の食品や特定の処理を行った食品に適用されます。
放射線照射食品の表示
放射線を照射した場合には、放射線を照射した旨と放射線を照射した年月日を表示する必要があります。消費者が食品の処理方法を知るための重要な情報です。
日本では、現在、ジャガイモの発芽防止目的での放射線照射のみが認められています。表示例としては「放射線照射済み」「照射年月日:2023年10月1日」などの形式で表示します。
特定保健用食品の表示
特定保健用食品として販売する場合は、特定保健用食品としての表示方法に準じて表示する必要があります。特定の保健機能があることを表示するためには厳格な基準を満たす必要があります。
特定保健用食品は消費者庁長官の個別審査を受けて許可された食品であり、特定の保健の用途に資する旨を表示することができます。特定保健用食品マークや許可表示、注意喚起表示などが必要となります。
機能性表示食品の表示
機能性表示食品として販売する場合は、機能性表示食品としての表示方法に準じて表示する必要があります。一般用生鮮食品における機能性表示食品の場合、一般用加工食品における機能性表示食品の表示事項に加えて、以下の事項を表示しなければなりません:
- 保存の方法
- 食品関連事業者の氏名または名称及び住所
機能性表示食品は事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。消費者庁に届出をすることで、機能性を表示することができますが、特定保健用食品とは異なり国の審査を受けたものではありません。
遺伝子組換え農産物の表示
大豆・とうもろこしなどの遺伝子組換え農産物については、基準に基づく表示が必要です。また、「遺伝子組換えでない」等と表示するためには、分別生産流通管理が必要です。遺伝子組換え食品に関する消費者の選択権を保護するための制度です。
現在、表示義務があるのは以下の8作物33品目です:
- 大豆(枝豆、大豆もやしを含む)
- とうもろこし
- ばれいしょ
- なたね
- 綿実
- アルファルファ
- てん菜
- パパイヤ
これらの農産物を原材料とする加工食品についても、一定の条件下で表示が必要となります。
乳児用規格適用食品の表示
食品表示基準の対象となる乳児用食品の範囲は、食品、添加物等の規格基準において規定された「乳児用食品」の対象である食品と同じで、1歳未満の乳児を対象としています。
乳児用規格適用食品である旨の表示は、食品衛生法に基づき乳児用食品に係る放射性物質の規格が適用される食品であることを明記することを原則としています。ただし、消費者が乳児用食品であることを容易に判別できるものについては、表示は不要であるとの考えから省略規定が設けられています。
表示例としては「乳児用規格適用食品」などと記載します。
食品の特性に応じた表示事項
食品表示基準の別表第24に掲げる個別の食品には、食品の特性に応じて表示が必要な事項が定められています。特定の食品にはそれぞれの特性に合わせた表示が求められます。
特定の農産物における表示事項
玄米及び精米 消費者に販売するために容器包装に入れられたものに限り、以下の表示が必要です:
- 名称
- 原料玄米
- 内容量
- 精米時期
- 販売者など
これにより消費者は精米の鮮度や品質を判断することができます。特に精米は時間の経過とともに風味や栄養価が低下するため、精米時期の表示は重要な情報となります。
しいたけ 栽培方法の表示が必要です。原木栽培なのか菌床栽培なのかを明示することで、消費者の選択に役立ちます。
表示例:
- 「原木栽培」
- 「菌床栽培」
特定の果実・野菜 以下の農産物には、特別な表示事項が必要とされています:
これらの果物・野菜には以下の表示が必要です:
- アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る)
- 保存の方法
- 消費期限または賞味期限
- 添加物
- 加工所の所在地及び加工者の氏名または名称
これらの果物には防かび剤などの添加物が使用されることがあるためです。特に輸入品については、防かび剤やワックスなどの食品添加物が使用されていることが多く、消費者への情報提供が重要です。
密封された特定商品の表示事項
特定商品の販売に係る計量に関する政令第5条に規定する特定商品であって密封されたものには、以下の表示が必要です:
- 内容量
- 食品関連事業者の氏名または名称及び住所
密封とは、商品を容器に入れ、または包装して、その容器や包装またはこれらに付した封紙を破棄しなければ、内容量を増減できないようにすることを指します。消費者が内容量を確認できない状態で販売されるため、正確な内容量表示が重要となります。
農産物が加工食品となるケース
次のような場合は、農産物ではなく加工食品として扱われます。加工食品には別の表示ルールが適用されるため注意が必要です。
加熱処理等を行った場合
- タケノコ水煮
- ふき水煮
- 水煮のわらび・ゼンマイなど
日干し等の乾燥を行った場合
- 乾しいたけ
- 干しぶどうなど
異種混合を行った場合
- 異種混合したカット野菜
- カット果物など
これらは単なる調整や選別、洗浄、切断、凍結ではなく、加工処理が施されているため、加工食品として扱われます。加工食品には名称、原材料名、添加物、内容量、賞味期限、保存方法、製造者などの表示が必要となります。
表示の責任者と表示位置
農産物の表示には責任者と表示位置に関するルールが定められています。正しい位置に適切な表示を行うことが求められます。
表示を行う責任者
表示をする者は、食品関連事業者です。生産者から最終消費者へ直接販売する小売業者までの流通過程の全ての者が該当します。海外から農産物を輸入する輸入者も表示義務があります。
表示義務がない場合:
- 設備を設けて飲食させる場合(レストランなど)
- 容器包装に入れずに生産地で販売する場合(農家の直売所など)
- 容器包装に入れずに不特定若しくは多数の者に対して譲渡する場合(無償譲渡)
表示位置と文字の大きさ
容器包装に入れられた農産物の場合
容器包装に入れられた農産物には、容器包装を開かないでも容易に見ることができるように、その容器包装の見やすい箇所に表示する必要があります。
ただし、以下の事項については、食品に近接した掲示その他の見やすい場所に表示することができます:
- 名称(放射線を照射した食品、保健機能食品及びシアン化合物を含有する豆類を除く)
- 原産地
- 遺伝子組換え農産物に関する事項
- 栽培方法
容器包装に入れられていない農産物の場合
容器包装に入れられていない農産物には、食品に近接した掲示その他の見やすい場所に表示する必要があります。例えば、店頭の陳列棚に表示札やPOPを設置する方法が一般的です。
文字の大きさ
容器包装への表示に用いる文字は日本産業規格Z8305(1962)に規定する8ポイントの活字以上の大きさの文字を使用する必要があります。
ただし、表示可能面積がおおむね150cm²以下のものは、5.5ポイントの活字以上の大きさの文字を使用することができます。消費者が容易に読める文字の大きさを確保することが重要です。
まとめ
農産物の表示は消費者の食品選択を支援するために重要な役割を果たしています。名称や原産地といった基本的な表示事項に加え、特定の食品や条件に応じた表示事項を正確に表示することで、消費者は安心して農産物を購入することができます。
生産者や販売者は、適切な表示を行うことで消費者との信頼関係を構築し、自社製品の価値を適切に伝えることができます。また、消費者は表示内容を確認することで、自分のニーズや価値観に合った農産物を選択することができます。
食品表示制度は消費者保護と公正な取引の確保を目的としており、すべての食品関連事業者はこのルールを遵守する必要があります。