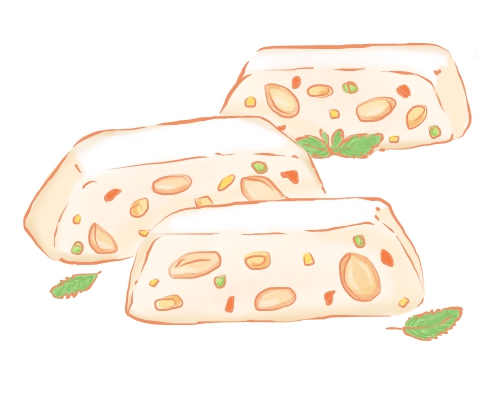浅田飴とは|発祥起源や普及した理由などの歴史

浅田飴とは


浅田飴(あさだあめ)は江戸時代に浅田宗伯という医師によって開発された、喉の不調を和らげるための伝統的な日本の薬用キャンディです。
喉の痛みや咳を緩和するために広く使用され、現代でも多くの人々に愛用されています。
成分にはカリンエキスやハーブが含まれており、これらが喉を保護して炎症を抑える効果があります。
特に風邪をひいたときや乾燥した季節に喉の調子を整えるためにも食べられています。
長い歴史と信頼性を誇る浅田飴は日本国内のドラッグストアやスーパーなどで簡単に手に入れることができます。
浅田飴の歴史
浅田飴の発祥起源
浅田飴が初めて世に登場したのは明治20年(1887年)のことです。当時、その名は“御薬(おんくすり)さらし水飴”と呼ばれていました。
江戸幕府の御典医であり、漢方医学の権威であった浅田宗伯氏の処方を受け継いだ堀内伊三郎がこの薬用水飴を考案しました。
初めは“たん、せき一切、肺病の持薬、ひきかぜ、よわき人、老人の滋養薬”として販売されました。
その製法は非常に手間がかかるもので、大きな鍋でキキョウやマオウなどの生薬を煎じ、水飴に練り込むというもの。
この誠実な製薬工程が人々に信頼されて、後の浅田飴の成功の礎となりました。
浅田飴が生まれた背景
浅田飴が生まれた背景には、明治から昭和にかけての漢方医学の発展が関係しています。
当時、漢方薬は西洋医学に押されながらも、根強い支持を受けていました。
浅田飴は、この漢方医学の伝統を受け継ぎながら、近代的な製薬技術を取り入れることで、医薬品としての地位を確立しました。
浅田宗伯の生い立ちと功績
浅田宗伯は文化12年(1815年)、信州筑摩郡栗林村(現在の長野県松本市)に生まれました。
浅田宗伯は幼い頃から医業を志し、京都や江戸で漢方医学や儒学を学びました。
その後、江戸で漢方医として開業し、幕府の御典医や幼少期の大正天皇の侍医を務めるなど、多くの功績を残しています。
彼は医学書の執筆にも注力していましたので、生涯で200巻以上の著作を残し、その中には『傷寒論識』や『古方薬議』などの名作が含まれています。
浅田飴の処方を伊三郎に伝授した宗伯の功績は現代にも受け継がれています。
浅田飴の初期の形状
発売当初の浅田飴は水飴タイプでしたが、持ち運びや服用の不便さが指摘されるようになり、大正4年(1915年)に固形化が試みられました。
その試行錯誤を経て、翌年には現在のような形状が完成。携帯性と使いやすさが格段に向上し、多くの人々に愛用されるようになりました。
浅田飴の進化
浅田飴の味も時代とともに進化してきました。
昭和37年(1962年)には、従来のニッキ味に加えて、洋風化に合わせたクール味が登場しました。
その後、昭和61年(1986年)にはトロピカルなパッション味が発売。
さらに2003年にはシュガーレスの浅田飴も開発され、健康志向の消費者にも支持されています。
このように浅田飴はさまざまな時代に生まれた多様なニーズに応える努力を続けているのです。
浅田飴の広告戦略
浅田飴の成功には、ユニークな広告戦略も一役買っています。
ころんと飴を出すブリキ缶や歌舞伎絵をあしらったカラフルな広告は、浅田飴が注目を集めた要因の一つです。
また、永六輔さんが出演するテレビコマーシャルも非常に親しみやすいもので、幅広い世代に商品を浸透させることに成功しました。
これらの広告活動は浅田飴のブランドイメージを高める重要な要素となっています。
浅田飴と競合商品との違い
浅田飴が世に出た後、大正2年(1913年)には森永製菓が「コーフドロップス」を発売。昭和46年(1967年)には龍角散トローチが登場しています。
これらの競合商品が次々と市場に現れる中で、浅田飴は“良薬にして口に甘し”という独自のキャッチコピーや、生薬処方の強みを生かして、他製品との差別化が成功しています。
浅田飴の名前の由来
明治22年(1889年)、堀内伊三郎の長男である伊太郎が「御薬さらし水飴」を「浅田飴」と改称しました。
この名前の由来は、処方を考案した浅田宗伯にちなんでいます。
さらに“良薬にして口に甘し”というキャッチコピーも同時に採用されました。
この言葉は、薬としての確かな効能を持ちながらも、服用しやすい甘さを兼ね備えた商品の特性を的確に表現しています。
この新しい名前とキャッチコピーが広まり、浅田飴は一躍ロングセラー商品となりました。
浅田飴の信頼性
浅田飴の基本理念は“薬としての確かな効き目を、服用しやすく提供する”というものです。
この理念に基づき、キキョウやカッコンなどの漢方生薬を使用した処方が守られています。
咳や喉の不調に対する確かな効果が得られると、昔から多くの消費者から信頼されています。
まとめ
浅田飴は明治時代から現代に至るまで、その時代に合わせた改良と進化を続けてきました。
現代でも浅田飴は多様な商品展開を行っており、例えば無糖タイプの商品を発売したり、新たな味を開発したり。
また、公式ウェブサイトやSNSを活用した情報発信にも力を入れており、若い世代にも親しみやすいブランドとして進化を続けています。
漢方医学の伝統を受け継ぎながら、医薬品としての確かな効果と親しみやすさを両立させた浅田飴は、今後も多くの人々に愛され続けることでしょう。