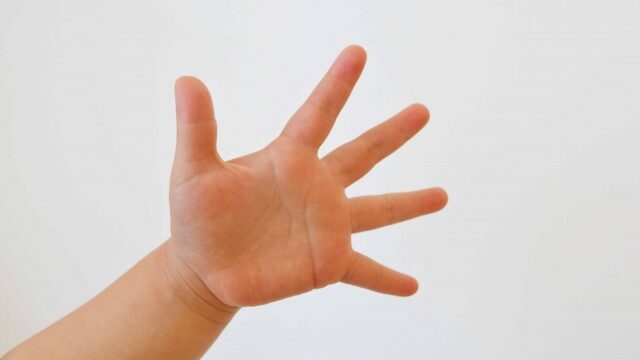世界一まずいグミ|ハリボー ラクリッツ シュネッケン

世界には驚くほど多様な美味しいお菓子がありますが、中には「まずい」と評判になり、かえって注目を集めるユニークなお菓子も存在します。ドイツの国民的お菓子メーカー「ハリボー」が手がける黒いグミ「シュネッケン」。甘草(ラクリッツ)が織りなす独特の苦味と香りがもたらす、一口でやみつき(?)になる体験談や、ドイツと日本の味覚の驚くべき違いを深掘り。罰ゲームやパーティーの話題にぴったりの「世界一まずいグミ」の魅力、そして北欧の強敵「サルミアッキ」との比較を通して、異文化の味覚の奥深さを探ります。
ハリボー ラクリッツ シュネッケンとは?
| 商品名 | HARIBO LAKRITZ SCHNECKEN(ハリボー ラクリッツ シュネッケン) |
|---|---|
| 製造国 | ドイツ |
| 名前の意味 | 「シュネッケン」=ドイツ語で「カタツムリ」 |
| 形状 | 渦巻き状(カタツムリの殻のような見た目) |
| 主成分 | ラクリッツ(甘草) |
| 日本での価格帯 | 約250円(ヴィレッジヴァンガードなど) |
このお菓子の正式名称は「ハリボー ラクリッツ シュネッケン (HARIBO LAKRITZ SCHNECKEN)」と言います。
「シュネッケン」とはドイツ語で「カタツムリ」を意味し、その名の通り、渦巻き状のユニークな形をしています。
まるでカタツムリの殻のように見えるため、この名前が付けられました。
シュネッケンはタイヤ味のグミ!?
このラクリッツ シュネッケンですが、日本では見た目・におい・味・食感、何を思ってか「タイヤ味」という衝撃的なニックネームで知られています。
パッケージに描かれた自転車のタイヤのイラストも相まって、多くの人がタイヤを連想するほど、その黒い色合いと硬い食感が印象を強くしています。
「まずさ」の秘密は「ラクリッツ」
シュネッケンの味の鍵を握るのは、主要成分である「ラクリッツ」です。
ラクリッツとは、甘草(リコリス)という植物の根から抽出される成分で、漢方薬の原料としても使われることがあります。
このラクリッツが持つ独特の苦味と香りが、シュネッケンの個性的な味を生み出しているのです。
シュネッケンを食べた人の感想
実際にシュネッケンを試した人々の感想は、まさに衝撃的の一言に尽きます。
プロレスラーの丸藤選手は「これぞ世界一シリーズにふさわしい香りと味」「臭い!タイヤを食っているようだ」と表現しています。
ある体験者は「最初の一口は大丈夫だったが、噛み続けるうちに何とも言えない苦味や漢方のような味が押し寄せてきて、結局一口で断念した」と語っています。
特に興味深いのは、食べ方による味の変化です。
多くの人が食べ始めに「あれ、そんなに悪くないかも」と感じるものの、噛み続けるうちに強烈な苦味や独特の味が口いっぱいに広がるという体験談が多数報告されています。
多くの日本人にとって、シュネッケンは「人生で最上級にまずいお菓子」や「まずいを通り越してヤバさを感じる」レベルの衝撃的な味として認識されています。
ドイツと日本の味覚の違い
しかし、驚くべきことに、シュネッケンの本場であるドイツ人にとっては、全く異なる認識を持っています。
ドイツ人の友人からは「普通に美味しいし、なんで美味しくないの?子供のころから食べているし、老若男女問わず好きな人も多い」という声が聞かれるほど、現地ではごく一般的な味として受け入れられています。
ドイツにはシュネッケン以外にもさまざまな種類のラクリッツ味のハリボー商品があり、基本的に黒いグミや飴はラクリッツの可能性が高いです。
これらはドイツの伝統的な味覚文化の一部として、現地の人々には馴染み深い味なのです。
ハリボー社のラクリッツ製品
ハリボー社は2020年に創業100周年を迎えた世界最大の菓子メーカーです。
通常のグミは世界中で大人気ですが、このラクリッツ味のシリーズは、特に日本人には受け入れられにくい傾向にあります。
現在、日本でもヴィレッジヴァンガードなどの店舗で250円程度で購入できます。
一人で一袋全て食べ切るのは至難の業なので、友人数人とシェアして試してみるのがおすすめです。
罰ゲームやパーティーのネタとしておすすめ
シュネッケンは、真剣に美味しいお菓子として楽しむというよりは、罰ゲームやパーティーのネタとして活用されることが多いようです。
その衝撃的な味を体験として楽しんだり、話のネタとして盛り上がったりするユニークな商品と言えるでしょう。
味の衝撃を共有することで生まれる、コミュニケーションの一つの形とも言えます。
もう一つの「世界一まずいお菓子」:サルミアッキ
| 項目 | シュネッケン | サルミアッキ |
|---|---|---|
| 製造地域 | ドイツ | フィンランドなど北欧5カ国 |
| 主成分 | ラクリッツ(甘草) | リコリス + 塩化アンモニウム |
| 味の特徴 | 苦味・漢方風・タイヤ風味 | 強烈な塩味とアンモニア臭 |
| 見た目 | 渦巻き状・真っ黒 | 小粒の黒い飴 |
| 評価され方 | ドイツでは定番・日本では罰ゲーム | 北欧では人気・他国では敬遠されがち |
「世界一まずいお菓子」として注目されているのは、シュネッケンだけではありません。
もう一つ有名なのが、北欧の伝統的なお菓子「サルミアッキ」です。
サルミアッキは、塩化アンモニウムとリコリス(甘草の一種)を原料とした黒い小粒の飴で、強い塩味とアンモニア臭が特徴。
北欧5カ国では子供から大人まで親しまれる伝統的なお菓子ですが、北欧以外の地域ではその独特な味のため敬遠されがちです。
シュネッケンとサルミアッキの共通点
シュネッケンとサルミアッキは、どちらも現地では愛されている伝統的な味でありながら、他の地域の人々にとっては理解しがたい味として認識されている、という共通点があります。これは、食文化の違いが味覚の認識に与える影響の大きさを示す、非常に興味深い事例です。
これらの商品は、真剣に「美味しいお菓子」として楽しむものではなく、その独特な味を体験として楽しんだり、話のネタとして活用したりする用途で親しまれています。
異文化の味覚に触れることで、自分たちの味覚の基準を再認識したり、食文化の多様性を理解する機会にもなっているのかもしれません。世界にはさまざまな味覚の文化があり、それぞれが長い歴史の中で培われてきた背景を持っていることを、これらの商品は教えてくれているのです。
まとめ
「世界一まずいグミ」として日本で異彩を放つハリボーの「シュネッケン」は、その衝撃的な「タイヤ味」で多くの人々を魅了(?)しています。
甘草由来の「ラクリッツ」がもたらす独特の苦味と香りは、日本人にとっては罰ゲームレベルの体験となる一方で、本場ドイツでは老若男女に愛される日常的なお菓子です。
この味覚の大きなギャップは、水質を含む食文化の違いが大きく影響していると考えられます。
シュネッケンや北欧の「サルミアッキ」といった、現地の愛され菓子が他国で「まずい」と評される現象は、食文化の多様性と奥深さを私たちに教えてくれます。
これらのユニークなグミは、単に味を「楽しむ」だけでなく、友人との話題作りや、異文化理解のきっかけとしても、私たちに新たな体験を提供してくれるでしょう。