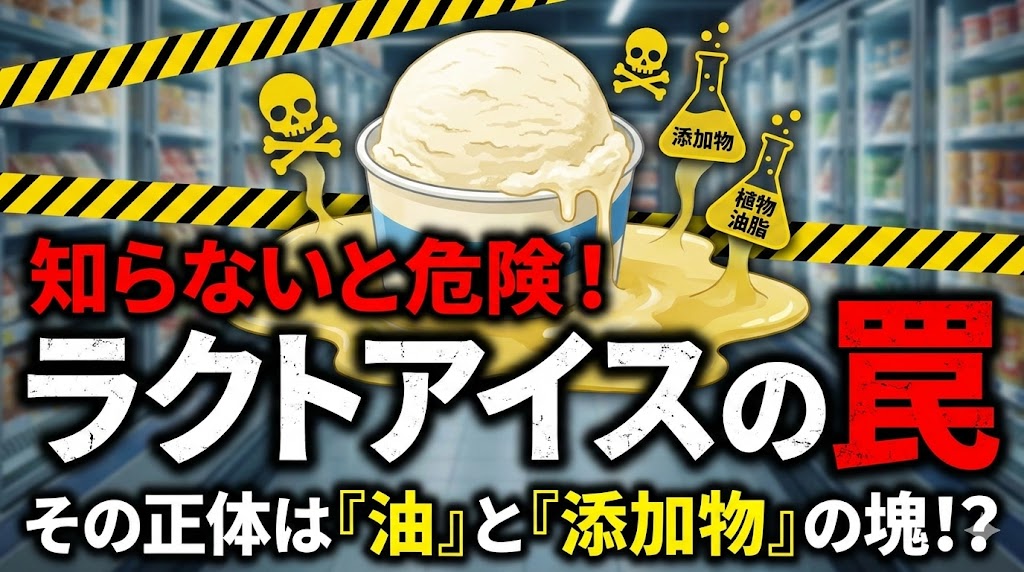ドンパッチとパチパチパニックに違いはあるの?【比較】

口の中で「パチパチ」とはじける不思議なキャンディーは、多くの人にとって忘れられない体験でしょう。
このユニークな食感を世に送り出してきた代表的なお菓子に、今も語り継がれ愛され続ける「ドンパッチ」と、現在もその人気を不動のものとしている「パチパチパニック」があります。
両者は同じ「パチパチ感」を共有しているため混同されがちですが、実はその歴史、製造元、そして市場での立ち位置に違いがあります。
しかし、それぞれが独立した存在でありながらも、日本の「パチパチキャンディー」という特別なジャンルを築き上げてきた中で、見えない関連性や共通の系譜が存在するのも事実です。
この記事では、これら二つのキャンディーの違いと比較、そして深いつながりを掘り下げていきます。
口の中の「パチパチ」現象の正体
この不思議な現象の正体は、実は科学的な原理に基づいた安全な仕組みです。
キャンディーの中には高圧の炭酸ガスが封入されており、口の中で唾液によって飴が溶けて薄くなると、内部に封じ込められていたガスの圧力に耐えきれなくなり、小さな破裂を起こします。
この微細な破裂が、あの独特の刺激と音を生み出しているのです。例えるなら、風船が割れる時に音が出るのと同じような現象が、口の中で小さなスケールで起こっているということになります。
製造方法
この技術は決して簡単ではありません。
製造方法は非常に特殊で、まず砕いたキャンディーを圧力の高いガスの中で溶かし、固め直して作ります。 圧力をかけながら加熱するため、特殊な設備が必要となり、高い技術力と専門的な知識が求められます。
この技術的な難しさから、日本でこのようなキャンディーを製造しているのは限られた企業だけという状況になっています。
安全性
パッケージの裏面には「勢いよくはじけることがあります」といった注意書きがありますが、これは危険性を示すものではありません。
主に子ども向けの商品であるため、不意にはじけた際の注意を促すためのものであり、食べることによって健康上の問題が起こるわけではありません。
パチパチ伝説の始まり「ドンパッチ」
「パチパチキャンディー」の記憶を語る上で欠かせないのが、かつて子どもたちの間で爆発的な人気を誇った商品。明治製菓(現:株式会社 明治)から発売されていた「ドンパッチ」です。
1970年代後半に登場したドンパッチは、口に入れると勢いよくパチパチと音を立てながら弾けるそのユニークな食感で、当時の子どもたちの心を瞬く間につかみました。まるで口の中で魔法が起こっているかのような体験は、子どもたちにとっての新しいエンターテイメントであり、瞬く間に駄菓子屋の定番商品となりました。
しかし、時代の流れとともに惜しまれつつも、ドンパッチは残念ながらすでに製造・販売を終了しており、現在では購入することができません。
それでも、多くの人にとって、ドンパッチは単なる過去のお菓子ではなく、今もなお「懐かしのお菓子」として強く記憶の中に残り、語り継がれ、愛され続けています。
現代のパチパチ定番「パチパチパニック」
ドンパッチが市場から姿を消した後、口の中でパチパチ弾けるお菓子を求める消費者のニーズが根強く残りました。その空白を埋め、現在もその楽しさを提供し続けているのが、アトリオン製菓が製造・販売する「パチパチパニック」です。
現在のパチパチパニックは、グレープ味、コーラ味、ソーダ味の3種類が基本ラインナップとして展開されています。さらに、季節や時期によって変わる4つ目の味も用意されており、消費者を飽きさせない工夫がされています。
スーパーや100円均一ショップなどで手軽に購入でき、子どもから大人まで幅広い層に支持されています。100円均一ショップでは「3つで100円(税別)」というお得な価格で販売されることが多くなっています。
前身商品の「シュワシュワパンチ」
パチパチパニックの「パチパチ」もまた、ドンパッチと同様に、飴の中に高圧の炭酸ガスを封入する独自の技術によって生み出されています。アトリオン製菓の前身である明治産業は、1979年にはすでにこの高圧キャンディーの生産を開始しており、これはドンパッチが発売された時期と重なります。
この技術を用いた商品は、1999年には「シュワシュワパンチ」という商品名で発売され、その後2007年に現在の「パチパチパニック」という名前に変更されました。つまり、パチパチ弾けるキャンディー自体は、このブランド名の下で20年以上の歴史を持つロングセラー商品として進化を続けているのです。
2つのパチパチキャンディーの関連性
ドンパッチとパチパチパニックは、法的な意味での関連性や直接的な事業継承、ブランドの継続性はありません。
製造元が異なり、それぞれ独立した商品として存在しています。
しかし、「口の中でパチパチ弾けるキャンディー」というユニークなジャンルにおいて、両者には間接的な関連性や、ある種の「系譜」を推察することができます。
共通の技術原理
ドンパッチもパチパチパニックも、高圧の炭酸ガスを飴の中に封入するという、共通の科学的原理に基づいています。この技術は高度であり、限られたメーカーしか扱えません。
アトリオン製菓(旧明治産業)が1979年から高圧キャンディー生産を開始したことは、ドンパッチが発売された時期と重なり、同時期に複数のメーカーが同様の技術開発を進めていた可能性、あるいは共通の技術的ルーツが存在した可能性を示唆しています。
手にした市場のニーズ
また、ドンパッチが市場から姿を消した後も、「口の中でパチパチ弾けるお菓子」を求める消費者のニーズは根強く残りました。そこに、後発である「シュワシュワパンチ」や「パチパチパニック」が登場し、その空白を見事に埋める形で人気を博しました。
多くの消費者にとって、パチパチパニックは、かつて夢中になったドンパッチの体験を呼び起こす存在であり、無意識のうちに「ドンパッチの代わり」あるいは「後継者」として認識されることがあります。実際にインターネット上のレビューなどでも、「昔食べたドンパッチのよう」といった感想が見られます。
「明治」というルーツ
ドンパッチとパチパチパニック。異なるメーカーから発売されたこれらの「パチパチ弾ける」お菓子には、実は興味深い繋がりがあります。
ドンパッチを製造していたのは明治製菓。一方、パチパチパニックを手掛けるアトリオン製菓は、元々明治の子会社である明治産業でした。
これは単なる偶然でしょうか。日本の大手菓子メーカーである明治グループが、同時期に「パチパチ弾ける」というユニークな技術に着目し、それぞれの商品を開発・展開していた状況を物語っています。
明治グループと関連企業の変遷
明治製菓(旧社名)
1916年に創業した菓子・医薬品の総合メーカーで、チョコレートやビスケット、ドンパッチなどの駄菓子も製造していました。2011年のグループ再編により、食品事業は株式会社明治に、医薬品事業はMeiji Seika ファルマ株式会社に分離され、それぞれ独立した事業体として再出発しました。
明治(株式会社明治)
明治グループの食品部門を担う中核企業です。2011年に明治乳業が明治製菓の食品事業を統合し、社名を「株式会社明治」に変更して誕生しました。現在はお菓子、乳製品、飲料、栄養食品など幅広い製品を手がけています。
明治産業(旧:明治製菓の子会社)
明治製菓の製造子会社として設立され、ヨーグレットやハイレモンなどの錠菓やグミの製造を担当してきました。現在も明治グループの製造部門の一翼を担っており、独自の技術で菓子の品質を支えています。
このように、明治製菓の子会社として「パチパチ」の技術を培っていた明治産業は、2023年に丸紅グループへ譲渡され、現在はアトリオン製菓として独立しています。しかし、その根底には明治製菓時代から受け継がれた技術が息づいています。
直接的な「血縁」はないものの、同じ「明治」という大きな菓子メーカーグループの周辺で「パチパチ」の技術が育まれ、やがてアトリオン製菓へと受け継がれ、現代までその系譜が繋がっている可能性も考えることができるでしょう。
パチパチパニックの急成長
近年、パチパチパニックは驚異的な売上成長を遂げています。
2024年3月期の売上高は約7億円に達し、なんと10年前と比較して10倍もの成長を記録しました。また、2021年度は2015年度の4倍以上の売上を記録するなど、長年販売している商品としては異例の急成長を続けています。
開発部の担当者も少し不思議に思うほどで、その明確な理由は完全には解明されていない部分もありますが、いくつかの戦略的な要因が考えられます。
販路の開拓
特に重要だったのが、手軽に立ち寄れる100円均一ショップという販路の開拓でした。
例えば、最大手のダイソーは海外を含む店舗数が2024年2月時点で5325店に達し、過去20年で2000店以上も増加しています。このような店舗網の拡大は、消費者との接点を飛躍的に増やしました。
さらに、100円均一ショップでは「3つで100円」という割安な価格設定がなされており、これが消費者の購入頻度を高める要因となっています。少子化が進む中でも、販路の拡大が全体の売上を牽引しているのです。
ターゲット層の拡大
最近では、主要顧客である子どもだけでなく、大人にもファン層を広げようと、積極的なマーケティング活動を展開しています。2024年7月にはSNSでアレンジレシピを募集するキャンペーンを実施し、マシュマロやヨーグルトにかけるなど、新たな食べ方を提案しました。
また、ブランド認知度向上のため、2024年には日本記念日協会に申請し、8月8日を「パチパチパニックの日」に制定しました。この記念日制定と同時に、人気アイドルグループSKE48とのコラボレーションも実現。メンバーがパチパチパニックを楽しみながら早口言葉に挑戦する動画を公開するなど、話題性のある企画で従来の子ども向けの枠を超えた幅広い層へのアピールを図っています。
経営体制の変革
アトリオン製菓の経営面でも大きな変化がありました。もともと明治の子会社でしたが、2023年3月期に丸紅が株式を100%取得し、丸紅グループの子会社となりました。
丸紅グループにとってアトリオン製菓は唯一のお菓子メーカーであり、丸紅は社長を送り込み、営業力や開発力の強化を図っています。
新体制の下、山下奉丈社長は「自社商品を充実させるために、営業と開発が一堂に会する商品戦略会議を新たに設け、顧客の視点を取り入れやすい体制にした」と説明しています。実際にパチパチパニックのメロンソーダ味は、この新しい体制の中から生まれた商品です。
生産能力の増強
こうした需要の拡大を受け、アトリオン製菓は2024年春に生産設備を大幅に増強し、生産能力を2.5倍に増やしました。 これは、2024年3月期にかけて需要の伸びに生産が追いつかない状況が続いていたためで、「嬉しい悲鳴」が上がるほどの人気ぶりを物語っています。
将来の展望
今後の展望も非常に野心的です。パチパチパニックは今後3~5年で、2024年3月期に7億円だった売上高を20億円にする計画を立てています。現在は国内のみでの販売ですが、長期的には海外展開も視野に入れ、最終的には30億~40億円程度まで売上高を伸ばしたいと考えています。この海外展開において、丸紅が世界中に持つ広範なネットワークが大きな武器となるでしょう。
まとめ
ドンパッチとパチパチパニックは、異なるメーカーから生まれた別々の商品でありながら、「口の中でパチパチ弾ける」という共通のユニークな体験を私たちに提供してきました。ドンパッチは伝説として語り継がれ、パチパチパニックは現代の定番として進化を続けています。
直接の繋がりはなくとも、この二つのお菓子は、日本の「パチパチキャンディー」という特別なジャンルを築き上げ、多くの人々に驚きと楽しさを与え続けている点で、実は互いに影響し合う「親戚」のような存在と言えるのかもしれません。
あなたは、この「パチパチ」の魔法を、どちらのお菓子で体験しましたか?