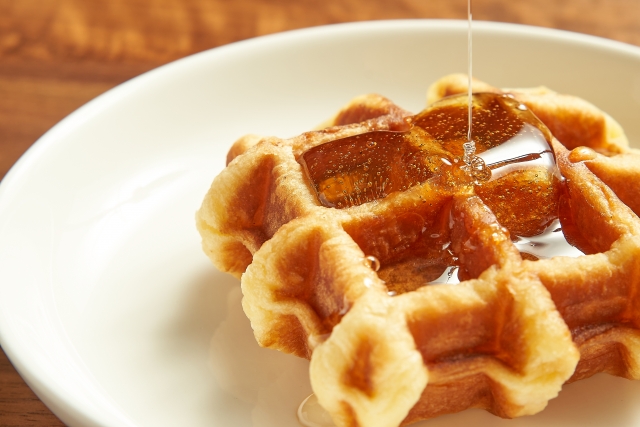どら焼きとは|発祥起源や名前の由来
どら焼きと聞いて、多くの人が思い浮かべるのは、ふっくらとした円盤状の生地に小豆あんが挟まれた、あの親しみやすい和菓子でしょう。コンビニエンスストアでも手軽に購入でき、子供から大人まで広く愛されているこのお菓子には、実は長い歴史と興味深い変遷があります。今回は、どら焼きの奥深い世界を紐解いていきましょう。
どら焼きとはどんなお菓子か
どら焼きは、カステラ風の生地を2枚焼き、その間に小豆あんを挟んだ膨化食品の和菓子です。シンプルな見た目とは裏腹に、その製法には職人の技とこだわりが詰まっています。
どら焼きの基本材料
どら焼きの生地には、小麦粉、卵、砂糖が使われています。これに蜂蜜を加えることで、しっとりとした食感とコクのある風味が生まれます。店舗によっては、みりん、醤油、塩、麹、日本酒、抹茶、黒糖など、様々な材料を加えて独自の風味を出している場合もあります。
三同割という基本的な配合
和菓子作りの世界では、「三同割(さんどうわり)」と呼ばれる配合が基本とされています。これは、小麦粉、卵、砂糖を同じ割合で混ぜる製法のことです。多くの和菓子店がこの配合を基準としながら、独自の工夫を加えて他店との差別化を図っています。
どら焼きの名前の由来
「どら焼き」という名前の由来には、複数の説が存在します。
菓子の形状に由来する説
最も有力な説は、菓子の形が打楽器の銅鑼(どら)に似ているからというものです。平たく丸い形状は、確かに銅鑼を連想させます。
調理器具に由来する説
生地を焼く際に使っていた銅製の鍋が銅鑼に似ていたためという説や、実際に銅鑼を調理器具として使っていたためという説もあります。どの説にしても、「銅鑡」という楽器との関連が強く示唆されており、現代でも「銅鑼焼き」と漢字で書くことがあります。
武蔵坊弁慶にまつわる伝説
どら焼きの起源にまつわる最も有名な伝説は、平安時代の武蔵坊弁慶にまつわるものです。源義経の家臣である弁慶が、手負いの状態で民家で治療を受け、そのお礼として、熱した銅鑼で生地を焼き、あんこを包んだお菓子を振る舞ったと伝えられています。しかし、この伝説には歴史的な矛盾があります。弁慶が亡くなったとされる時期には、小豆あんこはまだ一般的ではなかったため、この話はあくまで伝説の域を出ないと考えられています。
どら焼きの歴史
どら焼きは、その長い歴史の中で様々な形に姿を変えながら、現在の形にたどり着きました。
どら焼きのルーツ「麩の焼き」
どら焼きの原型は、安土桃山時代に生まれた「麩の焼き」というお菓子にまで遡ります。小麦粉を水で溶いて焼いた生地に、味噌などを塗って巻いたものです。この麩の焼きが江戸に伝わると、寛永年間には味噌の代わりに餡を巻いた「助惣焼(すけそうやき)」が誕生しました。
現代的などら焼きの誕生
江戸時代のどら焼きは、一枚の生地を四角く折りたたみ、あんこがむき出しになる形でした。現在の丸い形のどら焼きが登場したのは明治時代です。東京上野の和菓子店「うさぎや」で販売された「編笠焼(あみがさやき)」が、現代的などら焼きの始まりとされています。そして、現在のような2枚の生地であんこを挟むスタイルは、大正時代から始まりました。これは、西洋から伝わったホットケーキの影響を強く受けていると言われています。
地域によって異なるどら焼きの呼び方
どら焼きは、地域によって異なる呼び名を持つことも特徴です。特に近畿地方では、独特の名称で親しまれています。
近畿地方の「三笠」
近畿地方では、「三笠」「三笠焼き」「三笠まんじゅう」「三笠山」などと呼ばれることがあります。これは、奈良県にある三笠山(御蓋山)の形に似ていることに由来しています。
「どら焼き」と「三笠」の違い
「どら焼き」と「三笠」の違いには諸説あります。一般的には、2枚の生地の縁を軽く押さえるのがどら焼きで、互いにくっつくように作ったものが三笠とされています。また、元々は片面焼きがどら焼きで、両面焼きになったのが三笠だったという説や、どら焼きよりも厚い生地が三笠と区別されることもあります。
その他の地域の呼び名
他の地域や有名店でも、どら焼きは独自の呼び名で親しまれています。老舗カステラ店の文明堂では「三笠山」、名古屋市の両口屋是清では「千なり」、富山県では「名月」と呼ばれています。
どら焼きのバリエーション
伝統的な和菓子でありながら、どら焼きは常に進化を続けています。製法や具材、見た目の面で、驚くほど多様なバリエーションが生まれています。
一般的な具材
どら焼きの具材として最も一般的なものは、やはり小豆あんです。そのままでも美味しい小豆あんですが、さらに栗や餅、甘納豆などを加えて、食感や風味に変化をつけたどら焼きも多く見られます。
変わり種の具材
近年では、より大胆な具材を挟んだどら焼きも登場しています。大分県湯布院の名物「ぷりんどら」は、生地にプリンを挟んだものです。他にも、フルーツをメインにした「フルーツどら焼き」や、パフェのようなボリューム感がある「ぱふぇどら」、さらには惣菜を挟んだものまであります。
変わった製法のどら焼き
虎焼 焼成機に紙を敷いて生地を焼き、紙を剥がすことで虎柄の模様をつけた、見た目にも楽しいどら焼きです。
ぬれどら焼き
鹿児島県の梅月堂が製造する「ぬれどら焼き」は、特に注目すべきどら焼きです。薄くしっとりとした手焼きの生地と、包みきれないほどたっぷりの自家製粒あんが特徴です。この生地作りは非常に高い技術を要するため、「職人泣かせ」「職人殺し」とも呼ばれています。
この商品はもともと普通の「どら焼き」として売られていましたが、お客様から「仏壇にお供えして賞味期限ぎりぎりで食べると、もっとおいしい」という声が多く寄せられたため、2014年から「ぬれどら焼き」に商品名を変更しました。
現代の多様なバリエーション
生どら
1985年に宮城県のカトーマロニエが発売した「生どら」は、生クリームと小豆あんをホイップして挟んだものです。現在では、カスタードクリームやフルーツ、チョコレートクリームなど様々な具材が使われています。
どら焼きマリトッツォ
イタリアのマリトッツォの人気に影響を受けて生まれたのが「どら焼きマリトッツォ」です。生どらよりもさらにたっぷりの生クリームを挟み、いちごなどのフルーツを加えることもあります。「どらトッツォ」などとも呼ばれています。
蒸しどら
スポンジケーキのように蒸し上げた生地に、あんこやクリームなどを挟んだ和菓子です。生地に黒砂糖や抹茶、桜ペーストなどが使われることもあります。
その他
京都市の笹屋伊織では、バウムクーヘンのように棒状のあんこを生地で包んだどら焼きがあります。富山県では、長方形の生地を斜めにカットした「三角どらやき」も作られています。また、鼓月では、波型の生地や、ハート型・猫型の生地を使ったどら焼きも販売されています。
どら焼きと社会とのつながり
どら焼きが全国的に有名になったのは、メディアの影響や、地域振興の取り組みも大きく関係しています。
ドラえもんとの深いつながり
国民的人気漫画『ドラえもん』の主人公、ドラえもんの大好物としてどら焼きは広く知られています。作者の藤子・F・不二雄氏の出身地である富山県では、どら焼きがお祝い事などで贈られる身近な和菓子でした。この地域の文化が作品に反映されたと考えられています。
海外での呼び名 2014年に放送が始まった米国版ドラえもんでは、どら焼きが「ヤミー・バン(yummy bun)」という名称に変更されています。
どら焼きの日と地域活性化
丸京製菓(鳥取県米子市)は、2008年8月30日に日本記念日協会に4月4日を「どらやきの日」として正式登録しました。米子市を「どらやきのまち」にしようというプロジェクトの一環です。この取り組みにより、市内の運動公園が「どらやきドラマチックパーク米子」と名付けられるなど、地域全体でどら焼きを盛り上げる活動が行われています。
現代におけるどら焼きの定義
現代のどら焼きは、かつての「小豆あんを挟んだ和菓子」というイメージから大きく広がっています。
コンビニエンスストアや専門店の商品を見てみると、カスタードやチョコレート、フルーツを入れたものまで種類は豊富です。なかには、あんこを使わないどら焼きまで登場しています。
パンケーキのようなふんわりとした生地に、さまざまな具材を挟んだものも「どら焼き」と呼ばれていたりするのです。
伝統の形を残しながらも、どら焼きは時代の嗜好に合わせて多様化し、新しいお菓子文化を生み出していると言えるでしょう。