エクレアとは|フランス語で「稲妻」を意味する
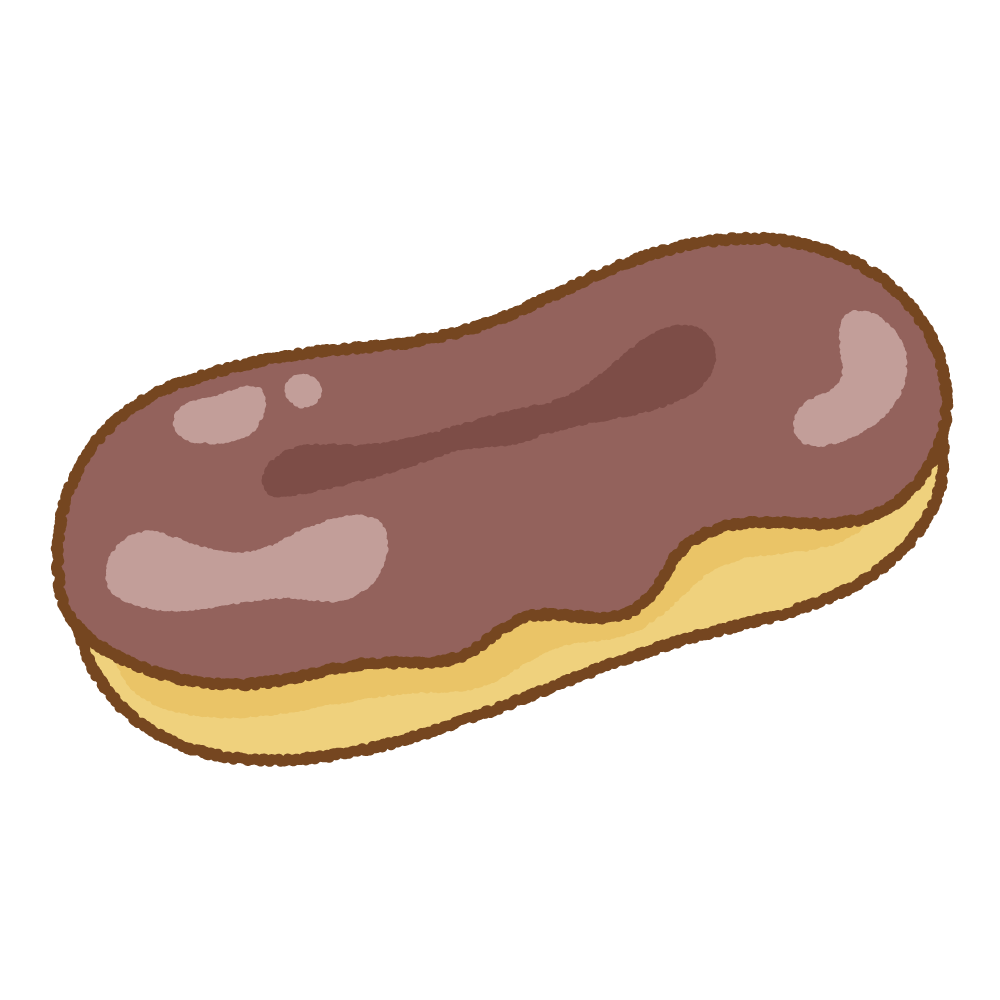
エクレアとは
長さが約12センチ、幅が約2センチの楕円形で、表面は光沢のあるチョコレートやアイシングで覆われています。
丸い形をしたシュークリームとは、見た目が異なります。
エクレアの構造
エクレアは、3つの主要な部分から成り立っています。
シュー生地
土台となるのは、軽くてサクサクした食感のシュー生地です。
この生地は、焼く過程で内部に空洞ができる特殊な性質を持っています。
クリーム
シュー生地の内部にできた空洞にクリームが詰められています。
一般的に使われるのは、カスタードクリームです。
コーティング
表面は、チョコレートやフォンダンと呼ばれる砂糖を主成分としたアイシングで覆われています。
これら3つの要素が組み合わさることで、エクレア独特の味わいと食感が生まれます。
エクレアの名前の由来
これにはいくつかの説があります。
稲妻が落ちるように一瞬で食べられてしまうから、という説が広く知られています。
その他に、焼き上がったシュー生地の表面の割れ目が稲妻に似ているから、という説や、表面のコーティングが稲妻のように光って見えるから、という説もあります。
稲妻のように細長い形の理由
エクレアが細長い形をしているのには、歴史的な理由があります。
エクレアの前身となる菓子は、19世紀初頭のフランスで「公爵夫人風のパン」と呼ばれていました。
これは、上流階級の女性たちが品よく食べられるように考えられたものです。
細長い形は手で持ちやすく、大きな丸いシュークリームのように口の周りを汚したり、クリームがはみ出したりすることがありませんでした。
エクレアの製造方法
エクレアの製造には、他の菓子とは異なる独特な製法が用いられます。
シュー生地の作り方
シュー生地は、まず鍋に水、バター、塩を入れて火にかけ、沸騰させます。
次に火から下ろし、一気に小麦粉を加えて混ぜます。
その後、粗熱が取れたところで溶き卵を少しずつ加えながら、よく混ぜていきます。
この製法により、焼く過程で生地内部の水分が蒸発し、空洞ができます。
エクレア用の生地は、均一な太さで細長く絞り出すため、技術が必要です。
クリームの詰め方と種類
焼き上がって冷めたシュー生地には、クリームを詰めます。
伝統的な方法では、生地の底に小さな穴を3箇所開け、そこからクリームを注入します。
これにより、生地を切ることなくクリームを詰めることができます。
使われるクリームは、カスタードクリームが一般的です。
濃厚な卵の味わいと滑らかな食感が特徴です。
現代では、チョコレート、コーヒー、抹茶、キャラメルなど様々な風味のクリームが使われています。
表面のコーティング
表面のコーティングは、エクレアの見た目と味を決める重要な部分です。
伝統的なのは、砂糖を主成分としたフォンダンと呼ばれる白いアイシングです。
フォンダンは、適切な温度に温めてから生地に塗ります。
この作業には、余分な部分を指で取り除く熟練した技術が必要です。
チョコレートコーティングも人気があります。
溶かしたチョコレートを表面に塗って固めたもので、フォンダンよりも濃厚な味わいです。
近年では、アーモンドスライスや金箔などを加えた装飾的なエクレアも作られています。
エクレアの歴史
シュー生地の発達
シュー生地の原型は、中世にまでさかのぼります。
16世紀から18世紀にかけて、「ププラン」というシュー生地を使った丸い菓子がありました。
18世紀には、フランソワ・マランがレシピを紹介し、楕円形の菓子**「カルトゥーシュ」**も作られていました。
エクレアの誕生
18世紀末から19世紀初頭に、パティシエのジャン・アヴィスがシュー生地を完成させました。
アヴィスの弟子であったアントナン・カレームが、1815年に現在のエクレアの直接の祖先となる**「公爵夫人風のパン」**を考案しました。
これは、細長いシュー生地にジャムを詰め、表面を砂糖でグラサージュ(コーティング)したものです。
名称の変化
「公爵夫人風のパン」という名前は、約10年から20年の間に「エクレア」という名前に変わりました。
この名称の変化は、貴族階級を連想させる名前よりも、より親しみやすい名前が求められたことや、菓子が一般に広まったことが背景にあります。
シュークリームとの違いと日本のエクレア
形状と作り方の違い
エクレアとシュークリームは、同じシュー生地を使いますが、形状と仕上げに違いがあります。
シュークリームは丸い形に焼き上げ、通常はコーティングをせず、生地の上部をカットしてクリームを挟みます。
一方、エクレアは細長い形に焼き上げ、必ず表面にコーティングを施し、底面からクリームを注入するのが伝統的な方法です。
日本での位置づけ
フランスではエクレアが一般的ですが、日本ではシュークリームの方がより親しまれています。
エクレアは、日本では少し特別な菓子として位置づけられています。
抹茶味のエクレアなど、日本独自の風味を取り入れたバリエーションも定着しています。
エクレアが持つ文化的意味
エクレアは、単なる菓子以上の文化的意味を持っています。
フランスでは、エクレアは上品さの象徴とされ、パティスリーの技術力を示す指標の一つとされています。
その細長い形状、三層構造のバランス、そして「稲妻」という名前は、この菓子が単なる食べ物を超えた存在であることを示しています。
現代においても、エクレアは伝統を守りながら、各店舗の個性を反映した様々なバリエーションが世界中で作られ続けています。





