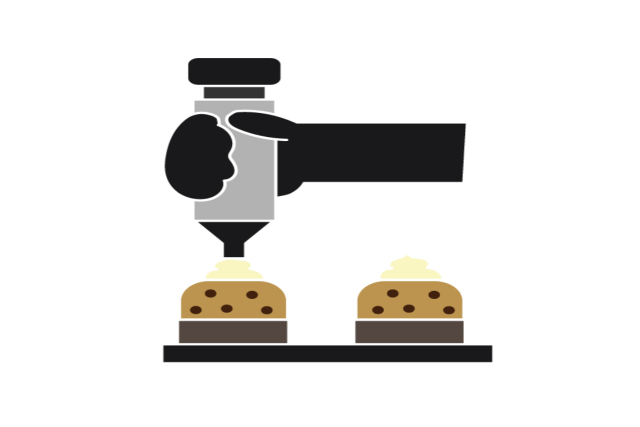船橋屋とは|創業から現在までの歴史や特徴

船橋屋とは
船橋屋は、江戸時代から続く日本の老舗和菓子店です。
看板商品は、小麦澱粉を乳酸発酵させて作る独特の「くず餅」です。
創業は文化二年(1805年)で、現在の東京都江東区にある亀戸天神の参道で創業しました。
船橋屋の創業はいつ?
創業時の社会背景
船橋屋が創業した江戸時代後期は、町人文化が花開いた時期でした。
当時の人々は、神社仏閣への参拝を日常的に行っていました。
特に季節の行事や祭りの際には、多くの参拝客が集まりました。
創業までの経緯
創業者の勘助は、千葉県北部にあたる下総国船橋の出身で、元は豆腐屋を営んでいました。
彼はより大きな商機を求めて江戸への進出を考え、梅や藤の名所として知られる亀戸天神に目をつけました。
多くの参拝客で賑わう場所であるにもかかわらず、甘味を提供する店が少ないことに気づいたのです。
信頼を築くための工夫
勘助は、いきなり店を開くのではなく、まず亀戸天神御用達の植木職人に弟子入りしました。
江戸時代の商売では、地域社会との信頼関係が不可欠だったからです。
植木職人として働くことで地域の人々と関係を築き、亀戸の土地や人々の好みを理解していきました。
この期間を経て、勘助は亀戸天神の参道でようやく茶店を開くことができました。
船橋屋の歴史
くず餅の誕生
勘助は、故郷の船橋で幼い頃から見慣れていた餅を商品にしました。
小麦粉からグルテンを取り除いた小麦澱粉を湯で練り、せいろで蒸して餅を作りました。
この餅に、香ばしいきな粉と甘い黒蜜をかけて提供しました。
江戸での評判
この餅は、参拝客の間でたちまち評判となりました。
餅のしなやかな食感と、きな粉の香ばしさ、黒蜜の甘さが調和した味わいが当時の人々にとって新鮮だったからです。
いつしか人々はこの餅を「くず餅」と呼ぶようになり、勘助の店は出身地にちなんで「船橋屋」と名付けられました。
文学者たちとの交流
明治時代の評価
明治時代に入ると、船橋屋の名声は確固たるものとなりました。
明治初頭に発行されたかわら版「大江戸風流くらべ」では、江戸名物として「亀戸くず餅(久寿餅)・船橋屋」が掲載されました。
この頃には、わざわざくず餅を味わうために遠方から訪れる人々も現れ始めました。
著名人との関わり
船橋屋には、後に歴史に名を残す多くの文化人が訪れました。
西郷隆盛はくず餅を好んでいたと記録されています。
芥川龍之介、永井荷風、志賀直哉、堀辰雄、高見順、大佛次郎といった文学者たちも店を訪れ、作品にその体験を記しています。
特に芥川龍之介は、少年時代に学校を抜け出してくず餅を食べに行ったというエピソードが残っています。
吉川英治と船橋屋
小説家の吉川英治との関係は深いものでした。
吉川英治は、執筆の合間にパンに黒蜜を塗って食べる習慣があり、船橋屋の黒蜜を評価しました。
これが縁となり、吉川英治は船橋屋のために看板文字を揮毫しました。
この看板は現在も本店の喫茶室に掲げられています。
度重なる災害からの復興
船橋屋は、関東大震災や第二次世界大戦、東京大空襲といった度重なる災害や戦災を経験しました。
戦前の本店は焼失しましたが、奇跡的に発酵槽とその中の発酵澱粉は被害を免れました。
これにより、江戸時代から続く製法を途切れさせることなく継承することができました。
現在の本店
現在の本店は、昭和28年4月に戦後復興として完成したものです。
創業以来の製法が守られ、多くの人々にくず餅を提供し続けています。
現代の船橋屋
経営体制
2022年9月29日、渡邉雅司氏の辞任に伴い、神山恭子氏(旧姓:佐藤恭子)が代表取締役社長に就任しました。
神山社長は2004年に船橋屋に入社し、和菓子売り場や通販事業、新卒採用などを経て、くず餅乳酸菌の研究開発事業にも携わっていました。
伝統の継承と創造
神山社長は、船橋屋の事業を「伝統継承事業」と「伝統創造事業」の二つの柱で捉えています。
伝統継承事業として、江戸時代から受け継がれた製法と味を守り続けています。
伝統創造事業として、くず餅乳酸菌の研究開発や、若い世代に向けた商品の開発など、伝統に新たな価値を見出す取り組みを行っています。
船橋屋のくず餅の製法
小麦澱粉の抽出
船橋屋のくず餅の製造方法は、創業当初から基本的な部分は変わっていません。
まず、厳選した小麦粉からグルテン質を分離して、小麦澱粉だけを抽出します。
このグルテン除去の工程は、くず餅の品質を決定する重要な過程です。
長期間の発酵
抽出された小麦澱粉は、杉や檜で作られた木製の発酵槽に入れられます。
木製の槽は乳酸菌の活動をより活発にするためです。
この発酵槽で、約15ヵ月という長期間にわたって乳酸発酵が行われます。
この長い発酵期間が、独特の風味としなやかな食感を生み出します。
蒸し上げと仕上げ
発酵が完了した小麦澱粉は、せいろで蒸し上げられます。
これにより、ほのかな香りと酸味を持つくず餅が完成します。
蒸し上がったくず餅は、適度な弾力としなやかさを併せ持つ独特の食感を持っています。
きな粉と黒蜜のこだわり
くず餅に添えられるきな粉は、厳選された大豆を強めに焙煎し、粗めに挽いて作られます。
強めに焙煎することで香ばしさが生まれ、粗挽きにすることで食感にアクセントが加わります。
黒蜜は沖縄産の黒糖をベースに、数種類の糖を独自の比率でブレンドした船橋屋秘伝の味です。
この三つの要素が組み合わさることで、船橋屋のくず餅ならではの味わいが完成します。
関東と関西の「くず餅」の違い
船橋屋のくず餅は、一般的に「葛餅」と書かれる関西の葛餅とは異なる食べ物です。
関西の葛餅は葛の根から採取される葛粉を原料とし、透明でゼリーのような食感です。
一方、関東のくず餅(久寿餅)は小麦澱粉を発酵させて作られるため、白く濁った見た目でお餅のような食感を持ちます。
船橋屋のくず餅の栄養
発酵過程で生まれる植物性乳酸菌は「くず餅乳酸菌」と名付けられ、現在では健康食品としての価値が注目されています。
1人前で約200kcalとカロリーは控えめで、グルテン含有率も低いという特徴があります。
船橋屋の商品
主力商品「くず餅」
船橋屋の主力商品は、江戸時代から続く「くず餅」です。
無添加自然発酵という伝統製法で製造され、消費期限はわずか2日間です。
この短い消費期限は、保存料や添加物を一切使用しない製法を守っているためです。
あんみつ類
戦前から親しまれているあんみつ類も、船橋屋の重要な商品です。
特に「特製くず餅入りあんみつ」は支持されています。
伊豆七島産の天草をじっくり煮出して固めた寒天と、職人が作る自家製あんこが特徴です。
寒天は磯の香りが強く、コリッとした食感を楽しめます。
和フィナンシェ
和フィナンシェは、洋菓子と和菓子の要素を組み合わせた商品です。
船橋屋のくず餅から発見された「くず餅乳酸菌」を使用して作られています。
和の素材を活かしつつ、フィナンシェ特有のバターの香りと食感を併せ持っています。
くず餅プリン
くず餅の独特な風味と食感を活かしながら、なめらかなプリンに仕上げられています。
若年層にも親しみやすい和スイーツとして開発されました。
店舗展開
船橋屋の店舗は、創業の地である亀戸の「亀戸天神前本店」をはじめ、東京都内や千葉県、埼玉県に広く展開しています。
東京では、大丸東京店や東武百貨店池袋本店、京王百貨店新宿店、松屋浅草店などの主要な百貨店に出店しています。また、エキュート赤羽店やアトレ吉祥寺店、テルミナ錦糸町店といった駅ビルにも多く店舗を構えており、東京駅や渋谷駅などの主要ターミナル駅の商業施設にも出店しています。
千葉県では、東武百貨店船橋店やペリエ千葉エキナカ店など、県内の主要な駅ビルに店舗があります。さらに、羽生PA(上り線)の鬼平江戸処店のように高速道路のサービスエリアにも出店しており、多様な場所で商品を購入することが可能です。これらの店舗に加え、広尾には姉妹ブランドの「船橋屋こよみ広尾店」があります。