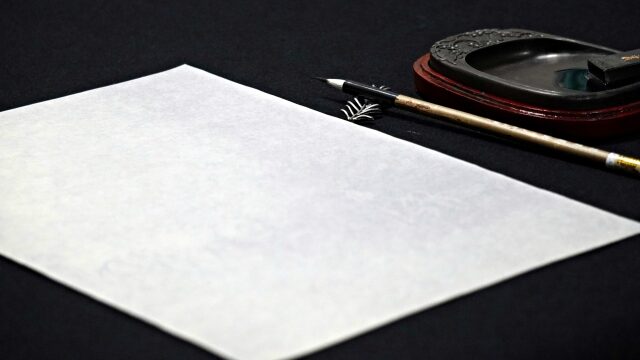ジンジャー(生姜)ブームとは|流行のきっかけと終わった理由
本記事では、カラメルやシナモンといった味覚トレンドの変遷を背景に、突如登場したジンジャーテイストの流行とその展開、そしてなぜ短命に終わったのかを詳しく解説します。プランタン銀座をはじめとする当時のデパ地下の動きや、日本人の味覚との相性、生姜の文化的背景まで掘り下げ、味のブームがどのように生まれ、なぜ定着しなかったのかを読み解きます。
ジンジャーブーム
日本のお菓子業界には、時代を彩る様々な味のトレンドがあります。
1999年にはカラメルテイストが人気を博し、続く2000年にはシナモンテイストが多くの人々に愛されました。
そして2001年、新たな味覚の流行として登場したのが「ジンジャー(生姜)」テイストです。
ジンジャーとは、ショウガ科の植物の根茎部分を指し、独特の辛味と香りを持つ食材です。
日本でも古くから料理や漢方などに使われてきましたが、欧米ではクッキーやケーキなどのお菓子にも幅広く用いられています。
このジンジャーを使ったお菓子が、2001年に日本でも「新しい味」として脚光を浴びたのです。
日本でジンジャーブームが起きた理由
実のところ、その理由は明確ではありません。
カラメルやシナモンの流行には何らかの社会的背景や消費者心理の変化があったのかもしれませんが、ジンジャーについてはその経緯が曖昧で、むしろその謎めいた部分こそが興味深いともいえるでしょう。
この現象の背景を推察すると、おそらく商品開発の現場で「カラメル、シナモンときて、次は何にしようか」と考えた際に、ジンジャーが候補として浮上したのではないでしょうか。
深い戦略的な意図というよりも、比較的自然な流れで「今度はこれで行ってみよう」という感覚で市場に投入され、予想以上に消費者の反応が良かったというのが実情だったのかもしれません。
ジンジャーブーム中のデパ地下の様子
こうしたトレンドの動きに最も敏感に反応するのは、やはりデパートの地下食品売り場、いわゆるデパ地下です。
中でも東京・有楽町のプランタン銀座は、常に他店を一歩リードする反応の速さを見せていました。同店がこのような新しいトレンドに敏感だった理由として、店舗規模がコンパクトであることが挙げられます。大型店舗と比べて意思決定が迅速で、新しい商品の導入や売り場の変更などの対応が機敏に行えたのです。
また、同店のバイヤーたちも、このような新しい仕掛けに対して非常に意欲的に取り組みます。
店内中央の目立つステージエリアには、お客様の視線を引きつけるように、ジンジャーテイストの商品がしっかりとディスプレイされていました。ジンジャークッキーやジンジャーケーキなど、流行に敏感な若い女性たちや仕事帰りの女性たちが楽しそうに買い物をしている光景が見られました。
ジンジャーブームが衰退した理由
このような盛り上がりを見せていたにもかかわらず、ジンジャーテイストは期待されていたほど爆発的な人気を得ることはありませんでした。
その理由として考えられるのは、それまでの日本人の味覚になじみが薄かった、やや強めのジンジャーという味に対する適応の問題です。
カラメルやシナモンと比べて、ジンジャーの辛みや独特の風味は、日本人の舌にとってより馴染みにくいものだったのかもしれません。
ジンジャーは寒い国で親しまれてきた
ジンジャー、つまり生姜を使った食品について世界に目を向けてみると、興味深い傾向が見えてきます。
北欧やロシアといった寒冷地域では、古くからジンジャーブレッドやジンジャーケーキ、ジンジャークッキーなどが親しまれてきました。
これらの地域では、生姜の持つ体を温める効果を利用して、厳しい寒さに対抗する生活の知恵として発達してきたのです。
生姜に含まれる辛味成分は血行を促進し、体の内側から温めてくれるため、長い冬を乗り切るための重要な食材として重宝されてきました。
この伝統的な食文化と比較すると、温暖な日本での突然のジンジャーブームは、興味深い現象と言えるでしょう。
まとめ
ここまで、2001年に日本で起きたジンジャーテイストの流行についてお話しました。
カラメル、シナモンと続いた中で、次なる一手として登場したジンジャーは、新鮮味があった一方で、日本人の味覚にはまだなじみにくい側面もあり、大きなブームには至りませんでした。
現在ではジンジャー味のお菓子も少しずつ定着してきており、2001年のジンジャーブームは、そうした流れの「始まりの一歩」だったのかもしれません。