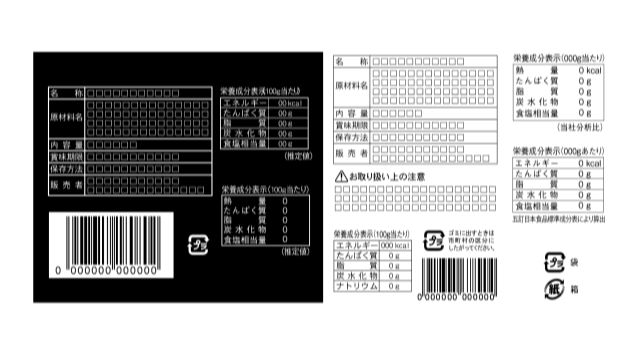ガムの需要が衰退した理由|新たに生まれたミント味ブーム
かつて、日本のコンビニエンスストアのレジ横には、必ずと言っていいほどチューインガムが並んでいました。通勤や通学のお供として、多くの人に愛されていたガムは、いつしかその姿を消し、市場は縮小の一途をたどっています。しかし、その裏で、これまで日本では人気がなかったミント味のスイーツが一大ブームを巻き起こしました。ガムの衰退とミント味スイーツのブームには、どのような関係があるのでしょうか。
そもそもガムって何だろう?
ガムの歴史は古く、紀元前3世紀頃の古代ギリシャでは、木の樹脂を噛む習慣があったと言われています。現代のチューインガムは、甘味料や香料、ガムベースなどの原料から作られており、噛むことを目的としたお菓子です。欧米では古くから娯楽性や味わいを楽しむものとして親しまれてきました。しかし、日本ではその後、実用的な役割を担うようになり、独自の道を歩むことになります。
日本のガムは「実用性」で広まった
日本におけるチューインガムの歴史は、戦後から高度経済成長期にかけての社会の変化と深く関わっています。
アメリカから伝わったガム
戦後、日本にアメリカ文化が流入する中で、チューインガムも本格的に普及しました。しかし、日本のガムは欧米とは少し異なる受け入れられ方をします。欧米では娯楽やお菓子として楽しまれていたガムが、日本では実用的な役割を重視されるようになったのです。
なぜガムは「実用品」になったの?
高度経済成長期以降、日本では長時間の通勤や多忙な仕事が一般的になりました。この環境で、ガムは口臭予防や眠気覚まし、集中力向上といった実用的な機能で重宝されるようになります。朝の通勤前や昼食後、会議の前など、エチケットとしてガムを噛む習慣が広く浸透しました。ミントの清涼感が口臭予防や集中力向上という実用的な価値と結びついたことで、ガムといえばミント味という固定観念が形成されたのです。1980年代から2000年代にかけて、ガム市場は安定した成長を続け、規則正しい生活リズムを持つサラリーマンや学生たちに支えられていました。
ガムが売れなくなった理由
長年にわたり安定した人気を誇っていた日本のガム市場に、2000年代後半から大きな変化が訪れました。
変わる生活とガム離れ
スマートフォンの普及や働き方の多様化は、人々の生活様式を大きく変えました。在宅勤務の増加やオンライン会議の普及により、従来の画一的な勤務スタイルが崩れ、ガムを噛む習慣も減少していきました。また、電車内でのマナー意識が高まり、口寂しさを紛らわせるためにガムを噛むという行動パターンも変化していったのです。
便利なオーラルケア商品が増えた
口臭予防に対する人々の意識も変わっていきました。歯科衛生への関心が高まり、ガムよりも効果が高いとされるマウスウォッシュや舌クリーナーなど、様々なオーラルケア商品が登場しました。これにより、ガムの持つ実用的な価値が相対的に薄れていったのです。
買い物の仕方まで変わった
コンビニエンスストアでの買い物行動の変化も影響しました。セルフレジや電子決済の普及により、レジでの待ち時間が減り、衝動買いの機会が減少しました。かつてレジ横に置かれていたガムは、消費者の目に触れる機会を失っていったのです。
ガムの衰退が「ミント味ブーム」を生んだ?
ガム市場が縮小していく中で、多くの日本人にとってミント味との接点が減っていきました。しかし、この変化が思わぬ形で新しい市場を生み出すことになります。
テレビ番組が火をつけた「ミント味旋風」
2017年8月、テレビ番組「マツコの知らないチョコミントの世界」が放送されました。この番組は、日本ではなぜミント味スイーツが人気を得られないのかをテーマにしていました。しかし、この番組がきっかけとなり、長年ミント味を愛好してきた「隠れミント党」の人たちが、自分たちの好みを堂々と主張し始めました。SNSでその声が広がると、これまでミント味を避けていた人たちも興味を持ち、試してみる機会が増えました。
眠っていた「好き」が目覚めた
実際にミント味のスイーツを食べてみた人からは、「意外と美味しい」「これなら好きになれる」といった好意的な声が続出しました。これは、日本人の味覚がミント味を受け入れられないのではなく、単に慣れ親しむ機会が少なかっただけだということを示していました。ガムの衰退によって「機能的なミント」との接点が減ったことが、スイーツを通じた「楽しむミント」への関心を高める土壌を作ったとも言えるでしょう。
売上が急増!ミント味スイーツの逆襲
このブームを受け、これまで限定的だったミント味商品の売上は急激に伸びました。アイスクリームやチョコレート、クッキーなど、多くのカテゴリーでミント味の新製品が次々と投入されるようになりました。製菓メーカー各社も、この新たな市場の可能性に気づき、積極的に商品を展開するようになったのです。
この一連の流れを振り返ると、チューインガム市場の低迷がミント味スイーツ市場の拡大に繋がったという、興味深い関係性が見えてきます。食文化は、一見無関係に思える社会の変化によって、大きく変わることがあるのです。