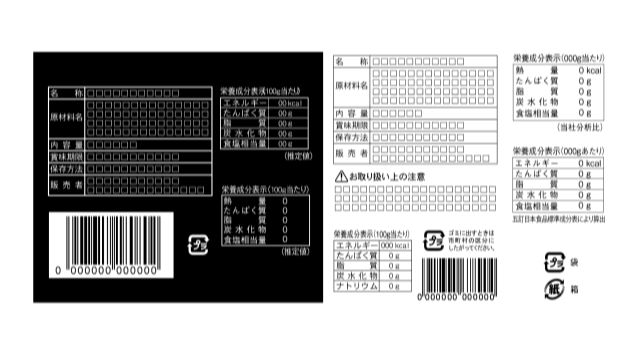「健康菓子」の需要増加!その理由や企業の取り組みを紹介

お菓子から「健康菓子」への需要が増加
日本の菓子業界は、これまでになかった大きな変化の波が来ています。
昔、お菓子といえば、子どもが楽しむためのものでした。
甘くておいしく、カラフルなものが多く、純粋に楽しむための食べ物だったのです。
しかし、現代社会では人々の健康に対する考え方が根本的に変わってきています。
社会的背景から来る健康意識の変化
人々の健康意識が変わった背景には、いくつかの理由があります。
現代社会の健康課題
1つ目は、糖尿病や高血圧といった「生活習慣病」が増えていることです。
これらの病気は毎日の食事と深く関係しているため、食べ物を選ぶ際に慎重になりました。
健康寿命への関心
2つ目は、日本社会の高齢化が進み、「健康寿命」を延ばしたいと考える人が増えたことです。
健康寿命とは、心身ともに自立して生活できる期間のことです。
ただ長生きするだけでなく、質の高い生活を送りたいという願いが広まっています。
新型コロナウイルスの影響
3つ目は、新型コロナウイルスの流行です。
感染症に負けないためには、日頃から健康に気を配ることが大切だと多くの人が感じ、免疫力や体調管理への関心が高まりました。
こうした背景から、特に働く大人たちは、手軽に健康管理ができる食べ物を求めるようになりました。
この需要に応える形で生まれたのが「健康菓子」という新しいお菓子の種類です。
健康菓子の定義と目的
健康菓子とは、おいしさや楽しさといったお菓子の良さに加え、体の健康に役立つ効果や機能を持つ商品のことです。
ただ甘いものを食べて満足するだけでなく、お腹の調子を整えたり、血糖値をコントロールしたり、疲れをとったりする目的で作られています。
健康菓子市場の成長
この健康菓子市場は、大きく成長しています。
市場規模の拡大
ある調査会社によると、2024年の健康菓子市場は、前の年と比べて6.9%も成長し、その規模は3558億円に達しました。
この成長率はとても高い水準です。
この数字は、多くの産業と比べても非常に高く、健康菓子市場の勢いの強さを示しています。
菓子市場全体に占める割合の変化
さらに、健康菓子が菓子市場全体に占める割合を見てみると、その変化はよりはっきりとわかります。
2019年には10.9%だった割合が、2024年には12.2%にまで上がっています。
たった5年間で1.3ポイントも増えているのです。
このわずかな数字の増加は、数千億円規模の市場では非常に大きな意味を持ちます。
これは、消費者がお菓子に求めるものが根本的に変わってきていることを示しています。
健康菓子のターゲット層は大人
健康菓子市場の成長を支えているのは、お菓子を買う人の層が変わったことです。
これまでの菓子市場では、味や見た目を重視する子どもが主な消費者で、親が買うかどうかを決めていました。
しかし、健康菓子では、働く大人たちが中心的なお客さんになっています。
大人の購買行動の特徴
大人の消費者は、子どもとは買い物の仕方が大きく違います。
彼らは単に甘いものが食べたいだけでなく、健康を保ったり、良くしたりするといったはっきりした目的を持ってお菓子を選びます。
また、自分自身で商品の成分や効果を調べ、納得してから買う傾向があります。
そのため、健康菓子に求められる機能性も従来の菓子とは大きく異なり、より専門的で多様化が進んでいるのです。
機能性表示食品制度の活用
健康を意識する消費者の多様なニーズに応えるため、お菓子を作る会社はさまざまな方法をとっています。
その中でも特に注目されているのが、「機能性表示食品制度」を活用した商品開発です。
制度の概要
この制度は2015年に始まり、企業が科学的な根拠があれば、商品のパッケージに健康効果を表示できるというものです。
この制度ができる前は、お菓子の健康効果を消費者に伝えることがとても難しく、健康に役立つ商品でもその価値を十分に知ってもらえませんでした。
しかし、機能性表示食品制度のおかげで、メーカーは商品の健康効果をわかりやすく伝えられるようになり、より多くの健康菓子を開発できるようになりました。
ヘルスクレームと関与成分の拡大
制度が活用されるにつれて、「ヘルスクレーム」や「関与成分」の分野も広がっています。
ヘルスクレームとは、「おなかの調子を整える」や「食後の血糖値の上昇を抑える」といった、健康に関する効果を示す言葉です。
関与成分とは、その効果をもたらす具体的な成分のことで、食物繊維や特定の栄養素などが当てはまります。
制度が始まった当初は、表示できる健康効果が限られていましたが、研究が進んだことで、現在では血糖値のケアや腸内環境の改善、疲労回復など、さまざまな健康課題に対応した商品が作れるようになっています。
メーカー各社の具体的な取り組み
大手のお菓子メーカーも、積極的に健康菓子を作っています。
明治の取り組み
明治オリゴ糖ミルクチョコレート
例えば、明治は昨年「明治オリゴ糖ミルクチョコレート」を発売しました。
この商品は、お腹の善玉菌のエサになり、腸内環境を改善する効果が科学的に証明されているオリゴ糖を配合しています。
親しみやすいチョコレートに、腸内環境を改善するという明確な健康機能を持たせることで、おいしさと健康の両方を満たすことに成功しました。
これは、健康菓子の理想的な形と言えるでしょう。
カルビーの取り組み
フルグラ食後の血糖値ケア
カルビーは今年4月に「フルグラ食後の血糖値ケア」を新しくしました。
この商品は、食後の血糖値が上がるのを抑える成分が入っているシリアルです。
朝食や間食として手軽に食べられるため、忙しい現代人の健康管理に役立ちます。
リニューアルにより、機能性や味わいがさらに向上し、健康を意識する消費者のニーズにより的確に応えられるようになりました。
機能性表示食品制度に依存しないアプローチ
健康菓子の成長は、機能性表示食品制度だけによるものではありません。
注目される健康価値のキーワード
制度に頼らずに健康価値をアピールする商品も増えており、市場をさらに盛り上げています。
江崎グリコの「SUNAO」シリーズやロッテの「ZERO」シリーズがその代表です。
江崎グリコの「SUNAO」シリーズ
「SUNAO」シリーズは、糖質を大幅に抑えながらも、普通のアイスクリームと同じようなおいしさを実現しています。
糖質制限をしている人でも、罪悪感なく楽しめるのが大きな魅力です。
ロッテの「ZERO」シリーズ
「ZERO」シリーズも同様に、砂糖を使わずに甘味料を使うことで、おいしさを楽しみながら糖質やカロリーを抑えた商品として人気です。
これらの商品は、「糖質オフ」や「砂糖不使用」といった、誰にでもわかりやすい言葉で健康価値を伝えています。
健康菓子に広がる健康キーワード
健康菓子市場では、単に1つの機能だけでなく、さまざまな角度から健康価値を提供する商品が広がっています。
健康に直結する、いくつかのキーワードを説明します。
低GI
「低GI」とは、食べた後に血糖値が上がる速度がゆっくりであることを示します。
GI値が低い食品は、血糖値の急激な上昇を抑えるため、糖尿病の予防や体重管理に役立ちます。
糖質オフ
「糖質オフ」は、糖質の量を意識的に減らす食事法に合わせた商品です。
最近のダイエットや健康志向の高まりで注目されています。
自然素材
「自然素材」は、人工的な添加物や化学成分を避けたいという人たちのニーズに応えるキーワードです。
オーガニック、無添加、天然由来といった関連する概念とともに、食品の安全を重視する人たちに支持されています。
ロカボ
「ロカボ」は、ゆるやかな糖質制限を意味する言葉です。
無理なく続けられる健康的な食生活として注目されています。
ハイカカオ
「ハイカカオ」は、カカオがたくさん入っているチョコレートのことです。
カカオには、血圧の改善や脳の働きを良くする効果が期待できるポリフェノールが豊富に含まれています。
健康菓子市場の今後
健康菓子市場は、今後も成長が続くと予想されています。
継続的な成長予測
2025年には、前の年と比べて6.1%増の3776億円になると見込まれています。
これは、新型コロナウイルスをきっかけに高まった人々の健康意識が、一時的な流行ではなく、生活習慣として定着したためです。
長期的な追い風
また、高齢化が進む日本では、健康を維持したいという気持ちがさらに高まると考えられます。
将来の健康を考えて、病気を予防しようとする中年層も増えており、健康菓子市場にとっては長期的な成長が見込めます。
新しい可能性
科学技術が進歩すれば、新しい健康機能を持つ成分が発見され、これまでになかった商品が生まれる可能性もあります。
個人の健康状態に合わせた、一人ひとりにぴったりの商品も期待されています。
このように、健康菓子市場はただのブームではなく、社会の変化と人々の意識の変化に支えられた、今後も成長が続く分野です。
お菓子という枠を超えて、健康食品としての役割も担う、新しい食べ物の種類として、これからの食品業界で重要な存在になっていくでしょう。