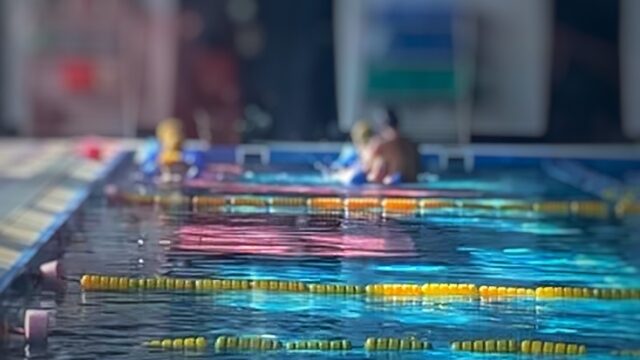ハイレモンとは|お菓子だけどビタミンC栄養機能食品
ハイレモンとは
| 製造・販売元 | アトリオン製菓株式会社 |
|---|---|
| 商品分類 | 錠菓(タブレット型菓子) |
| 栄養機能食品区分 | ビタミンCの栄養機能食品 |
| 発売年 | 1980年 |
ハイレモンは、アトリオン製菓が手がけるタブレット型の錠菓です。
さらに、お菓子でありながら、なんとビタミンCの栄養機能食品として認められています。
ビタミンC栄養機能食品と言われる理由
ハイレモンを語る上で欠かせないのが、「ビタミンC栄養機能食品」という位置づけです。
ただのレモン味の錠菓ではなく、国が定めた基準を満たした“機能を持つ食品”として認められています。
「栄養機能食品」とは、特定の栄養成分を一定量以上含み、その成分が体の中でどのように働くかを表示できる食品のことです。
ただし、どんな食品でも自由に名乗れるわけではありません。
栄養機能食品として表示できるのは、国が定めた基準量を満たしている場合に限られます。
ビタミンCの働き
ハイレモンが該当するのは、ビタミンCの栄養機能食品です。
ビタミンCは体に欠かせない栄養素で、皮膚や粘膜の健康維持を助ける働きを持っています。また、抗酸化作用と呼ばれる重要な働きもあり、体内で発生する「活性酸素」の害を減らしてくれます。
活性酸素は、呼吸の過程で自然に生まれる物質ですが、増えすぎると細胞にダメージを与え、老化や生活習慣病の原因にもなることがあります。ハイレモンは、そんなビタミンCを手軽に補えるお菓子として親しまれてきました。
糖分の働き
ハイレモンのもう一つの大きな構成要素が「糖分」です。
糖分はお菓子としての甘みを生み出す基本的な成分であり、食べる楽しさを作り出します。さらに、体にとっては大切なエネルギー源でもあります。
疲れたときに甘いものを欲しくなるのは、脳や体がエネルギーを必要としているからです。ハイレモンは、甘さで気分を和らげながら、ちょっとしたエネルギー補給にもつながるお菓子といえるでしょう。
オリゴ糖が支える腸内環境への配慮
さらに注目したいのが、配合成分の一つである「オリゴ糖」です。
オリゴ糖は、腸内に住む善玉菌の栄養源として知られています。
腸内環境を整えることが健康維持に重要とされる今、このオリゴ糖の配合は時代に合った工夫といえます。
ハイレモンの名前の由来
| 挨拶説 | 英語表記「HI-LEMON」の「HI」は挨拶の「Hi」を指す |
|---|---|
| 語源説 | 「ハイ、レモンあげる」という言葉から命名 |
| ブランド戦略 | ヨーグレットとは意図的に名前の関連性を持たせず、独立したブランドとして立ち上げ |
「ハイレモン」という名前には、いくつかの説があります。
パッケージを見ると「HI-LEMON」という英語表記が確認できますが、この「HI」は「high」(高い)という意味ではないようです。
挨拶としての「Hi」説
むしろ、人と人が出会ったときに交わす「Hi」という挨拶を指していると考えられています。親しみやすさや気軽さを感じさせる言葉として選ばれたのでしょう。
日常会話から生まれた説
別の説では「ハイ、レモンあげる」という日常的な会話から生まれた名前だとも言われています。誰かに何かを手渡すとき、私たちは自然と「ハイ」という言葉を口にします。
独立したブランド戦略
もう一つ注目すべき点があります。
それは、ハイレモンがヨーグレットとは意図的に異なる名前をつけられたという事実です。
同じ企業が似た商品を展開する場合、シリーズ名をつけて関連性を示すことが多いものです。
しかし明治製菓は、ハイレモンをヨーグレットの派生商品としてではなく、まったく独立したブランドとして育てていく方針を選びました。
受験シーズン限定版「ハイレルモン」
一年を通じて販売されている通常版のハイレモンとは別に、特定の時期だけ登場する特別なバージョンがあります。それが、受験シーズンに合わせて販売される「ハイレルモン」です。
この特別版は、通常版とは大きく異なる特徴を持っています。配合されているビタミンCの量が、なんと3倍に増量されています。
「ハイレモン」が「ハイレルモン」に変わるのですが、この「レル」というのは「入れる」の意味です。つまり「入れるもん」という語呂合わせになっており、受験生にとって縁起を担いだネーミングとなっているわけです。
ハイレモンの開発コンセプト「おいしくてちょっぴりヘルシー」
商品開発チームが掲げたコンセプトは、シンプルでありながら明確でした。
それは「おいしくてちょっぴりヘルシー」というものです。
この言葉には、二つの要素のバランスが表現されています。
おいしさ
一つ目は「おいしさ」です。
どれだけ健康に良くても、おいしくなければ人々は繰り返し買おうとは思いません。
菓子である以上、まず味わいとして満足できるものでなければならないという考えです。
ちょっぴりヘルシー
二つ目は「ちょっぴりヘルシー」という部分です。
ここで「ちょっぴり」という言葉が使われているのには意味があります。
これは薬でもサプリメントでもなく、あくまで菓子であるという前提を忘れないためです。
レモン味の選択
配合する栄養素としてビタミンCが選ばれたことで、自然とフレーバーはレモン味に決まりました。
ビタミンCと聞けば多くの人が思い浮かべるのが柑橘類、特にレモンです。
当初のターゲット層
開発チームは、健康意識の高い大人層をメインターゲットとして想定していました。
しかし、発売後の展開は、彼らの予想をはるかに超えるものとなります。
ハイレモンの購入層|大人?子ども?
ハイレモンの開発当初、マーケティングチームが想定していたのは、健康に気を配る大人たちでした。
ビタミンCの健康機能を理解し、日常的に栄養管理を意識している層に向けた商品として企画されていたのです。
ところが、市場に出してみると意外な展開が待っていました。
確かに大人たちも購入していましたが、それと同じくらい、あるいはそれ以上に、子どもたちの間で広まっていったのです。
子どもに人気が出た理由
その答えの鍵を握っていたのが、PTPシートという包装形態です。これは当初、商品の差別化という戦略的な理由から行われたものでした。
健康機能を持つ菓子であることを視覚的に伝え、他の一般的な菓子とは違うという印象を与えるために、薬のような包装を採用したのです。
しかし、この包装が子どもたちにとって、まったく別の意味を持つことになりました。シートからタブレットを押し出すという行為そのものが、一つの遊びのような体験となったのです。
食べ物を味わうという体験は、実は口に入れる瞬間だけで完結するものではありません。
パッケージを手に取り、開封し、中身を取り出し、そして口に運ぶ。この一連の動作すべてが、食の体験を構成しています。
ハイレモンの場合、PTPシートから押し出すという行為が、記憶に残る体験の重要な一部となりました。
大人になっても「あのシートから押し出す感覚」を覚えている人が多いのは、この体験が強く印象に残ったからかもしれません。
ハイレモンは乗り物酔いに効く?
やがて、小学生たちの間では、ハイレモンに対する独特な認識が広まっていきました。
それは「乗り物酔いに効く菓子」というものです。
この認識が医学的に正確な根拠に基づいていたかどうかは別として、子どもたちの間ではそのように語り継がれていきました。
遠足の前日、親と一緒にスーパーへ行き、おやつを選ぶ。そのときに「ハイレモンは乗り物酔いに効くらしいよ」という情報を耳にした子どもが、実際に購入する。
そして遠足当日、バスの中でハイレモンを食べる。この経験が、また別の子どもたちに伝わっていく。こうして、世代を超えて共有される「子ども時代の知恵」のようなものとして、定着していったのです。
ハイレモンの包装「PTPシート」
ハイレモンの大きさは、およそ10円玉と同じくらいです。
手のひらに乗せると、その小さなタブレットからレモンの爽やかな香りが漂ってきます。
そしてこのハイレモンを特徴の一つが、PTPシートと呼ばれる独特な包装形態です。
パッケージに目を向けると、白・黄・緑という三色の組み合わせが印象的です。
この配色は発売当初から変わることなく使い続けられており、ハイレモンの顔とも言える存在になっています。
また、タブレットの中には、ごくまれに笑顔の絵が描かれたものが紛れ込んでいることがあります。
ハイレモンのパッケージデザイン
ハイレモンのパッケージを見たとき、誰もが最初に目にするのが、白・黄・緑という三色の組み合わせです。この配色は、発売以来40年以上にわたって変わることなく使い続けられています。
各色が持つ意味
この三色が組み合わさることで、レモンという果実が持つイメージが視覚的に表現されているのです。
企業が長年同じ商品を販売し続ける中で、パッケージデザインを刷新したいという誘惑は常にあります。しかし、ハイレモンの場合、あえてこの配色を変えないという選択が続けられてきました。
箱タイプのパッケージ形状も、発売当初から基本的に変わっていません。
手のひらに収まるサイズ感、箱を開けるときの感触、中からPTPシートが出てくる瞬間。これらすべてが、ハイレモンを食べる体験の一部として記憶されているのです。
パッケージを変えない理由
なぜ、これほどまでに「変えないこと」が重視されているのでしょうか。それは、ハイレモンというブランドが大切にしている価値観と深く関わっています。
食べ物の記憶というのは、味だけで構成されるものではありません。そのとき誰といたか、どんな場所で食べたか、どんな気持ちだったか。さまざまな要素が組み合わさって、一つの記憶として心に刻まれます。
そして、その記憶を呼び起こすトリガーとなるのが、視覚的な要素なのです。
白・黄・緑のパッケージを見た瞬間、「あ、ハイレモンだ」と認識する。箱を開けてPTPシートを取り出す手の動き。シートからタブレットを押し出す感触。これらすべてが、かつて自分が子どものころに体験したことと同じである。
その一致が「あのころ食べたハイレモンだ」という懐かしさを生み出すのです。親が子どもに「これ、お父さんも子どものころ食べてたんだよ」と語りかけるとき、目の前にあるハイレモンが自分の記憶の中のものと同じであることが大切なのです。
ハイレモンの変更された要素
| パッケージの基本カラー | 変化なし | 白・黄・緑を維持 |
|---|---|---|
| 箱の形状 | 変化なし | 発売時から同じ形状 |
| ビタミンC配合量 | 調整あり | 時代に応じて調整 |
| オリゴ糖配合量 | 調整あり | 時代に応じて調整 |
| ロゴデザイン | 調整あり | 時代に応じて微調整 |
見た目の基本的な印象は保ちながらも、中身については時代に合わせた改良が続けられてきました。
ビタミンC配合量の調整
ビタミンCの配合量は、栄養学の進歩や消費者のニーズに応じて調整されています。栄養機能食品として認められるための基準を満たしながら、より効果的な量を追求してきたのです。
オリゴ糖の配合
また、オリゴ糖という成分も配合されていますが、その量も時代とともに見直されてきました。オリゴ糖は腸内環境を整える働きが注目されている成分で、健康意識の高まりとともに、その配合にも工夫が加えられているのです。
ロゴの微調整
パッケージのロゴについても、よく見ると時代ごとに少しずつ変化しています。文字の書体が微妙に調整されたり、配置が変わったりしています。しかし、これらの変更は、あくまで「原型を失わない」という大原則のもとで行われています。
ハイレモン誕生時の時代背景
ハイレモンが誕生した1980年という年を理解するためには、その少し前、1970年代の社会の空気を感じ取る必要があります。この時代、ビタミンCという栄養素が、世界中で大きな注目を集めていました。
きっかけを作ったのは、アメリカの化学者ライナス・ポーリングです。彼はビタミンCと風邪の関係性について研究を行い、その成果を著書として発表しました。
現代では、コンビニでビタミンC入りの飲料を買うことは日常的な光景です。しかし、1970年代はまだそうではありませんでした。ビタミンCを食品に配合するという発想自体が、比較的新しいものだったのです。
健康志向菓子という新領域|ヨーグレット発売
こうした時代の流れを受け、明治製菓(現・明治)は“健康志向の菓子”という新しい領域に踏み出します。
1979年、同社が発売したのが「ヨーグレット」です。
ヨーグルト味の錠菓として親しまれたこの商品は、単に味を楽しむだけでなく、「おいしく食べながら体にも良い」という、当時としては革新的なコンセプトを掲げて登場しました。
お菓子に“機能性健康食品”という要素を持たせた先駆的な存在だったのです。
第二の健康志向菓子の開発|ハイレモン発売
ヨーグレットの発売は、明治製菓にとって一つの挑戦でしたが、市場からの反応は良好でした。
そこで同社は、この健康志向菓子というカテゴリーをさらに広げていく戦略を立てます。
ヨーグレットに続く第二の商品として、ビタミンCに焦点を当てた菓子を開発することになったのです。
こうして1980年、ヨーグレットに続く健康志向食品として、そしてビタミンC入り菓子という新しいジャンルを切り開く商品として、ハイレモンが市場に登場しました。
ハイレモンは賞味期限が延びた?
| 項目 | 変更前 | 変更後 | 変更年 |
|---|---|---|---|
| 賞味期限 | 9か月 | 12か月 | 2021年 |
2021年、ハイレモンに関する一つの技術的な改良が発表されました。それは、賞味期限の延長です。それまで9か月だった賞味期限が、12か月へと延びることになったのです。
品質を維持しながら、より長期間の保存が可能になったことは、消費者にとっても、流通に関わる人々にとっても、大きなメリットです。店頭での販売期間に余裕が生まれ、家庭で買い置きしておく場合にも、より安心して保管できるようになりました。
この変更は、単に数字を書き換えただけのものではありません。その背景には、綿密な科学的検証がありました。食品の賞味期限を設定するには、保存試験という手続きが必要です。
これは、実際に商品を一定期間保管して、その品質がどのように変化するかを詳しく調べる試験です。
保存試験では、さまざまな条件下で商品を保管します。温度や湿度を変えながら、味、香り、色、食感、栄養成分などが時間とともにどう変化するかを測定していきます。
ハイレモンの企業体制の変革
明治産業へ製造を委託
ハイレモンを取り巻く企業体制は、2023年に大きな転換点を迎えました。
ハイレモンは1980年の発売以来、明治製菓(その後の明治)のブランドとして市場に提供されてきました。しかし、実際の製造工程は、明治産業という別の会社が担当していました。
明治がハイレモンというブランドを所有し、商品企画や販売戦略を立てる。一方、明治産業が実際に工場でタブレットを作り、パッケージに詰めるという製造業務を行っているということです。
これは「受託製造」と呼ばれる仕組みです。
受託製造というのは、ブランドを持つ会社が、製造だけを別の会社に依頼する形態です。
明治産業を丸紅に売却
2023年3月、この長年の関係に大きな変化が訪れます。
この売却に伴い、もう一つの重要な決定が発表されました。
それは、ハイレモンの商標権の移管です。
明治は、ハイレモンの商標権を明治産業に譲渡することを決め、将来的にはこの権利が丸紅に渡ることも同時に発表されました。
発表から約2か月後の2023年5月10日、明治産業は正式に丸紅の完全子会社となりました。
明治産業がアトリオン製菓へ社名変更
そして、さらに1か月あまり後の2023年6月19日、明治産業という社名が、アトリオン製菓へと変更されました。
こうして、ハイレモンは明治グループから離れ、丸紅グループの商品として歩み始めることになりました。
ハイレモンがテレビ番組で大反響
2024年、ハイレモンにとって新しい転機となる出来事がありました。フジテレビ系列で放送されているバラエティ番組『ホンマでっか!?TV』で、この菓子が取り上げられたのです。
番組で紹介されたのは、ハイレモンに含まれる糖分とビタミンCが、疲労回復に効果的であるという内容でした。糖分は即座にエネルギーとして利用でき、ビタミンCは体のさまざまな機能をサポートする。この二つの成分が組み合わさることで、疲れたときの栄養補給に役立つという説明がなされたのです。
放送後の反響は、予想を大きく上回るものでした。それまでハイレモンは、どちらかといえば「懐かしい菓子」というイメージで語られることが多かったのですが、この放送をきっかけに「疲労回復に役立つ菓子」という新しい認識が広まっていきました。
特に、レモンという果実や黄色いパッケージから夏を連想する人が多く、夏の暑さで疲れたときの栄養補給という新しい用途が注目されるようになりました。店頭では在庫が品薄になる状況も発生しました。
2025年の新商品「ハイレモン塩飴C」
2025年、この反響を受けて、ハイレモンのラインナップに新しい商品が加わりました。それが「ハイレモン塩飴C」です。
私たちの体は、汗をかくことで体温を調節しますが、汗と一緒に塩分も失われていきます。特に夏場は大量の汗をかくため、失われた塩分を補給する必要があります。
「ハイレモン塩飴C」は、この塩分補給の機能と、従来のハイレモンが持つビタミンC補給の機能を組み合わせた商品です。飴という形状を選んだのは、舐めながらゆっくりと成分を摂取できるという利点があるためです。
ハイレモンの取り扱い店舗の拡大
| 販売場所 | 従来 | 2025年以降 |
|---|---|---|
| スーパー | ○ | ○ |
| コンビニ | △ | ○ |
| ドラッグストア | △ | ○ |
新商品の投入と同時に、もう一つの変化が起こりました。それは、販売網の拡大です。
従来、ハイレモンを購入できる場所は、主にスーパーマーケットでした。コンビニやドラッグストアでも扱われてはいましたが、必ずしも全ての店舗で見かけるわけではありませんでした。
しかし2025年以降、コンビニやドラッグストアでの取り扱いが積極的に拡大されました。
- コンビニは、駅前や住宅街など、生活のさまざまな場面で立ち寄る場所
- ドラッグストアは、健康や美容に関心の高い人々が集まる場所
こうした店舗でハイレモンを手に取りやすくすることで、より多くの人々に届けられるようになったのです。
この販売網の拡大は、単に売上を増やすためだけのものではなく、ハイレモンの新しい役割を浸透させるという意図も含んでいます。
年齢によるハイレモンとの接触機会
小学生時代
小学生のころを思い返してみてください。買い物に行くとき、多くの場合は親と一緒だったはずです。週末、家族でスーパーマーケットへ出かける。そこで、お菓子売り場を見て回る。ハイレモンの白・黄・緑のパッケージを見つける。「これ買って」とお願いするか、あるいは親が「遠足にこれ持っていく?」と提案する。こうした経験を通じて、ハイレモンは子ども時代の記憶の一部となっていきます。
中高生時代
しかし、中学生、高校生と成長していくにつれて、買い物の仕方が変わります。学校帰りに友達と立ち寄るのは、スーパーではなくコンビニです。限られた小遣いで、その場で食べるお菓子を選ぶ。コンビニの棚は、スーパーとは品揃えが異なります。新しい商品、話題の商品が優先的に並べられる傾向があります。こうして、自然とハイレモンを目にする機会は減っていきます。日常の中からハイレモンが遠ざかり、いつしか「子どものころに食べた、懐かしいお菓子」という記憶の中の存在になっていくのです。
社会人以降
この消費パターンの変化に対して、ハイレモンを扱う企業側も、新しい戦略を打ち出しました。それが、コンビニやドラッグストアでの取り扱い拡大だったのです。中高生や若い社会人が日常的に立ち寄るコンビニで、ハイレモンを手に取れるようにする。健康意識の高い大人たちが訪れるドラッグストアで、ビタミンC補給の選択肢として提示する。こうした取り組みによって、ハイレモンは「懐かしいもの」という枠を超えて、「今も日常的に食べるお菓子」という新しい位置づけを目指しているのです。
ハイレモンは現在も販売中
1980年に誕生したハイレモンは、2025年で発売から45年を迎えました。45年という年月は、親子二世代、あるいは三世代にわたる長い時間です。その歩みを振り返ると、社会の変化とともに、人々の暮らしの中にどのように溶け込んできたかが見えてきます。
爽やかなレモンの味と元気を届けるお菓子
発売当初の1980年代は、まだインターネットも携帯電話もない時代でした。情報はテレビや雑誌、新聞から得るもので、買い物は店頭で商品を手に取って選ぶのが当たり前。ハイレモンは、そんな日常の中で子どもたちのポケットに入る定番のお菓子として親しまれてきました。
一方で、2025年の今、私たちはスマートフォンを使って簡単に情報を得たり、オンラインで買い物をしたりできる時代に生きています。お菓子ひとつを選ぶにも、SNSの口コミやレビューを参考にすることが増えました。それでも、ハイレモンは変わらず私たちのそばにあります。
時代の流れに合わせて、ビタミンCの量を調整したり、賞味期限を延ばしたり、企業体制を変えたりと進化を続けてきましたが、その根底にある「爽やかなレモンの味と元気を届けるお菓子」という本質は、今も変わっていません。
45年も愛され続けている理由
45年という年月の中で、多くの商品が姿を消していきました。その中で、ハイレモンが生き残り、愛され続けているのは、単に味や品質の良さだけでなく、人々の心に残る“記憶”を持っているからかもしれません。
- 遠足のバスの中で友達と分け合ったハイレモン。
- 試験勉強の合間に食べて気持ちを切り替えたあの瞬間。
- 暑い夏の日、疲れた体を癒してくれたあの酸っぱさ。
ハイレモンは、私たちの人生のさまざまな場面に寄り添ってきました。
これからも、ハイレモンは親から子へ、子から孫へと受け継がれていくでしょう。白と黄色、そして緑が映えるパッケージを見たとき、きっと誰かの心に懐かしい記憶がよみがえります。PTPシートを押し出す指先の感覚や、口の中いっぱいに広がるレモンの香りが、あのころの思い出をそっと呼び覚ますのです。