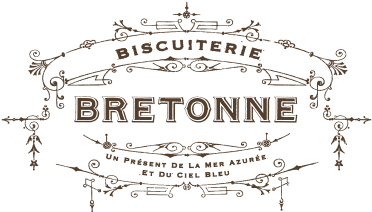あいすまんじゅうとは|丸永製菓の大ヒット和洋折衷アイス

あいすまんじゅうとは何か
あいすまんじゅうは、西洋のアイスクリームに日本の和菓子である小豆あんを組み合わせた、二層構造のアイスクリームです。
外側はバニラアイスクリームで、その内部には小豆あんが詰まっています。
内側の小豆あんは、アイスクリームの中心部分にまとまって入っています。
あいすまんじゅうの形
あいすまんじゅうは、梅の花のような形をしています。
5枚の花弁を思わせる丸みを帯びた形状です。
この形は、製造元である丸永製菓の本社がある福岡県の県花が梅であることに関係しています。
また、福岡県には学問の神様として知られる菅原道真を祀った太宰府天満宮があり、梅は菅原道真と縁の深い花として親しまれています。
こうした地域的な背景から、梅の花をモチーフにした形が採用されました。
この形状は発売当初から変わっておらず、商品の特徴として定着しています。
あいすまんじゅうの美味しい食べ方
冷凍庫から取り出してすぐに食べると、アイスクリームが固すぎて本来の味わいを楽しむことができません。
推奨されているのは、室温で約5分待ってから食べることです。
この時間を置くことで、アイスクリームが適度に柔らかくなり、小豆あんとの食感のバランスが最適になります。
あいすまんじゅうの人気
全国的な人気
あいすまんじゅうは、現在では全国に販売が拡大されています。
年間約5000万本という販売数は、全国規模での商業的成功を示しています。
日本全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、アイスクリーム専門店などで安定して売れ続けていることを表しています。
この規模の販売数は、幅広い地域で受け入れられており、一度購入した消費者が繰り返し購入する傾向があることを示しています。
福岡県の県民食
特に福岡県では「県民食」と呼ばれるほど生活に根付いています。
多くの家庭で冷凍庫に常備されています。
世代を超えて愛され続けており、祖父母から孫へと受け継がれる味として位置づけられています。
この地域での定着は、商品の品質だけでなく、地域文化との調和によるものでもあります。
福岡県の梅をモチーフとした形状、和菓子の伝統を受け継いだ味づくり、そして地元企業としての信頼感が相まって、地域のアイデンティティの一部となっているのです。
あいすまんじゅうの人気の理由
時代に合わせた商品展開
あいすまんじゅうは、基本的な味と品質を維持しながらも、時代に合わせた商品展開を行ってきました。
基本となるバニラ味に加えて、現在では抹茶味、栗味、いちご味など、季節限定の商品が数多く展開されています。
これらの季節限定商品は、基本の製造技術を応用しながらも、それぞれの味に合わせて小豆あんやアイスクリームの配合を調整しています。
老舗ブランドとのコラボレーション
他の老舗ブランドとのコラボレーション商品も発売されています。
京都の老舗和菓子店「本家西尾八ッ橋」と協力して作られたニッキ味は、300年以上の歴史を持つ八ッ橋の味をアイスクリームで表現した商品です。
また、仙台の「ずんだ茶寮」監修によるずんだ味では、東北地方の郷土の味である枝豆を使ったずんだあんが使用されています。
これらのコラボレーションは、異なる素材や味を自社の製造技術に適応させ、品質を保ちながら新しい商品を生み出す丸永製菓の技術力があるからこそ可能になっています。
高級路線のシリーズ
高級路線として展開されている「PREMIUMあいすまんじゅう」シリーズも、技術力の応用例と言えるでしょう。
これらの商品では、使用する原材料により高級なものを選び、製造工程でもより丁寧な処理を行っています。
例えば、「大納言づくし」では、通常の小豆ではなく北海道産の大納言小豆を使用し、さらに甘納豆も加えることで、小豆の味わいを多層的に楽しめるようにしています。
あいすまんじゅうのメーカーは丸永製菓
あいすまんじゅうは、福岡県久留米市にある丸永製菓という会社が作っています。
この会社は1933年に和菓子店として創業しました。
そのため、小豆あんを作る技術は長年の経験によって培われていました。
あいすまんじゅう開発の課題
1962年にあいすまんじゅうを発売する際、丸永製菓は従来の和菓子作りとは異なる課題に直面しました。
それは、冷凍しても固くならない小豆あんを作ることでした。
通常の小豆あんを冷凍庫で冷やすと、水分が凍って固くなってしまいます。
これでは、柔らかいアイスクリームと一緒に食べた時に食感のバランスが悪くなってしまいます。
解決方法
開発チームが注目したのは、ようかんの製法でした。
ようかんは冷やしても適度な柔らかさを保つことができるのは、水分量を適切にコントロールしているからです。
この原理を応用して、何度も試作を重ねた結果、冷凍状態でもなめらかで柔らかい食感を保つ小豆あんの製造に成功したのです。
この技術開発によって、アイスクリームと小豆あんが口の中で調和する味わいを実現しました。
あいすまんじゅうの製造工程
金型にクリームを流し込む
製造は梅の花の形をした金型から始まります。
この金型を十分に冷やした状態で、液状のバニラアイスクリームを流し込みます。
この時、金型を冷やす温度やクリームの量、流し込む時間を正確に管理することで、次の工程へ進むための準備を行います。
外側を固める
液状のバニラアイスクリームを流し込むと、金型に接している部分から順番に固まり始めます。
金型の温度とクリームの温度、そして時間を正確にコントロールすることで、外側だけが固まって内側が液状のままという状態を作り出します。
液状クリームの除去
この段階で、まだ固まっていない内側の液状クリームを取り除きます。
すると、梅の花の形をしたカップのような空洞ができあがります。
この空洞部分に、中心となる小豆あんを詰める準備が整います。
小豆あんを詰める
空洞部分に、冷凍でも柔らかい特別な小豆あんを詰め込みます。
小豆あんの量は正確に計量されており、最終的な味のバランスを考慮して決められています。
内側のクリームを注入
小豆あんを詰めた後、再び液状のバニラアイスクリームを注入し、木製の棒を差し込みます。
この時のクリームは、外側とは異なる配合になっています。
食べる人の食感体験を向上させるために、外側と内側で硬さを変えているからです。
外側のアイスクリームは空気の含有量を少なくして固めに作り、小豆あんをしっかりと支える役割を果たします。
一方、内側のクリームは空気をより多く含ませてふんわりとした食感にし、口溶けを良くしています。
急速冷凍で仕上げる
最後に全体を急速冷凍することで、理想的な食感のあいすまんじゅうが完成します。
冷凍過程でも温度管理は重要で、あまり急激に冷やすと食感が損なわれ、逆にゆっくり過ぎると品質が保てません。
適切な温度カーブで冷却することで、理想的な食感のあいすまんじゅうが完成します。
あいすまんじゅうの品質管理
衛生管理
食品製造、特にアイスクリーム製造においては、衛生管理が極めて重要です。
丸永製菓では、国際的な安全基準に準拠した管理体制を構築しています。
工場への立ち入りには厳格な手順が設けられています。
作業員は手洗い、ブラッシング、着替えなど約15分かけて衛生処理を行い、さらには眉毛の手入れまで求められます。
これは、製品に異物が混入することを防ぐための徹底した対策です。
日々のチェック
毎日、必ず味見による品質チェックが実施されています。
これは単に味を確認するだけでなく、食感、温度、外観など多角的に製品を評価する作業です。
このような日々の品質管理により、常に安定した品質の製品が提供されています。
国際的な評価
あいすまんじゅうは、ベルギーの品質評価機関であるモンドセレクションから、1996年から2007年、および2009年から2020年にかけて金賞を受賞しています。
モンドセレクションでは、味覚、衛生、パッケージ、原材料などの多項目にわたって厳格な審査が行われます。
この受賞は、品質の高さを示す客観的な証拠と言えるでしょう。
まとめ
あいすまんじゅうは、和菓子の伝統的な技術とアイスクリームという西洋の食品が融合した商品です。
伝統的な技術と現代的な製造技術の融合、地域性を活かした商品開発、品質への徹底したこだわり、そして時代に合わせた柔軟な商品展開が、あいすまんじゅうの成功につながっています。
この商品は、日本の「和洋折衷」文化を象徴する存在でもあります。
西洋から伝わったアイスクリームに、日本の伝統的な小豆あんを組み合わせることで、独自の価値を創造しました。