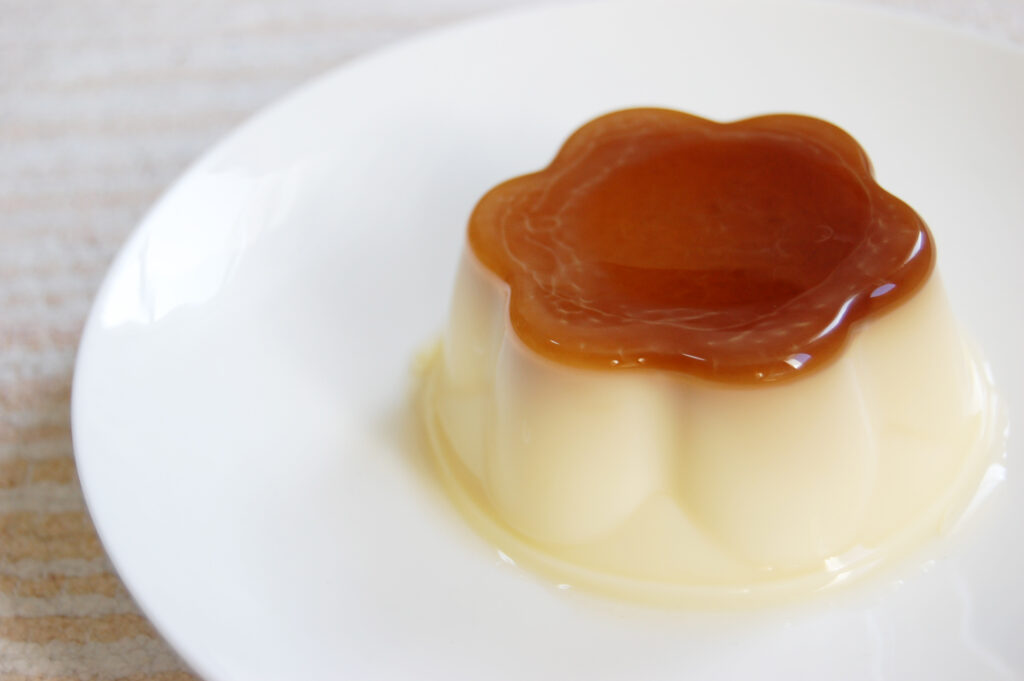木村儀四郎とは|あんぱんを全国に広め、ジャムパンを生んだ功労者

木村儀四郎とは
木村儀四郎(きむら・ぎしろう)は、銀座木村屋の三代目当主であり、あんぱんを全国に広めた人物です。さらに、日本で初めて「ジャムパン」を生み出したことでも知られています。
全国に普及
日本初の発明
木村屋とは
木村屋は、1869年(明治2年)に創業された老舗のパン屋です。
創業者は木村安兵衛(やすべえ)。元々は酒造業を営んでいましたが、明治時代の文明開化の流れを受け、銀座でパン屋を始めました。
銀座という当時最先端の地で開業した木村屋は、やがてその名を全国に轟かせることになります。そのきっかけとなったのは、明治天皇へのあんぱんの献上でした。
日本の伝統的な餡と西洋のパンが出会ったあんぱんは、その斬新な組み合わせと上品な味わいで宮中を魅了し、一躍話題となり、木村屋は名店の仲間入りを果たしたのです。
現在も「銀座 木村家」として営業しており、あんぱんをはじめとした菓子パンの名店として知られています。
木村家の相関図


木村儀四郎と木村屋
兄の死と家の危機
明治20年、二代目当主である木村英三郎が36歳の若さで急逝するという不幸が訪れます。その翌年には、木村屋の発展に大きく貢献した恩人・山岡鉄舟もこの世を去りました。さらに明治22年には、創業者である安兵衛までもが73歳で逝去。
当時、家業を支えるのは安兵衛の妻・ぶんと、儀四郎の妻・ゆうの二人の女性のみ。儀四郎はというと、すでに家を出ており、その消息は長らく途絶えていました。
相次ぐ不幸は、木村屋の存続そのものを危うくするほどの大きな打撃となり、木村屋はこのまま終わるのではないかという声すら上がっていました。
約10年ぶりに儀四郎が帰還
そんな危機的状況の中、明治28年の春、儀四郎は約10年ぶりに銀座本店へと戻ってきます。母・ぶんに長年の無沙汰を詫び、当時の大金である一万円を差し出して許しを請いました。
この10年間、儀四郎は決して遊んでいたわけではありませんでした。彼は静岡、新潟、金沢といった各地で直営店を運営し、積極的にあんぱんを広める活動を行っていたのです。その足跡は国内にとどまらず、中国や台湾にまで及び、市場調査を行うなど、海外への展開も視野に入れていました。
儀四郎が各地で蒔いたあんぱんの種は、明治30年頃になると日本全国で花開き、あんぱんの人気は爆発的に高まります。彼の先見の明と行動力が、木村屋を再び成長軌道に乗せたということです。
木村屋を支えた「ぶん」と「ゆう」
儀四郎が不在の10年間、木村屋を守ったのは女性たちでした。
安兵衛の妻「ぶん」と、儀四郎の妻「ゆう」が、男の職人たちをまとめて切り盛りしていたのです。
社会的に女性の地位が低かった時代。
ぶんのリーダーシップがなければ、木村屋は残らなかったかもしれません。
その後、ぶんは儀四郎に店を託し、明治30年に静かに息を引き取りました。
ゆうもまた、夫である儀四郎を支え、木村屋の発展に大きく貢献しました。
ジャムパン誕生の背景
明治時代後期、日本は日露戦争を見据えて軍用食の改善を進めていました。
戦場で炊飯する日本兵が敵の攻撃を受ける一方、欧米の兵士は火を使わない乾パンと缶詰で食事を済ませていたからです。
この状況を受け、軍はパン屋や菓子職人に協力を求め、大規模なビスケット工場の建設を計画しました。
実験を任されたのが、儀四郎らが立ち上げた「東洋製菓」です。
ここで、日本初の乾パンが完成し、日露戦争における兵士たちの重要な食糧となったのです。
偶然から生まれたジャムパン
乾パンの研究中、儀四郎はビスケット生地にジャムを挟んで焼く工程を見て、
「あんの代わりにジャムを使ったらどうだろう」とひらめきます。
早速銀座の本店で試作し販売したところ、これが驚くほどの大ヒットとなります。
こうして日本で初めての「ジャムパン」が誕生しました。
まとめ
木村儀四郎は、単にあんぱんを全国に広めただけでなく、日本の食文化に新たな風を吹き込んだ革新者でした。
乾パンの開発への貢献、そして日本初のジャムパンを生み出した功績は、彼の独創性と時代を読む力、そして何事にも挑戦するパイオニア精神の賜物と言えるでしょう。
木村儀四郎の功績は、今もなお、日本のパン文化の礎として語り継がれています。