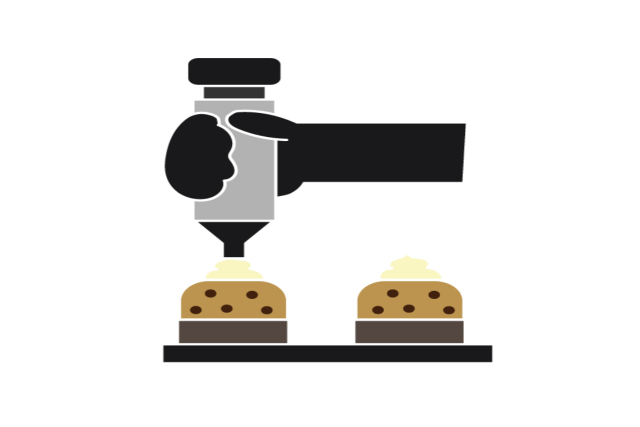オペラとは|菓子職人の技術力が試されるチョコケーキ

オペラとは何か
オペラは、フランスで生まれた長方形のチョコレートケーキです。
まず、このケーキがどのような分類に属するかから理解していきましょう。
菓子の世界では、ケーキを大きく分けると個人で食べる小さなものと、複数人で切り分けて食べる大きなものがあります。
オペラは後者にあたり、フランス語で「アントルメ」と呼ばれるカテゴリに属しています。
アントルメとは、ホールケーキのような大型菓子のことを指す専門用語です。
オペラの外見
オペラの外見を詳しく見てみると、縦横比が長方形になっており、高さは2センチメートルから3センチメートル程度となっています。
オペラの形と高さの決まり
オペラには古くから「高さが3センチメートルを超えてはならない」という決まりがあります。
この制約があるからこそ、オペラを作る菓子職人は各層を薄く均一に重ねる高度な技術を身につける必要があるのです。
表面の装飾
表面には艶やかで滑らかなチョコレートのコーティングが施されています。
このコーティングは「グラサージュ」と呼ばれる技法で作られており、鏡のような光沢を生み出します。
さらに、表面には金箔が散らされることが多く、これがオペラに上品で豪華な印象を与えています。
時には金箔の代わりに、チョコレートで「opéra」という文字が書かれることもあります。
オペラの内部構造
オペラの内部構造は、複数の層が美しく重なっているのが特徴です。
ケーキを構成する層
ケーキを横から切って断面を見ると、一般的には7つの層で構成されていますが、作り手によって5層から8層まで様々なパターンがあります。
この層の数の違いは、それぞれの菓子職人やブランドが持つこだわりや製法の違いを反映しています。
各層の材料
オペラを構成する主要な材料を、それぞれ詳しく説明します。
ビスキュイジョコンド
まず基本となるのが「ビスキュイジョコンド」と呼ばれるスポンジ生地です。
これは通常のスポンジケーキとは異なり、アーモンドパウダーを加えて作られます。
アーモンドパウダーを使うことで、生地にしっとりとした食感と豊かな風味が生まれます。
コーヒー風味のバタークリーム
次に重要な要素が、コーヒー風味が付けられたバタークリームです。
バタークリームは卵黄、砂糖、牛乳で作ったカスタードベースに無塩バターを合わせて作られ、なめらかで口どけの良い食感を持ちます。
ガナッシュ
三つ目の主要な構成要素がガナッシュです。
ガナッシュとは、チョコレートと生クリームを合わせて作られるクリーム状のもので、オペラでは主にビターチョコレートが使用されます。
このガナッシュが、ケーキに濃厚でリッチなチョコレートの味わいをもたらします。
層の組み立て方
ビスキュイジョコンド生地、バタークリーム、ガナッシュは交互に重ねられていきます。
例えば、底から順に生地、バタークリーム、生地、ガナッシュ、生地、バタークリーム、生地というように積み重ねられ、最後に表面全体がチョコレートのグラサージュでコーティングされます。
オペラの歴史
オペラの誕生には、複数の説と複雑な経緯があります。
ダロワイヨでの誕生説
1955年にパリの老舗パティスリー「ダロワイヨ」で誕生したという説が広く知られています。
ダロワイヨ社を買収したシリアック・ガヴィヨンという人物が開発し、その妻のアンドレが「オペラ」と名付けたとされています。
原型に関するもう一つの説
菓子研究家の大森由紀子によると、ダロワイヨより前に「マルセル・ビュガ」というパティスリーで、オペラの原型となるお菓子が作られていたという指摘があります。
第二次世界大戦の前後に活躍したパティシエのルイ・クレシーという人物が作っていた「クリシー」というお菓子が、その原型だったというのです。
クレシーから店を譲り受けたマルセル・ビュガが、ホームパーティでこの「クリシー」を振る舞ったところ、ダロワイヨのオーナーがそれを気に入り、名前を「オペラ」に改めて自分の店で販売するようになったという経緯があったとされています。
オペラの由来
オペラという名前や、表面を飾る金箔には、それぞれ由来があります。
名前の由来
これには複数の説があります。
もっとも有力とされるのは、1875年に完成したパリ9区にあるオペラ座ガルニエ宮との関連です。
ダロワイヨがオペラ座の近くにあったことから、この名前が選ばれたという説があります。
別の説としては、オペラ座で活躍するエトワール、つまり主役級のバレリーナや練習生たちがダロワイヨを訪れることが多かったため、彼らに捧げる意味を込めて命名されたというものがあります。
また、ケーキの層構造がオペラ座の観客席を連想させるという解釈や、当時オペラ座で活躍していたチョコレート好きの歌手のために作られたという話も残っています。
金箔の由来
オペラの表面を飾る金箔にも深い意味があります。
これは、オペラ座の屋根に立つ金色のアポロン神像をイメージして施されたものです。
アポロンはギリシャ神話に登場する芸術の神で、音楽や詩歌を司るとされています。
オペラ座の象徴的な存在でもあるこの神像にちなんで金箔を使うことで、ケーキに芸術的な美しさと格調の高さを表現しているのです。
オペラの作り方
ビスキュイジョコンドの作成
オペラを作るための最初のステップは、土台となるビスキュイジョコンドという生地を作ることです。
これは通常のスポンジ生地とは違い、アーモンドパウダーを加えて作られます。
まず、卵に粉糖とアーモンドパウダーを混ぜ合わせます。
次に、別に泡立てておいたメレンゲと薄力粉を加え、生地を完成させます。
この生地は焼き上げた後、冷ましてから使用します。
コーヒー風味シロップの準備
生地に風味としっとり感を与えるため、コーヒー風味のシロップを用意します。
砂糖と水を煮詰めてから、インスタントコーヒーを溶かします。
粗熱が取れたらラム酒を加え、香りをプラスします。
このシロップを生地に均一に染み込ませることで、ケーキ全体にコーヒーの芳醇な香りと適度な湿り気がもたらされます。
バタークリームとガナッシュの作成
ケーキの主要なフィリングであるバタークリームとガナッシュも、この段階で作ります。
コーヒー風味のバタークリームは、まず卵黄と砂糖、牛乳でカスタードベースを作ります。
このカスタードベースに、室温に戻した無塩バターを加えてなめらかになるまで混ぜ合わせます。
最後に、インスタントコーヒーを加えて風味を付けます。
一方、ガナッシュは、刻んだビターチョコレートを、生クリームと無塩バターと合わせて溶かし、なめらかになるまで混ぜて作ります。
組み立て作業
生地へのシロップの塗布
材料がすべて準備できたら、ケーキの組み立てに入ります。
まず、焼き上がったビスキュイジョコンド生地を必要な枚数に分けます。
それぞれの生地に、刷毛を使ってコーヒー風味のシロップを均等に染み込ませます。
この工程により、生地に適度な湿り気と香りが加わります。
各層の重ね方
シロップを染み込ませた生地の上に、バタークリームとガナッシュを交互に重ねていきます。
基本的には、「生地、バタークリーム、生地、ガナッシュ」という順序で丁寧に積み重ねていきます。
この際、各層の厚さが均一になるように注意することが、美しい仕上がりにとって重要なポイントです。
グラサージュでのコーティング
全ての層を重ね終わったら、最後に表面全体をチョコレートのグラサージュでコーティングします。
グラサージュは適切な温度に温めてから、一気にケーキの上から流し入れ、表面を平らにならします。
その後、冷蔵庫でしっかりと冷やし固めます。
仕上げのカット
ケーキが固まったら、最後にサイドを切りそろえて完成です。
カットする際は、包丁を温めてから使い、切るごとに包丁をきれいに拭き取ります。
こうすることで、層の境界線がくっきりとした美しい断面を作ることができます。
オペラの味わいと楽しみ方
完成したオペラの味わいや、美味しく食べる方法について説明します。
味わい
オペラの味わいは、ビターチョコレートとコーヒーの風味が調和した、濃厚でリッチなものです。
口に含むと、まずチョコレートグラサージュの滑らかさを感じ、続いて各層の異なる食感が順番に現れます。
アーモンドパウダーを使ったビスキュイ生地の軽やかさ、バタークリームのなめらかな口どけ、ガナッシュの濃厚さが複雑に絡み合い、一口ごとに変化する味わいを楽しむことができます。
コーヒー風味のシロップとバタークリームにより、ケーキ全体にコーヒーの芳醇な香りが漂います。
この香りとビターチョコレートの苦味が組み合わさることで、甘さは控えめでありながらも深みのある大人の味わいが生まれます。
菓子職人の技術力が試される
菓子職人にとって、オペラは技術力を試される重要な課題の一つとされています。
雑誌『料理通信』編集長の君島佐和子は、オペラについて「非常に手間がかかる上、層が美しいかどうかが一目瞭然なので、とても神経を使うケーキ」と述べており、その製作の困難さを表現しています。
製菓学校では、チョコレートソースで「Opéra」の文字を書くという技術試験が課されることもあり、学習者の技術習得度を測る指標として用いられています。
美味しく食べる方法
冷蔵庫から出して少し常温に置いてから食べると、バタークリームやガナッシュが適度に柔らかくなり、より滑らかな口どけを楽しむことができます。
また、オペラはコーヒーとの相性が良いとされています。
エスプレッソやブラックコーヒーと合わせると、ケーキに含まれるコーヒー風味と飲み物のコーヒーが相乗効果を生み、より深い味わいを楽しむことができます。
オペラの現在と多様な展開
オペラは現在、世界中の多くの国で作られ、愛されるケーキとなっています。
世界と日本での位置づけ
パリのダロワイヤ本店では、サヴァランと並ぶ商品となっており、1日に平均800個から1200個を売り上げるという記録があります。
日本においても、ダロワイヨの日本店舗をはじめ、多くのパティスリーでオペラが販売されています。
日本独自のオペラ
日本では、伝統的なレシピをベースにしながらも独自のアレンジを加えた商品も登場しています。
例えば、ホテルニューオータニ内の「パティスリーSATSUKI」では「オペラレジェール」という名前で、全8層構成のオペラを提供しています。
近年では、抹茶を使った日本風のオペラも登場しており、これは「Kabuki(歌舞伎)」と呼ばれることがあります。
これは、フランスの伝統的なオペラに対して、日本の伝統芸能である歌舞伎の名前を付けることで、文化的な対比を表現したものです。
新しい商品形態
2019年には、ダロワイヤの日本法人が「オペラ トーキョー」という常温保存可能な焼き菓子版のオペラを発売しました。
これは贈答品としての需要に応えるために開発されたもので、従来のオペラとは異なり、常温で保存できるため、贈り物としてより利用しやすい商品となっています。
まとめ
オペラは単なるケーキを超えて、フランスの菓子文化と芸術的な美意識を体現した存在です。
複雑な構造と繊細な味わい、そして美しい外観は、長い歴史の中で多くの人々を魅了し続けてきました。
伝統的な製法を守りながらも、各地の文化や現代のライフスタイルに合わせた新しいアイデアを取り入れた商品開発が続けられており、今後も世界中で愛され続けることでしょう。