第2回全国学生パイコンテストが開催されました
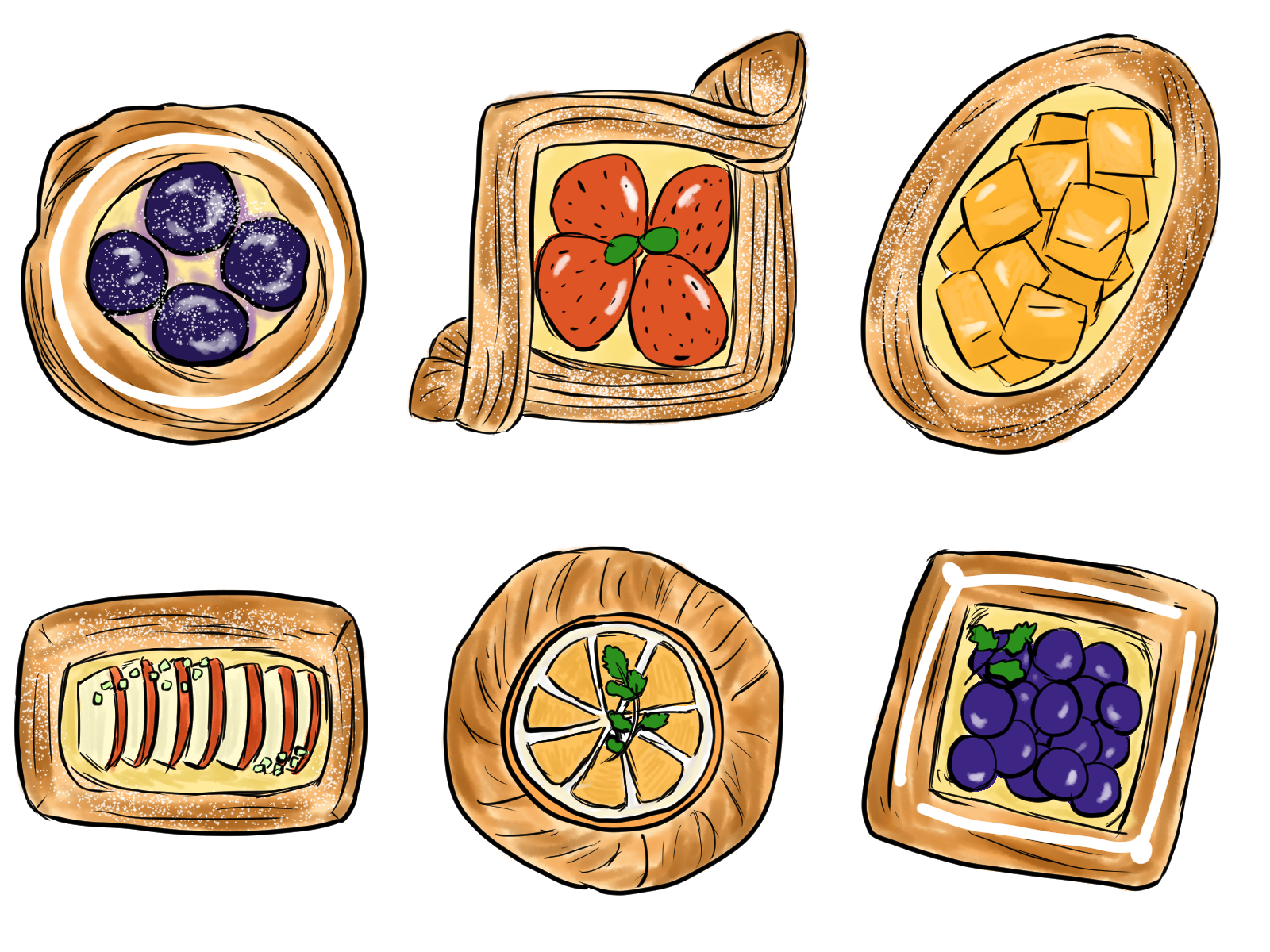
全国学生パイコンテストとは
「全国学生パイコンテスト」は、将来の食品業界を担う若者たちを対象とした、パイ作りの技術とアイデアを競う大会です。
このコンテストは、日本パイ文化財団という団体が主催しており、パイの美味しさや奥深い技術、文化的な価値を次の世代に伝えていくことを目的としています。
学生たちが日頃の学びの成果を発揮し、新しい視点や創造性をもってパイ作りに挑戦する、年に一度の祭典です。
全国の学生が集う「パイの祭典」
日本では近年、伝統的なお菓子だけでなく、パイという焼き菓子に注目が集まっています。
パイは、小麦粉を主原料とした生地を何層にも重ねて作る、サクサクとした食感が特徴です。
この技術はヨーロッパで生まれ、生地を薄く伸ばしては折り込む作業を繰り返すことで、美しい層が生まれます。
日本のパイ文化を広める活動
このパイ文化を広め、技術を次の世代に伝えるために、「日本パイ文化財団」という団体が活動しています。
財団は、パイ作りの技術や文化的な価値を若い人たちに教えることを大切な使命としています。
経験豊かな職人から若い人たちへ直接教えることで、技術が確実に受け継がれていきます。
第2回全国学生パイコンテストが開催されました
こうした背景のもと、財団は今年8月22日に「第2回全国学生パイコンテスト」を開催しました。
会場は、大阪市西区にある「ハグミュージアム」という、食文化や料理技術を学べる施設です。
このコンテストは、将来食品業界で活躍する学生たちに、パイ作りの楽しさや技術に触れてもらい、専門性を深めてもらうことを目的としています。
コンテストのテーマ「記念日のパイ」
今回のコンテストのテーマは「記念日のパイ」でした。
これは、単に技術を競うだけでなく、特別な日を彩る食べ物としてのパイの可能性を探ることを目指しています。
このテーマによって、参加者たちは見た目の美しさや、記念日にふさわしい意味を込めた作品作りが求められました。
応募数と本選進出チーム
全国から532もの作品が応募されました。
これは前回を上回る数で、学生たちの間でパイ作りへの関心が高まっていることがわかります。
応募作品はまず書類審査が行われ、レシピの独創性や技術、テーマとの一致度などが評価されました。
その結果、6チームが本選に出場する権利を獲得しました。
本選と審査のポイント
本選では、実際にパイを作り、審査員の前でプレゼンテーションを行いました。
審査は、試食による味の評価だけでなく、見た目の美しさ、一般の人でも作れるかどうかの「再現性」、そして作品に込めた思いを伝える力など、様々な視点から行われました。
単においしいパイを作るだけでなく、食文化を担うために必要な、多くの能力が試されたのです。
最優秀賞を受賞した作品
厳しい審査の結果、最優秀賞に選ばれたのは、吉祥寺二葉栄養調理専門職学校の学生チームでした。
彼らが作った作品は、「御栗物(おくりもの)-敬老の日にみんなで食べるマロンパイ-」という名前です。
敬老の日をテーマにした、意欲的な作品でした。
「御栗物」という名前は、「贈り物」という意味と、栗を使ったお菓子であることをかけた、言葉遊びの要素も含まれています。
視覚的なデザイン
パイを六角形にすることで、日本の伝統的な模様である「亀甲文様(きっこうもんよう)」を表現しました。
亀甲文様は亀の甲羅の形で、長寿や縁起の良さを象徴しています。
敬老の日というテーマに、日本の文化を取り入れることで、作品に深い意味を持たせています。
味わいの工夫
アーモンドクリームとマロンペーストという2つのクリームを組み合わせ、奥深い風味に仕上げました。
さらに、大粒の渋皮栗に、みたらし団子のタレを絡めるという新しいアイデアを取り入れています。
これは、和と洋を組み合わせた新しい試みとして注目されました。
審査員からの評価
審査員は、味の良さだけでなく、見た目の美しさやテーマとの統一性、そして学生たちのパイ作りに対する深い知識や情熱的なプレゼンテーション能力を高く評価しました。
このような総合的な評価は、将来活躍するために必要な能力を測る上で重要です。
コンテストの意義と今後の展望
コンテストを主催した日本パイ文化財団の理事長である、筏由加子氏は、大会を終えて財団の目的を改めて説明しました。
財団の目的
筏理事長によると、財団はパイが持つ「おもしろさ、おいしさ、奥深さ」を多くの人に知ってもらうことを目指しているそうです。
今回のコンテストでは、参加した学生たちが、まさにこれらのパイの魅力を作品を通じて証明してくれました。
受賞作品の商品化
さらに、財団は今後、受賞作品を実際の商品として売り出すことを考えています。
これは、学生たちの努力を一時的なイベントで終わらせず、社会に役立ててもらいたいという願いが込められています。
学生たちの将来への影響
コンテストに参加した学生たちの感想からは、この経験が彼らの将来に大きな影響を与えていることがわかります。
「パティシエを目指して頑張りたい」と語る学生もいれば、「パンメーカーへの就職が決まっているが、この経験を生かしたい」と話す学生もいました。
また、「アイデアを形にするのが好きで応募した。将来はクリエイティブな管理栄養士になりたい」と語る学生もおり、従来の専門職の枠を超えた新しい可能性を示しています。
このコンテストは、単なる技術を競うだけでなく、日本の食文化の未来を担う人材を育てる場となっています。
参加した学生たちが、今回の経験から得た知識と感動が、日本の食文化をより豊かで多様なものにしていく原動力となるでしょう。




