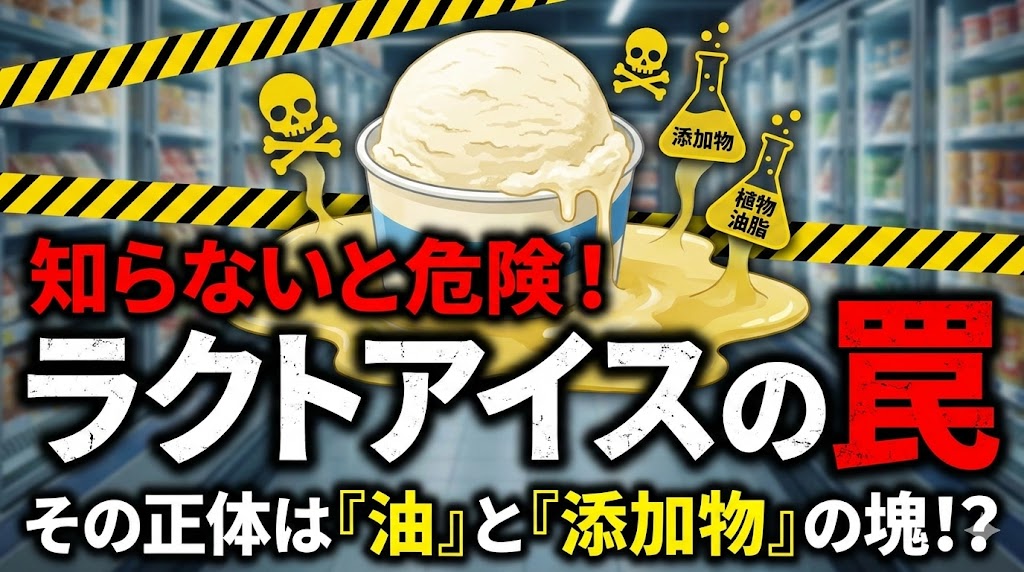生キャラメルとは|流行の理由と作り方

生キャラメルとは
日本の菓子業界では、時として世の中の常識を覆すような商品が突然大人気になることがあります。2000年代後半に現れた「生キャラメル」も、まさにそのような現象の一つでした。
ある日を境に、「生キャラメル、生キャラメル」という言葉がテレビや雑誌から聞こえてくるようになり、まるで魔法にかかったかのように多くの人々の関心を集めたのです。
このブームは、その爆発的な人気が特徴です。商品を求めて長い行列が街のあちこちにでき、それがテレビのニュースで繰り返し放送されました。雑誌を開けば、特集記事が組まれ、スーパーマーケットのチラシには「生キャラメル入荷!」「限定、おひとり様いくつまで!」といった文字が踊り、まるで早い者勝ちのお祭りのような状態でした。
なぜそんなに大人気になったの?
テレビのバラエティ番組では、どのチャンネルを回しても生キャラメルが取り上げられていました。タレントたちが次々と試食し、「これっておいしいー!」「口に入れたとたんに、あっという間にとけちゃう!」「うそー、なにこれ、ちょー不思議!」と、その独特な食感に心から驚きの声を上げていました。この「口の中でスッと溶ける」という、これまでのキャラメルにはなかった新しい体験が、多くの人の心を掴んだのです。
生キャラメルが生まれるまでの不思議な製法
生キャラメルがなぜそんなに柔らかいのか、その秘密は作り方にあります。まずは、普通のキャラメルやドロップ(硬い飴)がどうやって作られるのかを知る必要があります。
煮詰める温度が食感を決める
ドロップやキャラメルは、砂糖を煮詰めて作られます。このとき、どれくらいの温度まで煮詰めるかで、冷やしたときの固さが決まります。煮詰める温度が高ければ高いほど、固く仕上がり、逆に低ければ低いほど、柔らかく仕上がるのです。この原理を理解すれば、いろいろなお菓子の食感の違いがよく分かります。
従来のキャラメルとドロップの作り方
私たちが知っているドロップは、だいたい145度くらいまで砂糖を煮詰めてから冷やします。この高い温度で煮詰めることで、冷えるとカチカチに固まり、噛むとガリッと砕けるような食感になるのです。
一方、従来のキャラメルは、ドロップほど高温にはしません。少し硬めのキャラメルでも135度くらいまで、柔らかいキャラメルになると129度くらいまでで火からおろします。これにより、ドロップより柔らかく、適度な歯ごたえがあるキャラメルが完成します。
常識を覆した「生キャラメル」の誕生
これまでのキャラメルの常識を、生キャラメルは大きく変えました。生キャラメルは、なんと115度前後という、これまでのキャラメルよりもずっと低い温度で火からおろしてしまうのです。
「失敗作」から生まれた大ヒット商品
通常の製菓理論からすると、この低い温度では砂糖が固まらず、まるで「失敗作」のような状態になります。しかし、生キャラメルは、この柔らかすぎる状態をさらに冷やして、なんとか形を保てるようにして商品にしています。そのため、少しでも温かい場所に置いておくと、すぐに溶けて形が崩れてしまいます。お店では冷蔵ケースに入れて売られていることもありました。
この極端に柔らかい生キャラメルを口に入れると、人の体温(約38度)ですぐに溶けてしまいます。噛む必要もなく、あっという間に口の中から消えてしまうので、テレビのタレントたちが「不思議!」「とろける!」と驚いていた、あの独特な食感が生まれるのです。
ブームの立役者「田中義剛」氏
この生キャラメルブームを語る上で欠かせないのが、タレントの田中義剛(たなか よしひさ)さんと、彼が立ち上げた花畑牧場という会社の存在です。生キャラメルというアイデアを最初に考えたのが誰かははっきりしませんが、この商品を日本全国に広めたのは、間違いなく田中義剛さんの功績です。
従来の常識を打ち破る成功
このブームが面白いのは、もし伝統的なお菓子職人だったら「固まってないじゃないか!」と怒られてしまうような商品が、大ヒットしたことです。これは、「何が幸いするか分からない」という、商品開発やビジネスの世界の面白い一面を私たちに教えてくれます。
これまでの常識や技術にとらわれず、「とろける」という新しい食感や体験を人々に提供したことで、生キャラメルは特別な存在になりました。そして、消費者が求める「新しさ」や「驚き」は、必ずしも伝統的な技術や基準とは違うところにあるのかもしれない、ということを多くの人に気づかせたのです。