パート・ド・フリュイとは|果物に含まれたペクチンの働き
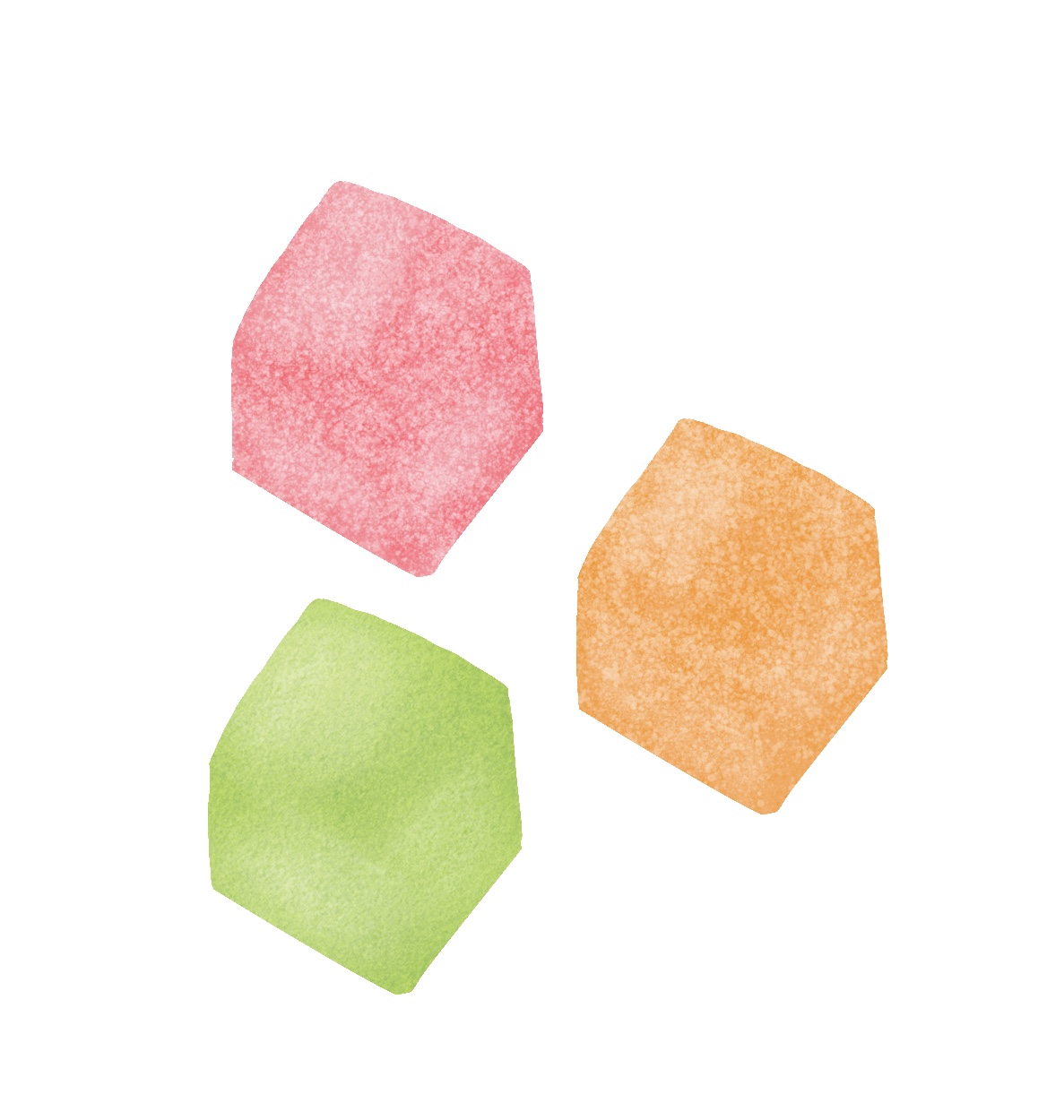
パート・ド・フリュイとは何か
パート・ド・フリュイは、フランス語で「果実のペースト」を意味する言葉です。
一口サイズの四角や丸い形をした、ゼリー状の小さな菓子で、見た目はグミのような食感を持っています。
パート・ド・フリュイが一般的なゼリーやグミと大きく違う点は、その製法にあります。
私たちが普段食べているゼリーはゼラチンや寒天で固めますが、この菓子はそれらを一切使用しません。
代わりに、果実そのものに含まれている「ペクチン」という天然の成分を利用して固めます。
ペクチンの働き
ペクチンは果物の細胞壁にある天然の多糖類という物質で、特に果物の皮や芯に多く含まれています。
たとえば、りんごでジャムを作るとき、砂糖と一緒に煮詰めると自然にとろみがつくのは、このペクチンの働きによるものです。
ペクチンは、適切な量の砂糖と酸がある環境で加熱されると、分子同士が結合してゲル状の網目構造を作り出します。
パート・ド・フリュイの味わい
パート・ド・フリュイは、果物の風味が凝縮されていることが特徴です。
製造過程で水分を飛ばすため、生の果物よりもはるかに濃厚な果実味が楽しめます。
砂糖の甘さと果物の自然な酸味のバランスが良く、後味はさっぱりしています。
食感は、外側が少し固く、内側がしっとりとしており、噛むごとに果実の風味が口の中に広がります。
パート・ド・フリュイの作り方
ピューレの用意
まず、選んだ果物をすりつぶしてピューレ、つまり果肉をペースト状にしたものを作ります。
煮詰める工程
このピューレに砂糖を加えて鍋で煮詰めていきます。
煮詰める過程で水分が蒸発し、果汁が濃縮されていきます。
同時に、果物に含まれるペクチンが砂糖や果物の酸と反応して、徐々に固まっていきます。
常温でも溶けない
この製法により、パート・ド・フリュイは常温でも溶けない特性を持っています。
ゼラチンを使ったゼリーは温度が上がると溶けてしまいますが、ペクチンで固めたこの菓子は夏場でも形を保つことができるのです。
この特性が、後に述べる歴史や用途と深く関わっています。
グラニュー糖をまぶす
完成したパート・ド・フリュイは、通常、表面にグラニュー糖をまぶして仕上げます。
これにはいくつかの理由があります。
まず、見た目を美しくする装飾的な効果があります。
砂糖の結晶が光を反射して、宝石のような輝きを生み出します。
また、表面の砂糖は水分の出入りを調整して保存性を高めます。
さらに、食べる際にシャリッとした食感のアクセントが加わり、その後にしっとりとした果肉の風味が楽しめます。
パート・ド・フリュイの保存方法
適切に作られたパート・ド・フリュイは、常温で数か月間保存が可能です。
ただし、湿度の高い環境では砂糖が溶けたり、カビが発生したりすることがあります。
そのため、乾燥した涼しい場所で保管することが推奨されます。
直射日光は色あせの原因になるため、暗い場所での保存が適しています。
パート・ド・フリュイに使用する果物
パート・ド・フリュイに使用される果物の種類は非常に多様です。
伝統的なリンゴやアプリコットに加えて、現代ではベリー系、柑橘系、トロピカルフルーツなど、さまざまな果物が使用されています。
ペクチン含有量の違い
これらの果物の選択は、ペクチンの含有量も考慮されます。
リンゴや柑橘類はペクチンを多く含むため、天然のペクチンだけでも固まりやすく、初心者にも作りやすい果物です。
一方、イチゴやマンゴーなどはペクチン含有量が少ないため、市販のペクチンを追加する必要があります。
フランスにおけるパート・ド・フリュイの立ち位置
現代のフランスにおいて、パート・ド・フリュイはコンフィズリー(砂糖菓子)の代表的な存在です。
コンフィズリーは、砂糖を主原料とした菓子の総称で、キャンディやヌガー、プラリーヌなども含まれます。
パティスリー(洋菓子店)では定番商品として扱われており、ショコラティエ(チョコレート専門店)でもチョコレートと並んで販売されています。
特に贈り物として、美しい箱に色とりどりのパート・ド・フリュイが整然と並べられた商品は、フランスの菓子店では日常的な光景です。
個包装されることも多く、衛生的で分けやすいという実用的な利便性もあります。
パート・ド・フリュイの歴史
パート・ド・フリュイの歴史は、10世紀のフランス中央部にあるオーヴェルニュ地域圏まで遡ります。
誕生の背景
当時のオーヴェルニュは農業が盛んで、特にリンゴやアプリコットが多く栽培されていました。
冷蔵技術のない時代、収穫した果物をそのまま保存することは困難でした。
そこで人々は、果物に大量の砂糖を加えて煮詰め、水分を飛ばして濃縮することで、長期保存を可能にしたのです。
砂糖が防腐剤の役割を果たすため、適切に作られたパート・ド・フリュイは数か月から1年程度の保存が可能でした。
これは、収穫期を過ぎても果物の風味と栄養を楽しめる方法でした。
呼び名の変遷
初期の頃、この菓子は「confitures sèches」、つまり「ドライ・コンフィチュール」と呼ばれていました。
コンフィチュールとは現在で言うジャムのことで、それをより固く乾燥させた状態という意味です。
砂糖が非常に高価だった時代、大量の砂糖を使うこの菓子は贅沢品として、地元の権力者や裕福な人々に珍重されました。
やがて、「les pâtes d’Auvergne」、つまり「パート・ド・オーヴェルニュ」と呼ばれるようになります。
その優れた携帯性と保存性により、商人や旅人によって各地に運ばれ、まず南フランス地域に広がり、やがてパリにも伝わりました。
パリの宮廷でも評判となり、フランス全土に普及していきました。
市販ペクチンの種類
現代では、天然のペクチンだけでなく、市販のペクチンパウダーを使用することも一般的です。市販のペクチンには、主に**「HMペクチン」と「LMペクチン」**の2種類があります。
HMペクチン
HMペクチンの「HM」は「High Methoxyl(高メトキシル基)」の略です。このペクチンは、固まるために高い糖度(全体の55~80%)と強い酸性度(pH2.5以下)を必要とします。パート・ド・フリュイのように、甘くて酸味のある菓子を作るのに適しています。
LMペクチン
一方、LMペクチンの「LM」は「Low Methoxyl(低メトキシル基)」の略です。このペクチンは、糖分や酸をそれほど必要とせず、代わりにカルシウムなどのミネラル分と反応して固まります。糖度の低いジャムや、菓子の表面に塗るナパージュ(透明なゼリー状のコーティング)などに使われます。パート・ド・フリュイを作る際には、必ずHMペクチンを使用します。LMペクチンでは、必要な糖度と酸度がないため、適切な食感のものが作れません。
HMペクチンの使い方
HMペクチンを使う際にはいくつかの注意点があります。
ペクチンは水分と直接混ざるとダマになりやすいので、使用する砂糖の一部とあらかじめよく混ぜておく必要があります。それを果汁に少しずつ加えながら溶かしていきます。
また、HMペクチンは酸を加えるとすぐに固まり始める性質があります。そのため、レモン汁やクエン酸などの酸は最後の工程で加え、素早く混ぜて型に流し込む必要があります。この作業が遅れると、鍋の中で固まってしまい、なめらかな仕上がりになりません。
まとめ
パート・ド・フリュイは、単なる菓子を超え、フランスの食文化と歴史を体現した伝統的な食品です。
その製法に込められた先人の知恵と工夫、そして時代を超えて受け継がれてきた味わいは、フランスの食文化遺産の一つと言えるでしょう。





