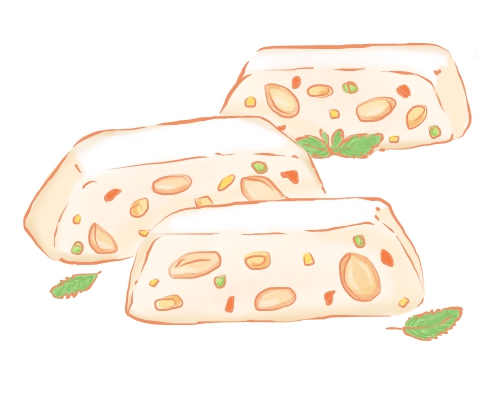チョコレート専門店市場|2024年の動向、2025年以降の見通し

調査概要
株式会社富士経済は2025年10月10日、国内のパン・スイーツ市場に関する包括的な調査結果を「パン&スイーツ市場の全貌・課題分析 2025」として発表しました。本記事は、この調査結果の中からチョコレート専門店市場に関する情報を抽出し、その動向と今後の戦略について分析したものです。
チョコレート専門店市場とは
市場の定義
チョコレート専門店市場には、路面店として営業する専門店だけでなく、百貨店で販売される商品も含まれます。街角に佇む小さな専門店も、百貨店の華やかな売り場に並ぶ商品も、すべてこの市場の一部なのです。
市場規模
| 年 | 市場規模 | 成長率 |
|---|---|---|
| 2026年予測 | 1,001億円 | 2024年比8.5%増 |
2026年には1,001億円に達する見込みです。1,000億円という大台の突破は、チョコレート専門店が日本の消費者にとって定着したことを示しています。原料価格が跳ね上がるという厳しい環境の中で、これだけの成長率を保っているのは、市場の底堅さを物語っています。
チョコレート専門店市場の特徴
多くのチョコレート専門店は、百貨店の地下食品売り場や催事場に出店しています。百貨店という場所が持つブランド力や集客力は、チョコレート専門店にとって大きな味方です。百貨店を訪れる人々は、ある程度の購買力を持ち、品質を大切にする傾向があります。そのため、チョコレート専門店の商品と、そこを訪れる顧客の志向が見事に合うのです。
しかし、この百貨店依存という特徴は、両刃の剣でもあります。百貨店の営業がうまくいかなければ、そこに出店しているチョコレート専門店も直接的に影響を受けてしまうのです。この関係性の脆さは、2020年に訪れた試練の中で、はっきりと姿を現すことになります。
チョコレート専門店市場の変遷
市場の縮小(2020年)
| 縮小要因 | 具体的な影響 |
|---|---|
| 店舗休業 | 百貨店の臨時休業・営業時間短縮・入場制限により販売機会が減少 |
| ギフト需要の低下 | 外出自粛により手土産需要が減少、企業の贈答需要も減少 |
2020年は、新型コロナウイルス感染症の流行により、市場は大きく縮小しました。この年、チョコレート専門店を取り巻く環境は一変したのです。
百貨店休業の影響
緊急事態宣言の発令により、多くの百貨店が臨時休業を余儀なくされました。百貨店が営業を停止すれば、そこに出店しているチョコレート専門店も営業できません。主要な販売チャネルが突然閉ざされたことで、売上は一気に落ち込みました。営業を再開した後も、短縮営業や入場制限により、従来のような販売はできない状態が続いたのです。
贈答需要の減少
外出自粛により、友人や知人に会う機会が激減しました。手土産としてチョコレートを購入する理由が失われてしまったのです。また、企業の贈答需要も減少しました。取引先への訪問が控えられ、季節の挨拶なども簡素化される中で、贈答品としてのチョコレートの出番は少なくなっていきました。
回復への道のり
| 回復要因 | 内容 |
|---|---|
| 人流の回復 | 緊急事態宣言解除後、百貨店の営業正常化により来店客が戻る |
| 自家需要の増加 | 贈答用から自分で楽しむための購入へと需要構造が変化 |
2021年以降、市場は徐々に回復へと向かいました。そこには二つの力が働いていたのです。
百貨店営業の正常化
緊急事態宣言が解除され、百貨店の営業が正常化するにつれて、来店客も少しずつ戻り始めました。長い自粛生活の中で、人々は外出して買い物をする楽しみを改めて感じるようになっていました。百貨店という非日常的な空間で、ゆっくりと商品を選ぶ体験が、新鮮な喜びとして感じられたのです。
自家需要の増加
市場回復のもう一つの原動力となったのは、自家需要の増加です。従来、チョコレート専門店の商品は、誰かに贈るものという位置づけが強くありました。しかし、コロナ禍を経て、自分で楽しむためにチョコレートを購入する人が増えたのです。外出を控える中で、自宅で味わえる小さな贅沢として、チョコレートが選ばれるようになりました。
この需要構造の変化は、市場に新しい安定性をもたらしました。贈答需要は季節やイベントに左右されやすく、波があります。一方で、自家需要は年間を通じて比較的安定しています。この変化により、市場は以前よりも安定した基盤を得ることになったのです。
チョコレート専門店市場の2024年の動向
バレンタインデーの変化
| 需要タイプ | 特徴 |
|---|---|
| カジュアルギフト | 手頃な価格で気軽に贈れるギフト、友人同士や日頃の感謝を伝える用途 |
| 自家需要 | 自分へのご褒美や家族と楽しむための購入 |
2024年のチョコレート専門店市場では、バレンタインデーを中心とした需要が市場を力強く牽引しました。ただし、そのバレンタインの様相は、かつてのものとは様変わりしています。
カジュアルギフトの拡大
昔のバレンタインデーは、本命チョコレートと義理チョコレートという、はっきりとした区分で語られることが多くありました。しかし、近年はカジュアルギフトという新しい波が生まれています。これは、高価な贈り物ではなく、気軽に手渡せるギフトのことです。友人同士で交換し合ったり、日頃お世話になっている人に感謝の気持ちを伝えたりする際に、気負わずに選べる商品なのです。
このカジュアルギフト需要の広がりは、市場の裾野を着実に広げています。以前のように特定の誰かにだけ贈るのではなく、何人かに配る形での購入が増えているのです。その結果、一人あたりが買う個数が増え、市場全体が膨らんでいきました。
自家需要の定着
バレンタインデーにおける自家需要も、すっかり定着しました。自分へのご褒美として、あるいは家族と一緒に楽しむために、バレンタインのチョコレートを購入する人が増えています。この動きは、バレンタインデーを「誰かに贈る日」から「チョコレートを楽しむ日」へと静かに作り変えています。
自家需要の増加により、バレンタイン商戦の期間も長くなる傾向にあります。以前は2月14日直前に集中していた購入が、今では1月下旬から2月中旬にかけて分散するようになりました。急いで買う必要がないため、自分のペースでゆっくりと選べるようになったのです。
価格改定による単価上昇
| 価格上昇の要因 | 詳細 |
|---|---|
| カカオ豆価格の高騰 | 気候変動による生産地の不作、主要生産国の政情不安 |
| 為替の影響 | 円安進行による輸入コストの上昇 |
2024年の市場拡大には、価格改定による単価の上昇も寄与しました。
カカオ豆の国際価格が高騰
カカオ豆の国際価格が高騰しました。気候変動による生産地の不作や、主要生産国の政情不安が重なり、原料価格は上がり続けています。さらに円安が進行する中で、輸入コストも跳ね上がりました。原料価格の高騰と為替の悪化という二つの波が同時に押し寄せ、チョコレート専門店は価格を改定せざるを得なくなったのです。
需要は落ち込まなかった
興味深いのは、価格が上がったにもかかわらず、需要が落ち込まなかったことです。消費者は値上がりを受け入れ、チョコレートを買い続けました。これは、チョコレート専門店の商品が、消費者にとって値段以上の価値を持っていることを示しています。品質の高さ、ブランドへの信頼、特別な時間を演出してくれる存在としての価値。そうした要素が、値上がり分を補って余りあったのです。その結果、単価の上昇が市場規模の拡大につながるという、一見矛盾した現象が起きました。
チョコレート専門店市場の2025年以降の課題
カカオ豆価格の高止まり
| 課題 | 影響 |
|---|---|
| 原料価格の高止まり | 企業の収益性を圧迫 |
| 夏場の長期化 | チョコレートは暑さに弱く、気温が高い時期の需要が減退 |
2025年に入っても、カカオ豆価格は高い水準のままです。短期的に価格が下がる見込みは薄く、この状況はしばらく続くと見られています。
収益性への圧迫
原料価格の高止まりは、企業の収益を少しずつ削っていきます。価格改定により消費者に負担してもらう形で対応していますが、それにも限界があるのです。あまりに高い価格を付けてしまえば、顧客が離れていってしまうかもしれません。企業は、上がり続ける原料コストと、消費者がどこまで許容してくれるかの間で、難しい判断を迫られています。
季節要因の影響
気候変動により、夏の暑さが長引く傾向にあります。チョコレートは暑さに弱い商品であり、気温が高い時期には売れ行きが鈍ります。夏が長引けば、それだけ売上が伸び悩む期間も延びるわけです。この季節要因は、一年を通じて安定した売上を確保することを難しくしています。
商品開発による適応
こうした課題に対して、チョコレート専門店は商品開発という手段で立ち向かおうとしています。参入各社が力を入れているのが、焼き菓子と半生菓子の開発です。
これらの商品開発により、チョコレート専門店の商品棚は豊かになっています。従来の生チョコレートやトリュフといった定番に加えて、焼き菓子や半生菓子という新しい選択肢が並ぶようになりました。顧客は、その日の気分や用途に応じて、様々な商品から選べるようになったのです。
焼き菓子の特徴
焼き菓子は、生チョコレートやトリュフに比べて、カカオの使用量を抑えられます。小麦粉やバターといった他の材料の比率を高めることで、カカオ豆価格の上昇による影響を和らげられるのです。
焼き菓子には、もう一つ見逃せない利点があります。それは日持ちすることです。生チョコレートは賞味期限が短く、いつ売れるかわからない中で在庫を抱えるのは難しいものです。一方、焼き菓子は比較的長く保存できます。これは販売の柔軟性を高め、売れ残って捨てるという無駄も減らせます。
半生菓子の特徴
半生菓子は、生菓子と焼き菓子の中間のような水分量を持つ菓子です。ガトーショコラやブラウニーなどが該当します。半生菓子の魅力は、しっとりとした食感にあります。チョコレートの風味を楽しみながらも、カカオの量を調整しやすいという利点を持っているのです。
ただし、カカオの量を減らした商品開発には、気をつけなければならない点もあります。あまりにカカオの比率を下げすぎると、チョコレート専門店としての存在意義が揺らいでしまう恐れがあるのです。顧客は、チョコレート専門店に対して、チョコレートならではの深い味わいを期待しています。その期待を裏切らないよう、カカオの量を抑えつつも、しっかりとチョコレートの風味が感じられる商品作りが求められています。
チョコレート専門店市場の2025年以降の見通し
原料価格の高騰が続く中で、将来を見据えた視点も欠かせません。
短期的な市場拡大は続く
短期的に見れば、市場の拡大は続くと予測されています。需要の底堅さと、企業の商品開発の努力により、2026年には1,000億円の大台を突破する見込みです。チョコレート専門店への消費者の支持は根強く、多少の値上がりでは揺らがない層が確実に存在します。また、自家需要が増えたという構造変化により、市場の安定性は以前より高まっています。
消費者の需要を守れるか
ただし、価格改定が繰り返されれば、いずれ消費者の我慢も限界に達するかもしれません。その時、需要が減り、売上が落ち込むことになります。収益が悪化すれば、企業はこの事業にかける力を弱めるかもしれません。新商品を開発するための投資を減らしたり、店舗を増やす計画を見直したりする動きが出てくる可能性があります。最悪の場合、事業から手を引く判断をする企業も現れるかもしれません。
企業の対応策
企業側も、ただ値段を上げるだけで済ませようとはしていません。商品の価値を高める努力を重ねているのです。新しい味の開発、パッケージを見直して魅力を増すこと、店舗での体験をより良いものにすることなど、様々な工夫を凝らしています。こうした取り組みにより、顧客の満足度を保ち続けようとしているのです。
まとめ
チョコレート専門店市場は2026年に1,001億円に達し、2024年比で8.5%増と予測されています。1,000億円という大台の突破は、チョコレート専門店が日本の消費者の生活に根付いたことを示しています。
市場は2020年のコロナ禍で大きく縮小しましたが、その後は人の流れが戻り、自分で楽しむための購入が増えたことで回復しました。2024年はバレンタインデーを中心に、気軽に贈れるカジュアルギフトと自家需要が市場を牽引しました。また、カカオ豆価格の高騰と円安による価格改定で商品の値段は上がりましたが、需要は落ちることなく堅調を維持しました。
2025年以降は、カカオ豆価格が高いまま推移することと、暑い夏が長引くことが課題となっています。これに対して企業は、焼き菓子や半生菓子といった、カカオの使用量を抑えた商品の開発に力を入れています。原料価格の高騰が続けば企業の意欲が下がる可能性もありますが、短期的には需要の強さと商品開発の工夫により、市場は成長を続ける見込みです。
チョコレート専門店市場の今後は、原料価格がどう動くか、企業がどこまで対応できるか、そして消費者の支持がどこまで続くかにかかっています。