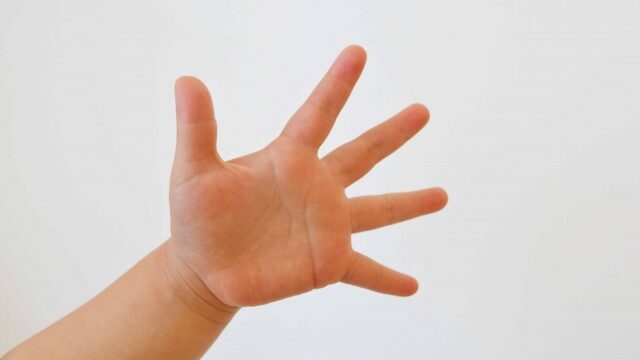飴の発祥起源とは|日本書紀から記される食の歴史
飴の起源を辿ると、その歴史は想像以上に古く、日本の文字記録の黎明期にまで遡ることができます。現在私たちが知っている飴とは製法も原料も大きく異なりますが、甘味への憧れと技術の発展は、古代の人々にとっても重要な関心事だったようです。
日本最古の歴史書に登場する「神秘の飴」
日本最古の正史である『日本書紀』は720年に完成しましたが、この中に既に飴に関する興味深い記述が見つかります。
『日本書紀』の第二巻には、初代天皇とされる神武天皇の時代(紀元前7世紀頃と伝えられる)の出来事として、飴作りにまつわる神秘的な逸話が記されています。
神武天皇の東征において、丹生川(にゅうがわ)のほとりで神を祀る重要な儀式の最中に、次のような言葉が語られました。
「吾(われ)今(いま)、当(まさ)に八十平釜(やそひらがま)を以(もっ)て、水(みず)無くして離(あめ)を造(つく)らん。飴成(あめな)らば則(すなわ)ち吾(われ)必ず鋒刃(ほうじん)の威(い)を仮(か)らずして天下(あめがした)を平(たいら)げん。乃(すなわ)ち飴を造(つく)る。飴即(あめすなわ)ち自(おのずか)ら成(な)る。」
この古代の文章を現代語に訳すと「私は今、多数の平瓦を使い、水を使わずに飴を作ってみよう。もし飴ができたなら、武力を使わずとも天下を平定することができるだろう。さあ、飴を作ろう。そして、それが成功したなら自らの成功も確実となるだろう」という意味になります。
この記述が示すのは、古代においても飴作りが単なる食品製造ではなく、何か特別な意味を持つ行為として捉えられていたということです。飴が成功すれば天下統一も成功するという発想は、甘味の希少性と製造技術の困難さを物語っています。当時の人々にとって、甘いものを作り出すことは、まさに奇跡的な技術だったのでしょう。
古代の「飴」ってどんなもの?
しかし、この時代の「飴」が具体的にどのようなものだったかについては、多くの謎が残されています。現代の私たちが想像するような透明で硬い飴玉とは、おそらく全く異なる代物だったと考えられます。
米を原料とした「水飴」のような甘味料
この疑問を解く手がかりとなるのが、平安時代前期(934年頃)に編纂された『倭名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)』という辞書的な書物です。
ここには「飴は米蔵を煎じて作るもの」と記されており、米を主原料として作られていた可能性が高いことが分かります。
「米蔵」という表現が何を指すかは議論の余地がありますが、米やその加工品を煎じて甘味を抽出していたことは確実のようです。
この記述から推測すると、古代の飴は現在のような精製された砂糖で作られたものではなく、米の澱粉を何らかの方法で糖化させて作った、どちらかといえば水飴のような粘性のある甘味料だったと考えられます。
「米飴」の製造工程
古代の飴作りについてより詳しい情報を提供してくれるのが、平安時代中期(927年)に編纂された『延喜式(えんぎしき)』です。この書物は、当時の朝廷における様々な儀式や制度を詳細に記録したもので、その中に飴の製法についても具体的な記述が残されています。
『延喜式』によると、当時の飴作りは非常に手間のかかる複雑な工程を経て行われていました。
- もち米やうるち米を砕いて煮詰める:
現代のように精米技術が発達していない時代ですから、この工程だけでも相当な労力を要したことでしょう。 - 麦芽を加える:
これは現代の醸造技術にも通じる重要な過程で、麦芽に含まれる酵素の働きによって米の澱粉を糖に変える、いわゆる糖化の過程です。この技術的な発見は、古代の人々の観察力と実験精神の賜物であり、現代の我々から見ても驚くべき科学的な発見だったといえます。 - 冷湯を加えて糖化を進める、4. 煮沸して布で濾す:
この一連の作業は、現代の食品加工技術の原型ともいえる精密さを要求するものでした。布で濾すという工程は、不純物を取り除いて純度の高い甘味料を得るための重要な技術で、当時の職人の技術水準の高さを物語っています。
完成した飴は、現代の水飴に近い粘性のある甘味料で、蜂蜜のような黄金色をしていたと推測されます。
「米」が主役だった古代日本の甘味文化
現代の飴が主にサトウキビやテンサイ(砂糖大根)から作られた砂糖を原料としているのに対し、古代日本の飴が米を原料としていたことは、日本の食文化における米の圧倒的な重要性を示しています。
米は古代日本において、単なる主食以上の意味を持っていました。それは生命の源であり、豊穣の象徴であり、神聖な作物でした。その米から甘味を作り出すということは、まさに米の神秘的な力を最大限に引き出す行為として認識されていたのでしょう。
独自の甘味文化を築いた「米飴」
また、米を原料とした飴作りは、日本独自の技術発展の道筋を示しています。砂糖が日本に本格的に伝来するのは奈良時代以降のことで、それまでは蜂蜜や果実などの天然の甘味料に頼るか、このような米からの甘味抽出技術に依存していました。つまり、米飴の技術は、外来の砂糖に頼らない独自の甘味文化の基盤を形成していたのです。
古代の「飴」が持つ社会的意義
権力と富の象徴だった「飴」
『日本書紀』の記述が示すように、飴作りは単なる食品製造ではなく、政治的、宗教的な意味を持つ重要な行為でした。甘味が希少だった時代において、飴を作ることができる技術は、権力と富の象徴でもありました。複雑な製造工程と長時間の作業を要する飴作りは、相当な人的資源と物的資源を投入できる支配層でなければ実現できない贅沢品の製造だったのです。
秘匿され、継承された「職人の技」
さらに、飴作りに関連する技術や知識は、おそらく特定の職人集団や宗教的な組織によって秘匿され、継承されていたと考えられます。これは、古代社会における技術の伝承システムの一端を示すものでもあります。技術の独占は権力の独占でもあり、飴作りの技術を持つ者は、社会的に特別な地位を占めていたと推測されます。
まとめ
このように、古代の飴は現代の私たちが気軽に楽しむお菓子とは全く異なる、深い文化的意義を持つ特別な存在だったのです。米から甘味を作り出す技術の発達は、日本の食文化の独自性を示すと同時に、古代人の知恵と技術力の高さを現代に伝える貴重な証拠となっています。神武天皇の時代から平安時代にかけて育まれた飴の文化は、その後の日本の菓子文化の発展に大きな影響を与え、現在に至るまで脈々と受け継がれているのです。