和菓子市場の調査分析|2024年の動向と2025年以降の見通し
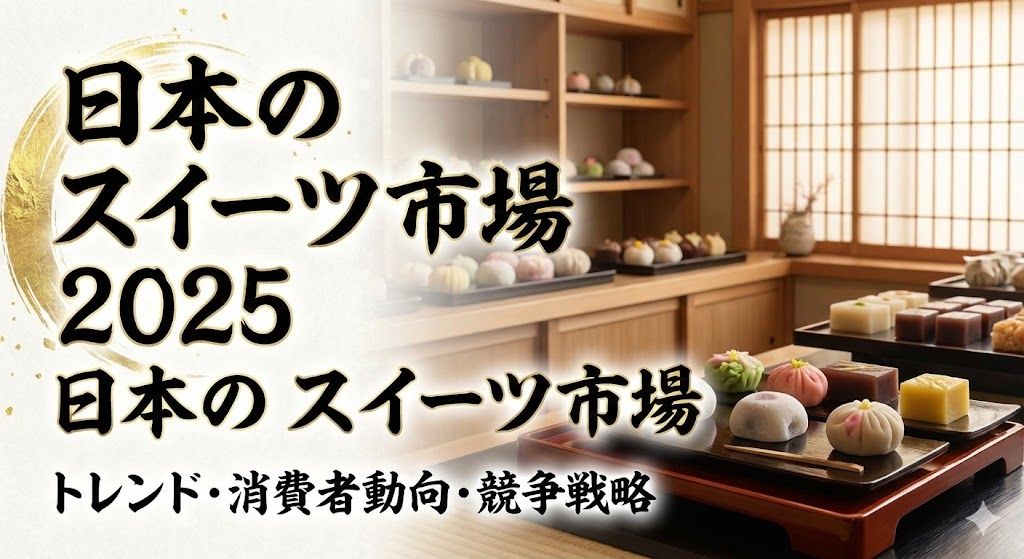
調査概要
株式会社富士経済による市場調査
株式会社富士経済は2025年10月10日、国内のスイーツ市場に関する包括的な調査結果を「パン&スイーツ市場の全貌・課題分析 2025」として発表しました。
この調査では、原料価格の高騰により消費者の価格意識が高まる中で、スイーツ市場がどのように変化しているのかを明らかにしています。調査は製品の種類だけでなく、どこで販売されているかという販売チャネルの視点からも詳細な分析を行っており、市場の実態を多角的に捉えています。
スイーツ市場は洋菓子と和菓子に大別されますが、本記事では和菓子市場に焦点を当てて、その動向と今後の見通しについて考察していきます。
調査の対象範囲
| 製品種類別 | ドライ和菓子 | ようかん、まんじゅう、大福・団子、最中、どら焼き、カステラ、あんみつ、鯛焼・今川焼 |
|---|---|---|
| チルド和菓子 | 冷蔵保存が必要な和菓子、カップ入り和菓子 | |
| 販売チャネル別 | 和菓子店 | 専門店としての和菓子店 |
| 流通和菓子 | 量販店、コンビニエンスストア、ドラッグストア | |
| 外食 | 回転ずし、ファミリーレストランなど |
和菓子は製品の保存形態によって、ドライ和菓子とチルド和菓子に分類されます。
ドライ和菓子は常温で保存できる商品であり、チルド和菓子は冷蔵保存が必要な商品です。この保存形態の違いは、賞味期限の長さや流通形態、そして消費者の購買行動に大きく影響を与えます。
販売形態の視点では、専門店としての和菓子店、量販店やコンビニエンスストアで販売される流通和菓子、そして外食店で提供される和菓子という三つのチャネルに分けて分析されています。
和菓子市場の全体構造
製品種類別の構成
| 製品分類 | 主な特性 | 主要商品 |
|---|---|---|
| ドライ和菓子 | 常温保存が可能、日持ちが長い、贈答用途が多い | ようかん、まんじゅう、大福・団子、最中、どら焼き、カステラ |
| チルド和菓子 | 冷蔵保存が必要、新しい食感や風味を実現 | 冷蔵保存が必要な和菓子、カップ入り和菓子 |
ドライ和菓子
| 主な品目 | 特徴 |
|---|---|
| ようかん | 砂糖と小豆を煮詰めて固めた菓子、賞味期限が長い |
| まんじゅう | 小麦粉や米粉の生地であんこを包んだ菓子、地域ごとに特色がある |
| 大福・団子 | 餅を使った菓子、柔らかな食感 |
| 最中 | 薄く焼いた餅皮であんこを挟んだ菓子、パリッとした食感 |
| どら焼き | カステラ生地であんこを挟んだ菓子 |
| カステラ | 長崎を発祥とする焼き菓子 |
| あんみつ | 寒天やフルーツ、あんこを組み合わせた菓子 |
| 鯛焼・今川焼 | 生地であんこを包んで焼き上げた菓子 |
これらの和菓子を特徴づけているのは、米や小豆といった日本で古くから親しまれてきた素材の使用です。小豆を煮詰めて作られるあんこは、和菓子の基本となる材料であり、控えめな甘さと素材本来の風味が調和しています。
季節ごとに旬の素材を取り入れることも、和菓子の文化的な側面です。春には桜餅や草餅、夏には水ようかんや葛餅、秋には栗を使った菓子、冬にはゆず風味の商品といった具合に、四季の移ろいを味覚で感じられるようになっています。
チルド和菓子
チルド和菓子は冷蔵保存が必要な和菓子やカップ入り和菓子を指します。伝統的な和菓子は常温保存が基本でしたが、現代の技術により冷蔵保存することで新しい食感や風味を実現した商品が生まれています。
カップ入り和菓子は、透明な容器に寒天や白玉、フルーツなどを盛り付けた商品です。見た目の美しさと食べやすさを両立しており、コンビニエンスストアや量販店で手軽に購入できます。スプーンで食べられる手軽さは、若い世代にも受け入れられやすい要素となっています。
伝統を守りながらも、新しい技術を取り入れることで、和菓子は進化を続けているのです。冷蔵技術の発達により、従来は難しかった食感や風味の表現が可能になり、和菓子の可能性が広がっています。
販売チャネル別の構成
| 販売チャネル | 提供価値 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 和菓子店 | 商品の質、伝統の継承、職人の技術 | 専門店としての品揃え、地域密着、贈答対応 |
| 流通和菓子 | 価格優位性、入手の容易さ | 日常的な購入機会、手頃な価格設定 |
| 外食 | 食事との組み合わせ | デザートメニューとしての提供 |
和菓子の販売チャネルを見ると、和菓子店という専門店での販売と、量販店やコンビニエンスストアでの流通販売、そして外食店での提供という三つの形態が存在します。それぞれのチャネルは異なる強みを持ち、異なる顧客層にアプローチしています。
和菓子店
| 和菓子店の特徴 | 内容 |
|---|---|
| 製法 | 伝統的な製法を守りつつ、現代の嗜好に合わせた商品開発 |
| 店舗形態 | 百貨店内店舗、観光地店舗、地域密着型店舗 |
| 提供価値 | 職人の技術、商品の質、贈答対応 |
和菓子店は伝統的な製法を守りながら、現代の嗜好に合わせた商品開発も行っています。基本的な製法や味わいは維持しつつ、見た目を現代風にアレンジしたり、新しいフレーバーを加えたりすることで、幅広い世代に受け入れられる商品が生まれています。
- 店内で製造している和菓子店
職人の技術を直接見ることができることもあります。餅をつく音、あんこを炊く香り、こうした五感で感じられる要素が、和菓子店ならではの魅力となっています。商品を選ぶ際に店員と会話をしながら、用途や予算に応じた提案を受けられることも、専門店の強みです。
- 観光地や行楽地に店舗を構える和菓子店
地域の特産品を使った商品や、その土地でしか買えない限定商品を提供することで、観光客の需要を取り込んでいます。包装にも地域性が表れており、パッケージを見ただけでどこの土産物かがわかるようなデザインが施されています。
- 百貨店に店舗を構える和菓子店
贈答需要に特化した品揃えを行っています。お中元やお歳暮、お祝い事や弔事といった正式な贈答の場面では、百貨店という場所が持つ信頼感が重要な意味を持ちます。
流通和菓子
流通和菓子は量販店、コンビニエンスストア、ドラッグストアで販売される商品です。これらの販路では、工場で大量生産された商品が陳列されており、価格優位性と入手の容易さが強みとなっています。
- 量販店
多様な商品が並び、まとめ買いも可能です。家族向けの複数個入りのパック商品が充実しており、日常的な消費に適しています。和菓子売り場には、どら焼き、まんじゅう、カステラといった定番商品が常時並んでおり、食後のデザートや子どものおやつとして購入されます。
- コンビニエンスストア
単身世帯や少人数世帯に向けた個食サイズの商品が中心です。仕事帰りや夜遅い時間でも購入できる利便性があり、急な来客時の手土産や、自分へのご褒美として選ばれています。近年では、コンビニエンスストアの和菓子は品質が向上しており、専門店に近い味わいを手頃な価格で楽しめるようになっています。
- ドラッグストア
価格競争力を活かした低価格商品が並びます。日用品の購入ついでに和菓子も買うという購買行動が見られ、計画的な買い物よりも衝動買いが起きやすい環境となっています。洗剤やシャンプーを買いに来たついでに、レジ前に並んでいる和菓子を手に取るという行動は、多くの人が経験しているでしょう。
外食
外食チャネルでは、回転ずしやファミリーレストランが和菓子を提供しています。これらの業態では、食事のあとのデザートとして和菓子が位置づけられています。
回転ずしでは、寿司という和食を食べた後に、口直しとして和菓子が選ばれることがあります。わらび餅やあんみつといった商品は、寿司の塩気の後に甘さを楽しむデザートとして適しています。子ども連れの家族では、食事の締めくくりとして和菓子を注文することで、子どもにも満足感を与えられます。
ファミリーレストランでは、和風デザートとして和菓子が提供されています。抹茶アイスと組み合わせたあんみつや、白玉ぜんざいといったメニューは、洋食を食べた後でも楽しめる和のデザートとして人気があります。
和菓子市場の2024年の動向
コロナ禍からの回復
| 時期 | 市場規模 | 状況 |
|---|---|---|
| 2020年 | 4,000億円未満 | 新型コロナウイルス感染症の影響で市場縮小 |
| 2022年 | 4,000億円台 | 百貨店内店舗を中心に回復 |
| 2024年 | 拡大継続 | コロナ禍前の水準に近い状態まで回復 |
和菓子市場は2020年に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて4,000億円を下回りましたが、その後は百貨店内店舗を中心に回復し、2022年に4,000億円台に戻しました。そして2024年も拡大が続いています。この回復の軌跡は、和菓子が日本の文化や習慣に深く根ざした商品であることを改めて示しています。
市場縮小の背景
- 百貨店の休業や営業時間短縮
新型コロナウイルス感染症の流行期間中、百貨店は休業や営業時間の短縮を余儀なくされました。百貨店に店舗を構える和菓子店にとって、これは売上の大幅な減少を意味しました。百貨店は和菓子の主要な販売拠点の一つであり、特に贈答用の高級和菓子は百貨店での販売が中心でした。店舗が営業できなければ、商品を販売することもできません。
- 贈答の機会が減少
贈答の機会そのものが減少したことも市場縮小の要因となりました。結婚式や葬儀といった冠婚葬祭が縮小され、企業間の贈答も控えられたため、和菓子の主要な用途の一つが失われたのです。お中元やお歳暮といった季節の贈答も、感染拡大を避けるために見送られることが多くありました。人と人との物理的な距離が求められる状況では、贈り物を手渡しする機会も減少せざるを得なかったのです。
- 観光需要の消失
観光需要の消失も大きな打撃となりました。観光地の和菓子店は、旅行者への土産物販売が売上の大きな部分を占めています。緊急事態宣言や移動自粛の呼びかけにより、観光客が途絶えたことで、これらの店舗は厳しい経営環境に置かれました。特に観光シーズンに売上が集中する店舗では、その影響は深刻でした。
回復の過程
2022年以降、人々の活動が徐々に正常化し、百貨店の来店客数も回復していきました。営業時間が通常に戻り、催事も再開されたことで、和菓子店は販売機会を取り戻していきました。百貨店の和菓子売り場には、再び贈答品を選ぶ顧客の姿が戻ってきたのです。
贈答の習慣も戻り始めました。結婚式や葬儀が以前の規模で行われるようになり、企業間の贈答も再開されました。お中元やお歳暮といった季節の挨拶も、コロナ禍前の水準に近い状態まで回復しています。人と人とのつながりを大切にする日本の文化は、感染症の影響を受けながらも、根強く残っていたのです。
観光需要も徐々に回復してきました。国内旅行が戻ってきたことに加えて、訪日外国人観光客も増加しています。観光地の和菓子店では、週末や連休に多くの来客で賑わう光景が戻ってきました。和菓子は日本文化を体験できる商品として、外国人観光客にも人気があり、この需要が市場を下支えしています。
2024年には、和菓子市場はコロナ禍前の水準に近い状態まで回復しています。ただし、完全に元通りになったわけではありません。感染症の経験を経て、消費者の行動には変化も見られます。オンラインでの購入が増えたり、個包装の商品が好まれたりといった変化は、今後も続く可能性があります。
贈答需要の高まり
2024年の和菓子市場では、洋菓子と比較して値ごろ感があることから贈答需要が高まりました。原料価格の高騰により洋菓子の価格が上昇する中、和菓子は相対的に手頃な価格で贈答品として選びやすい存在となっています。
価格面での優位性
洋菓子の原料である小麦粉、バター、砂糖、鶏卵といった材料は、国際的な価格上昇の影響を受けやすい特性があります。これらの多くは輸入に依存しているため、為替レートの変動や国際的な需給バランスの変化が、直接的に価格に反映されます。特にバターと鶏卵の価格上昇は、洋菓子の製造コストを大きく押し上げました。
一方、和菓子の主原料である小豆や米は、国産品の使用率が比較的高く、価格の変動が洋菓子ほど激しくありません。もちろん和菓子も砂糖や小麦粉を使用するため、原料価格の影響を全く受けないわけではありませんが、洋菓子と比較すると影響の度合いは小さいのです。この違いが、価格改定の幅の差として表れています。
洋菓子店の詰め合わせは3,000円から5,000円することも珍しくありませんが、和菓子であれば2,000円から3,000円程度で立派な詰め合わせが用意できます。この価格差は、特に複数の相手に贈る必要がある時に大きな意味を持ちます。お中元やお歳暮といった季節の挨拶では、何件もの贈り先があることが多いため、一件あたりの費用を抑えられることは贈る側にとってありがたいのです。
贈る側の経済的な負担が軽減されることは、贈答の習慣を継続しやすくすることにつながります。価格が高騰しすぎると、贈答そのものを見送るという選択も出てきますが、手頃な価格であれば、習慣として続けやすいのです。
贈答文化との結びつき
和菓子は日本の伝統的な贈答文化と結びついています。お中元やお歳暮、手土産として和菓子を選ぶ習慣は古くから続いており、贈る側も受け取る側も安心感があります。形式を重んじる場面では、やはり和菓子という選択が無難であり、かつ失礼がないのです。
包装の丁寧さも、和菓子が贈答品として選ばれる理由の一つです。和菓子店では、商品を美しく包装することに細心の注意を払っています。のし紙の選び方、水引の種類、包装紙の柄といった細部にまで気を配ることで、贈る側の気持ちを形にしています。受け取る側も、丁寧に包装された和菓子を開ける時、贈り主の心遣いを感じることができます。
個包装されていることも、和菓子の実用的な強みです。詰め合わせの中身が一つずつ包装されていれば、受け取った側は家族や職場の同僚と分けやすくなります。大きな菓子を切り分ける必要がないため、配る側の手間も少なくて済みます。この配りやすさは、特に職場への差し入れや、親戚への贈り物として重要な要素となっています。
価格帯も幅広く、1,000円台から5,000円以上まで、予算に応じて選べます。職場への差し入れには手頃な価格帯の商品を、目上の方への正式な贈答には高級な詰め合わせをといった使い分けが可能です。同じ和菓子という枠組みの中で、状況に応じた商品を選べることが、贈る側の負担を軽減しています。
観光需要の安定化
| 観光需要の特徴 | 内容 |
|---|---|
| 主な顧客 | 国内旅行者、訪日外国人観光客 |
| 購入理由 | 旅の記念、土産物 |
| 商品の特性 | 地域限定商品、その土地ならではの味わい |
観光地や行楽地の店舗を中心に、和菓子店は安定した需要を獲得しました。コロナ禍で途絶えていた観光客の流れが戻り、土産物としての和菓子の購入が回復しています。
観光地店舗の状況
京都の八つ橋、石川の笹団子、広島のもみじ饅頭といった商品は、その地域を象徴する和菓子として認知されており、観光客にとって外せない土産物となっています。
店舗の立地も、観光客の動線を意識したものとなっています。有名な寺社の参道、観光地のメインストリート、駅の構内といった場所に店を構えることで、観光客が自然に立ち寄れるようになっています。
地域限定商品の役割
地域限定商品は、観光需要を取り込む上で重要な役割を果たしています。「ここでしか買えない」という限定性が、購買意欲を高めます。
季節限定の商品も、観光需要を喚起します。桜の季節には桜餅や桜をモチーフにした和菓子が、紅葉の時期には栗や柿を使った和菓子が登場します。観光のシーズンと季節限定商品の時期を合わせることで、「今しか買えない」という限定性がさらに高まります。
訪日外国人観光客も、和菓子の重要な顧客層となっています。和菓子は日本文化を体験できる商品として、外国人観光客に人気があります。見た目の美しさ、繊細な味わい、職人の技術といった要素は、日本文化の象徴として受け止められています。
ようかんの予想外の需要拡大
| ようかんの新しい用途 | 背景 | 効果 |
|---|---|---|
| 非常食・備蓄食料 | 常温で長期保存可能、高カロリー | 災害時の備蓄需要の獲得 |
| 行動食(登山・アウトドア) | 軽量、かさばらない、エネルギー補給に適している | スポーツ愛好家・アウトドア派への需要拡大 |
| SNSでの話題化 | 日持ちと栄養補給の観点での注目 | 幅広い年齢層への認知拡大 |
2024年の和菓子市場において注目すべき現象は、ようかんの需要拡大です。ようかんは日持ちの点や栄養補給に効果的であるとしてSNSなどで話題となり、備蓄需要も獲得して売上増となりました。
備蓄需要の獲得
| 備蓄食料としての特性 | 内容 |
|---|---|
| 保存性 | 常温で長期保存可能、賞味期限が1年以上の商品も多い |
| 利便性 | 開封すればすぐに食べられる、調理不要 |
| 栄養面 | 高カロリー、糖質を素早くエネルギーに変換 |
| 携帯性 | 個包装で持ち運びやすい |
ようかんは常温で長期間保存できます。災害時の備蓄食料として、カロリーが高く糖分を素早く摂取できるようかんは、乾パンやレトルト食品と並んで推奨される食品となっています。
災害時には、電気やガスといったライフラインが停止することがあります。そうした状況では、調理の必要がない食品が重宝されます。また、水分を含んでいるため、水が不足している状況でも飲み込みやすいという利点があります。
小豆に含まれる糖質は、素早くエネルギーに変わります。災害時には体力を消耗することが多く、効率的にエネルギーを補給できる食品が求められます。
メーカー側もこの需要に対応し、備蓄用として訴求する商品を投入しています。賞味期限を長く設定した商品や、カロリー表示を明確にした商品、備蓄に適したパッケージの商品などが開発されています。
行動食としての再評価
| 行動食としての特性 | 内容 |
|---|---|
| 重量 | 軽量でかさばらない |
| エネルギー効率 | 重量あたりのカロリーが高い |
| 温度耐性 | 暑さや寒さでも品質が保たれる |
| 食べやすさ | 個包装で一口サイズ、手を汚さない |
SNSでは、登山やアウトドア活動の際にようかんを携行するという投稿が広がりました。登山やトレイルランニングといったアウトドア活動では、軽量であることが重要です。荷物を少しでも軽くするために、携行する食品は厳選されます。
また、気温の変化にも強いという特性があります。登山では標高によって気温が大きく変わりますが、ようかんは暑さでも寒さでも品質が保たれます。チョコレートのように溶けることもなく、パンのように固くなることもありません。
スポーツ愛好家やアウトドア派の間で、ようかんは手軽なエネルギー源として定着しつつあります。登山用品店でも、行動食のコーナーにようかんが並ぶようになりました。
こうした新しい用途の発見により、ようかんは高齢者向けの伝統的な和菓子というイメージから、幅広い年齢層に支持される実用的な食品へと位置づけが変化しています。メーカー側もこの動きに対応し、個包装で持ち運びやすいサイズのようかんや、スポーツ向けに特化した商品を投入しています。
和菓子市場の2025年の見通し
市場規模の継続的拡大
| 見通し項目 | 内容 |
|---|---|
| 市場規模の動き | 拡大継続 |
| 成長の性質 | 手土産需要と自家需要の安定的な継続 |
2025年の和菓子市場は、拡大が継続する見込みです。2024年に回復基調が明確になった市場は、その勢いを維持しながら成長を続けると予測されています。大きな飛躍というわけではありませんが、着実に需要が積み重なることで、市場規模が拡大する見通しです。
手土産需要の安定
| 手土産の用途 | 内容 |
|---|---|
| 主な場面 | 友人宅訪問、実家帰省、職場での差し入れ |
| 選ばれる理由 | 日本の習慣に適している、受け取る側も慣れている、価格帯が幅広い |
| 価格帯 | 1,000円〜5,000円程度 |
手土産需要は2025年も安定して推移する見込みです。友人宅を訪ねる際や、実家に帰省する際、職場での差し入れといった場面で、和菓子は定番の選択肢となっています。「何も持たずに訪問するのは気が引ける」という日本人の感覚が、この需要を支えているのです。
和菓子は手土産として優れた特性を持っています。日本の伝統的な贈答文化に適しており、受け取る側も慣れています。個包装されている商品が多いため、複数人で分けやすいという実用性もあります。賞味期限もある程度あるため、受け取った側が自分のタイミングで食べられます。
価格帯も幅広く、1,000円から5,000円程度の範囲で、場面に応じた商品を選べます。ちょっとした訪問には1,000円から2,000円程度の商品を、正式な挨拶には3,000円以上の商品をといった使い分けが可能です。この柔軟性が、様々な場面で和菓子が選ばれる理由となっています。
和菓子店では手土産需要を意識した商品構成を取っています。包装にも気を配っており、見栄えの良い箱や袋で提供することで、贈る側の気持ちを形にしています。「これを持っていけば失礼がない」という安心感を提供することが、リピート購入につながっているのです。
自家需要の継続
自分自身や家族のために購入する自家需要も継続する見込みです。日常的なおやつとしての和菓子消費は安定しており、食後のデザートやお茶の時間の楽しみとして定着しています。
自家需要では、手土産ほど包装の見栄えを重視する必要がないため、価格や味わい、日持ちといった実質的な要素を優先する傾向があります。流通和菓子は、この自家需要を主要なターゲットとしており、手頃な価格の商品を充実させています。
量販店では、複数個入りのパック商品が販売されており、家族で分けて食べることを前提とした商品設計により、1人あたりの単価を下げることができます。「今日は家族でゆっくりお茶を楽しもう」という時に、気兼ねなく買える価格設定が大切なのです。
コンビニエンスストアでは、個食サイズの和菓子が充実しています。仕事の合間や、夕食後のデザートとして、一人分だけ購入できる手軽さが評価されています。「ちょっと甘いものが食べたい」という時に、すぐに購入できる利便性が、繰り返し利用されることにつながっています。
商品開発の方向性
季節感の訴求
多くの品目で、季節感を訴求した商品展開が行われる見込みです。
季節感のある商品は、消費者の購買意欲を刺激します。「今しか食べられない」という限定感が、購入を後押しします。また、季節ごとに新しい商品が登場することで、「次はどんな商品が出るのだろう」という期待感も生まれます。
和菓子店では、季節限定商品を前面に出した陳列を行います。店頭のディスプレイを季節に合わせて変えることで、来店客に季節の移ろいを視覚的にも伝えています。
新しい用途への対応
| 新しい用途 | 対応方向 |
|---|---|
| 備蓄食料 | 賞味期限の延長、カロリー表示の明確化 |
| 健康志向 | カロリー・糖質を抑えた商品、栄養価の訴求 |
| 個食ニーズ | 一人分サイズの商品開発 |
| 若年層向け | 見た目の現代風アレンジ、洋菓子要素の融合 |
ようかんの事例が示すように、伝統的な和菓子が新しい用途で再評価される可能性があります。メーカーは、こうした新しいニーズに対応した商品開発を進める見込みです。
健康志向に対応した和菓子も注目されています。小豆には食物繊維やポリフェノールが含まれており、健康面でのメリットがあります。こうした栄養面の価値を訴求することで、健康を気にする消費者層にアピールできます。
個食サイズの商品開発も進んでいます。単身世帯の増加に伴い、一人分だけの和菓子が求められています。
若い世代に向けた商品開発も行われています。伝統的な和菓子は高齢者向けというイメージがありますが、見た目を現代風にアレンジしたり、洋菓子の要素を取り入れたりすることで、若い世代にも受け入れられる商品が生まれています。
まとめ
| 市場構造 | ドライ和菓子が中心、和菓子店での販売が主流 |
|---|---|
| 2024年の動向 | コロナ禍からの回復、贈答需要の高まり、観光需要の安定化、ようかんの新需要獲得 |
| 2025年の見通し | 拡大継続、手土産需要と自家需要の安定、季節感の訴求と新用途への対応 |
和菓子市場は、ドライ和菓子を中心に構成されており、和菓子店という専門店での販売が主流となっています。この構造は、和菓子が伝統的な製法と品質を重視する商品であることを反映しています。
2024年の市場は、コロナ禍から回復し拡大が続きました。百貨店内店舗を中心とした販売の回復、贈答需要の高まり、観光地店舗での安定した需要獲得が、市場の成長を支えました。ようかんは備蓄食料や行動食としての新しい用途を獲得し、予想外の需要拡大を実現しました。この事例は、伝統的な商品が現代的なニーズに応える形で再評価される可能性を示しています。
2025年の見通しとしては、市場の拡大が継続する見込みです。手土産需要は日本の伝統的な習慣に支えられて安定しており、自家需要も日常的なおやつとして定着しています。商品開発の面では、季節感を訴求した商品展開が継続され、備蓄食料や健康志向、個食サイズといった新しい用途への対応も進むと予測されます。
和菓子市場は、伝統を守りながらも、現代の消費者ニーズに柔軟に対応することで、着実な成長を続けています。日本の文化や習慣と深く結びついた和菓子は、時代が変わっても、人々の生活に寄り添い続ける存在であり続けるでしょう。




