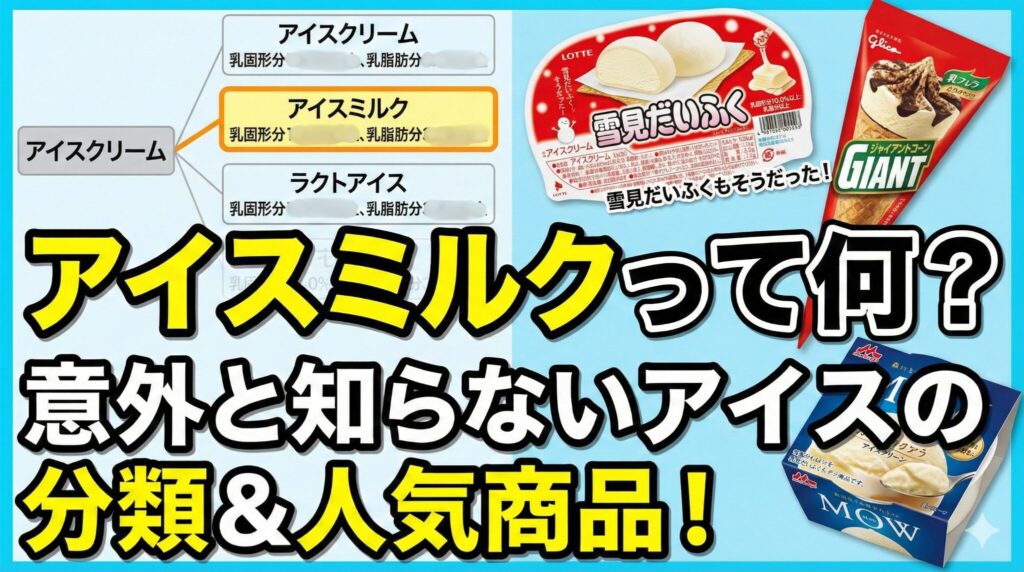加工食品の『内容量』|かんたん説明【食品表示基準】

加工食品の食品表示ルール
内容量とは?【食品表示における意味】
内容量(ないようりょう)とは、「その食品にどれだけ入っているか」を示す情報です。
重さ・体積・個数などで表されており、パッケージに必ず記載されています。
内容量を知るメリット
内容量を見ると、その商品がどれくらいの量なのかがわかります。
これは以下のようなことに役立ちます。
価格とのバランスを見る
同じ100円のお菓子でも「80g入り」と「100g入り」では、後者の方がお得に感じます。
食べる量の目安になる
カロリー表示と一緒に確認することで、「今日は半分だけにしておこう」など食べすぎ防止にもつながります。
実際のボリュームを知る
パッケージが大きくても中身は少ない、という場合もあります。見た目に惑わされずに選ぶためには、内容量の確認が欠かせません。
内容量の表示方法と単位
食品の状態によって、使われる単位が異なります。
| 表示方法 | 単位の例 | よく使われる食品例 |
|---|---|---|
| 重量(g・kg) | 100g、1.2kg | クッキー、チョコレート、焼き菓子 |
| 体積(ml・L) | 200ml、1L | プリン、ゼリー、ジュース |
| 数量(個数) | 6個入り、12個入り | 飴、小分けお菓子 |
※小分けのお菓子などでは、重量+個数を併記することもあります。
例:「120g(12個入り)」など。
お菓子・スイーツの内容量の具体例
それぞれ、中身の形や状態によって適した表示方法が使われています。
内容量の計量法と「特定商品」
日本では「計量法(けいりょうほう)」という法律があり、一部の食品は「特定商品」に指定されています。
この特定商品は、正確な計量・表示が義務づけられています。
特定商品として扱われる主な食品
これらの商品では、重さの誤差が一定の範囲内に収まるよう、製造の段階から厳しくチェックされています。
内容量を見るときの注意点
表示の見方を少し間違えると、実際の量を勘違いしてしまうことがあります。
以下のポイントを意識しましょう。
gとmlの違いに注意
重さ(g)と体積(ml)は、同じ数字でも内容が異なります。
たとえばゼリーなら「100g」と「100ml」は必ずしも同じ量ではありません。
水分の多さや成分の違いで重さが変わります。
個数表示だけで判断しない
「10個入り」と書いてあっても、1個あたりが小さい可能性もあります。
その場合は、全体の重さも一緒に確認することが大切です。
缶詰・瓶詰めは“2重表示”に注意
缶詰やシロップ漬けの果物などでは、以下のように2つの量が書かれています。
- 内容総量(そうりょう):汁も含めた全体の量
- 固形量:実際に食べられる中身の量(具だけ)
例:「内容総量400g/固形量250g」と書かれていた場合、食べられるのは250g分ということです。
まとめ
内容量の表示は、食品選びの重要なポイントです。
重さ・体積・個数などの違いを理解することで、「お得さ」や「食べる量の目安」がわかります。
特にお菓子やスイーツは、見た目に惑わされやすいジャンルなので、内容量をチェックする習慣をつけると安心です。