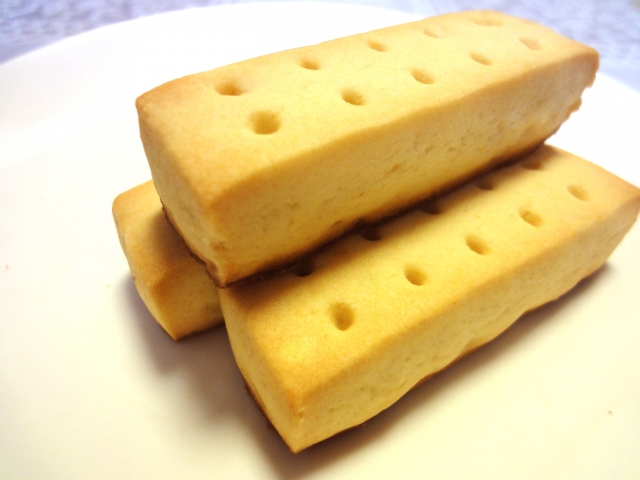【2025年】グミ市場の急成長|3年で1.8倍に拡大した背景と今後の展望

今、グミ市場が大きな転換期を迎えています。
全日本菓子協会が公表した2024年のキャンデー類小売金額は過去最高の3142億円を記録し、その成長の中心にグミが位置しています。
KSP-POSデータによれば、2025年1月から9月の期間においても金額・数量ともに前年同期比で10パーセントを超える伸びを示しており、この勢いは衰えていません。
新型コロナウイルス感染症の流行を契機とした消費行動の変化により、グミは新たな評価を獲得し、急速に市場を拡大してきました。
その社会的な定着は、消費者物価指数の2025年基準改定において新項目として追加されたことからも確認できます。
この成長を捉えた各メーカーは生産体制の強化を進めており、SNS戦略と組み合わせることで、さらなる市場拡大を目指しています。
グミ市場の規模と推移
| 年 | 市場規模 | 状況 |
|---|---|---|
| 2017年〜2021年 | 約600億円 | 横ばい推移 |
| 2021年 | 635億円 | 転換点 |
| 2024年 | 1138億円 | 3年で約1.8倍 |
2025年9月3日に公開されたインテージ「知るギャラリー」のデータは、グミ市場の変化を明確に示しています。
2017年から2021年まで、市場規模は約600億円で推移しており、大きな変動は見られませんでした。
しかし2022年以降、状況は変わります。
2021年の635億円から2024年には1138億円に達し、わずか3年間で約1.8倍という拡大を記録しました。
菓子業界において、これほど短期間で市場が倍近くになることは珍しい現象です。
消費者物価指数にグミの項目が追加された
2025年の基準改定でグミは消費者物価指数の新項目として追加されました。
かつてのグミは子ども向けの菓子という限定的な位置づけでしたが、現在では年齢層を問わず日常的に購入される商品へと変化しました。
経済統計において認知されるまでに至ったという事実は、一時的な流行ではなく構造的な変化が起きていることを示しています。
グミ市場拡大の要因
ガム需要の移転
新型コロナウイルス感染症の流行期には、私たちの生活様式が大きく変化しました。感染対策として衛生意識が高まるなか、ガムの消費行動にも変化が現れました。従来はリフレッシュや口臭ケアの目的で広く利用されていたガムですが、流行期にはその性質が消費者の心理に影響を与えたのです。
ガムに対する抵抗
ガムは噛み終わったあとに紙に包んで捨てる必要があり、外出先では処理に気を使う場面が多くあります。感染対策を意識する人が増えた時期には、こうした“手で触れる行為”や“ゴミの持ち歩き”に抵抗を感じる人が増加しました。さらに、マスク着用が日常化したことで、外でガムを噛む機会そのものが減少しました。
グミへの需要シフト
一方で、グミは口に入れたら完全に食べきることができ、ゴミが出ないという点で衛生的です。この特性が、感染症対策に敏感になっていた消費者に支持されました。また、小袋入りで持ち運びやすく、一口サイズで食べやすいという点も、外出時のおやつやリフレッシュアイテムとしての需要を高める結果につながりました。
食感のバリエーション拡大
各メーカーは食感の開発に力を注いできました。従来は比較的柔らかく、噛み応えが控えめな商品が中心でしたが、近年は硬めの食感を追求した「ハード系」や、弾力があって噛むほどに味わいが広がる「もちもち系」など、多様な食感の商品が登場しています。
硬めのグミは咀嚼による満足感を提供し、長時間噛み続けられることから、食べ応えを求める消費者のニーズに応えました。もちもち系のグミは、食べる時間そのものを楽しむという新しい価値を生み出しました。
こうした食感の多様化により、グミは子ども向けの軽いおやつという従来のイメージから脱却し、大人が選ぶスナックとしての性格を獲得しました。
幅広い年齢層への訴求
食感の進化とガム需要の移転により、グミは年齢層を超えて受け入れられるようになりました。
若年層はSNSでの情報交換や食べ比べを楽しみ、中年層は仕事中の気分転換や集中力維持のために噛み応えのある商品を選びます。
それぞれの世代が異なる理由でグミを購入するようになったことで、市場全体の底上げにつながっています。
SNS時代におけるグミ商品の特性
ASMR動画との適合性
SNSの普及は、グミ市場の拡大に大きな追い風となりました。特に注目されているのが、ASMR(Autonomous Sensory Meridian Response)コンテンツとの親和性です。グミを噛むときに生まれる「カリカリ」や「もちもち」といった咀嚼音は、多くの視聴者に心地よい刺激を与え、人気のASMR動画として拡散されています。これにより、グミは単なるお菓子ではなく、“音を楽しむコンテンツ”として新たな価値を持つようになりました。視聴者が動画をきっかけに商品を購入し、自分でも音を体験してみるという購買行動が生まれており、オンライン上での情報接触が実際の消費行動へとつながっています。
視覚的な訴求力
グミのもう一つの強みは、その色鮮やかな見た目です。赤や黄、緑、青といったカラフルな色が並ぶ様子は写真映えし、InstagramやX(旧Twitter)などで多くの投稿が見られます。複数種類を並べたり、透明な容器に入れて撮影したりすることで、グミの魅力を最大限に引き出した投稿が生まれています。こうしたビジュアルは他のユーザーの目に留まりやすく、思わず「食べてみたい」と感じさせる購買意欲を刺激します。
食べ比べ文化の形成
SNSでの発信が盛んになるにつれ、グミの“食べ比べ”文化も広がりました。グミは味や食感、形のバリエーションが豊富で、商品ごとの違いを楽しむのに最適なお菓子です。消費者がSNS上で食べ比べの感想を投稿する動きに合わせ、メーカー各社も新商品や期間限定商品の投入を加速。これにより、SNS上では常に話題が生まれ、継続的な注目が保たれています。発売直後に購入したユーザーがレビューを投稿し、それを見た他のユーザーが購入を検討する――そんな循環が、SNSを通じて自然に形成されています。
双方向コミュニケーションの実現
メーカー各社は、公式アカウントを活用してユーザーとの対話を重視しています。新商品の告知だけでなく、投稿へのリアクションやコメント返信を行うことで、消費者との双方向コミュニケーションを築いています。こうしたやり取りはブランドへの親近感を高め、ファン層の拡大にもつながっています。特に10代から20代の若年層は、テレビCMよりもSNSで情報を得る時間が長く、友人やインフルエンサーの投稿が購買意欲に直結します。SNSを通じたマーケティング戦略は、若年層との距離を縮める有効な手段として機能しているのです。
中年層が購入するグミ市場の形成
40代以上男性の購入率上昇
近年、中年層のユーザーも増加しています。特に40代以上の男性において購入率が高まっているという傾向が見られます。
カバヤ食品の「タフグミ」に代表されるような、かみ応えのある硬めの商品がこの層に選ばれています。長時間噛み続けられる食感は、仕事中の気分転換やストレス解消に適しており、デスクワークの合間に食べるという使い方が定着しています。
中年層にとっての実用的価値
中年層がグミを選ぶ背景には、いくつかの実用的な理由があります。噛むという行為そのものが集中力の維持やリフレッシュ効果をもたらすという認識が広がっており、ガムの代替としてかみ応えのあるグミが選ばれるようになりました。
小袋入りの携帯しやすい形態は、オフィスや外出先で気軽に食べられるという利便性があります。チョコレートのように気温で溶ける心配もなく、季節を問わず持ち運べる点も評価されています。
グミ商品の特性
フレーバーと食感の多様性
グミの持つ特徴の一つは、フレーバーと食感のバリエーションが豊富であることです。果物系の味だけでも定番から南国系のフルーツまで幅広い選択肢があり、さらに炭酸飲料風味やヨーグルト風味といった果物以外のフレーバーも展開されています。
食感についても柔らかいものから硬いもの、弾力のあるもの、表面に砂糖がまぶしてあるもの、中心に液体が入っているものなど、数多くのバリエーションが存在します。同じグミというカテゴリーの中でこれほど多様な体験が得られることは、消費者にとって大きな魅力となっています。
ブランドごとの個性
各メーカーは独自性を打ち出した商品を開発し、それぞれがブランドとして確立されています。明治の「果汁グミ」、カンロの「ピュレグミ」、UHA味覚糖の「コロロ」といった商品は、それぞれ異なる特徴を持ち、消費者の中で明確に区別されています。
果汁グミは果汁のジューシーさを前面に出し、ピュレグミは濃厚な果実感を訴求し、コロロは果実を食べているかのような食感を実現しています。こうしたブランドの多様性が、市場全体の厚みを増しています。
選択プロセスの楽しみ
グミは食べる楽しみに加えて、選ぶ楽しみも提供しています。店頭のグミコーナーには数十種類の商品が並び、消費者はその日の気分や好みに応じて選択できます。
新しい味を試してみる冒険心、お気に入りの定番商品を買う安心感、期間限定商品を見つけた時の特別感など、選択の過程そのものが一つの体験となっています。こうした選択の自由度の高さが、繰り返し購入される要因となっています。
新規参入によるグミ市場の拡張
三幸製菓による米粉グミの展開
市場の成長は、これまでグミを主力としていなかったメーカーの新規参入を促しています。三幸製菓は2024年、米粉を使った和風味のグミ「もちきゅあ」を発売しました。
三幸製菓は米菓メーカーとして知られており、米を原料とした商品を主力としています。その技術を活かして米粉をグミに応用したことで、他社にはない独自性を打ち出しました。和風味という切り口も、フルーツ系が主流の市場において差別化要素となっています。
森永製菓のブランド活用戦略
森永製菓は2025年2月、長年親しまれてきた「チョコボール」ブランドからグミ版を展開しました。チョコボールは1967年の発売以来、世代を超えて愛されてきたロングセラー商品です。
その知名度と信頼性をグミに応用することで、ブランドの力を活用した市場参入を図っています。消費者にとっても、馴染みのあるブランドから出ているという安心感があり、初めて手に取る際の心理的なハードルが下がります。
機能性成分配合商品の登場
グミ市場の拡大に伴い、単なる嗜好品としてだけでなく、健康や美容に配慮した商品も増加しています。コラーゲンを配合した商品は美容への関心が高い消費者層に訴求し、GABA(ギャバ)を配合した商品はストレス軽減やリラックス効果を訴求しています。
ビタミンやミネラルを強化した商品、食物繊維を配合した商品なども登場しており、グミは栄養補助の側面を持つ商品としても認識され始めています。この健康訴求型グミは従来のグミとは異なる新ジャンルとして位置づけられており、今後の市場拡大の一翼を担う可能性があります。
メーカーの生産体制強化
| メーカー | 施策内容 | 生産能力の変化 |
|---|---|---|
| 不二家 | 福島工場に新ライン設置 | 増強 |
| カンロ | 朝日・松本工場で2拠点体制 | 約5倍 |
| UHA味覚糖 | 福島県の工場に新棟建設 | 約6割増(2027年春稼働予定) |
| ロッテ | 狭山工場にグミ設備導入 | 約4倍(約30年ぶり自社生産再開) |
不二家の生産ライン増設
市場の拡大を受けて、各メーカーは生産能力の増強に乗り出しています。不二家は福島工場に新たな生産ラインを設置し、需要の増加に対応する体制を構築しました。
カンロの2拠点体制と大規模投資
カンロは特に大規模な投資を行っています。同社は2030年までにグミ市場が1500億円規模に達すると見込んでおり、その成長を取り込むために朝日工場と松本工場の2拠点体制を構築しました。この体制により、生産能力を約5倍に増強する計画です。
2拠点での生産体制は、リスク分散の観点からも意味があります。一つの工場でトラブルが発生した場合でも、もう一つの工場で生産を継続できるため、供給の安定性が高まります。
UHA味覚糖の新工場建設
UHA味覚糖は福島県の工場に新棟を建設中です。2027年春の稼働開始を予定しており、稼働時には生産能力を約6割増加させる計画となっています。
UHA味覚糖は「ぷっちょ」や「シゲキックス」といったグミ・キャンディー商品を主力としており、グミ市場における存在感は大きいです。新工場の建設には最新の製造設備が導入される見込みで、生産効率の向上だけでなく品質管理の高度化や新しい食感・味の開発にも寄与することが期待されます。
ロッテの自社生産回帰
ロッテは約30億円を投じて狭山工場にグミ製造設備を導入しました。この投資により、約30年ぶりに自社でのグミ生産を再開することになります。
これまでロッテはグミの生産を外部に委託していた部分がありましたが、市場の成長を受けて自社生産に回帰する判断を下しました。自社生産には品質管理を直接行える利点や、生産スケジュールの柔軟な調整が可能になるというメリットがあります。新設備の導入により、グミの供給能力は約4倍に拡大します。
今後のグミ市場の展望
中長期的な成長の見通し
各メーカーが大規模な設備投資を行っていることからも、グミ市場の成長は一時的なブームではなく中長期的に続くトレンドと捉えられています。カンロが2030年までに1500億円規模になると見込んでいることは、現在の市場規模からさらに拡大することを前提としています。
成長を支える要素は複数あります。食感のバリエーションはまだ開発の余地があり、新しい技術による食感の実現が期待されています。フレーバーについても、地域限定の味や他の食品とのコラボレーションなど、展開の可能性は広がっています。
デジタル時代との適合性
SNSでの情報発信とグミ商品の適合性は、今後も市場拡大の推進力となります。新商品が発売されるたびに話題が生まれ、消費者の関心が維持される仕組みが確立されています。
インフルエンサーとのコラボレーションや、ユーザー参加型のキャンペーンなど、SNSを活用したマーケティング手法はさらに洗練されていくでしょう。こうした取り組みにより、若年層だけでなく中年層以上への訴求も強化される可能性があります。
健康志向への対応
機能性成分を配合したグミの増加は、新しい消費者層の開拓につながります。お菓子としてだけでなく、栄養補助や健康維持の手段としてグミを選ぶ消費者が増えれば、市場はさらに広がります。
特に高齢化が進む日本において、手軽に栄養を補給できる食品へのニーズは高まっています。グミという食べやすい形態で必要な栄養素を摂取できる商品は、今後の社会的ニーズに合致する可能性があります。
多様性に基づく市場の深化
グミ市場の強みは、その多様性にあります。柔らかいものから硬いもの、甘いものから酸っぱいもの、果物味から飲料味まで、あらゆる嗜好に対応できる幅の広さが、幅広い消費者層を取り込む基盤となっています。
各メーカーが独自性を追求し差別化を図ることで、市場全体のバリエーションはさらに豊かになります。こうした多様性の深化が、消費者に飽きさせず継続的な購買を促す要因となります。
まとめ
グミ市場は2021年の635億円から2024年には1138億円へと急拡大し、消費者物価指数にも新項目として加わるほど社会に定着しました。この成長の背景には、コロナ禍でのガム需要の移転、多様な食感の進化、そしてSNSとの高い親和性があります。
ASMR動画や食べ比べ投稿を通じて若年層の関心を集めた一方、かみ応えのある商品の登場で中年層にも支持が広がりました。多彩なフレーバーや食感が“選ぶ楽しさ”を生み出し、各ブランドが独自のポジションを確立しています。三幸製菓の和風グミや森永製菓のチョコボール系グミなど、新規参入も活発で、健康志向型グミの台頭も市場拡大を後押ししています。
こうした需要増に対応し、不二家、カンロ、UHA味覚糖、ロッテなど主要メーカーは生産能力の強化を進行中です。カンロは2030年までに市場規模1500億円を見込み生産を約5倍に拡大、ロッテも約30年ぶりに自社生産を再開し供給体制を刷新しました。多様化と発信力を強みに、グミ市場は今後も持続的な成長が期待されています。