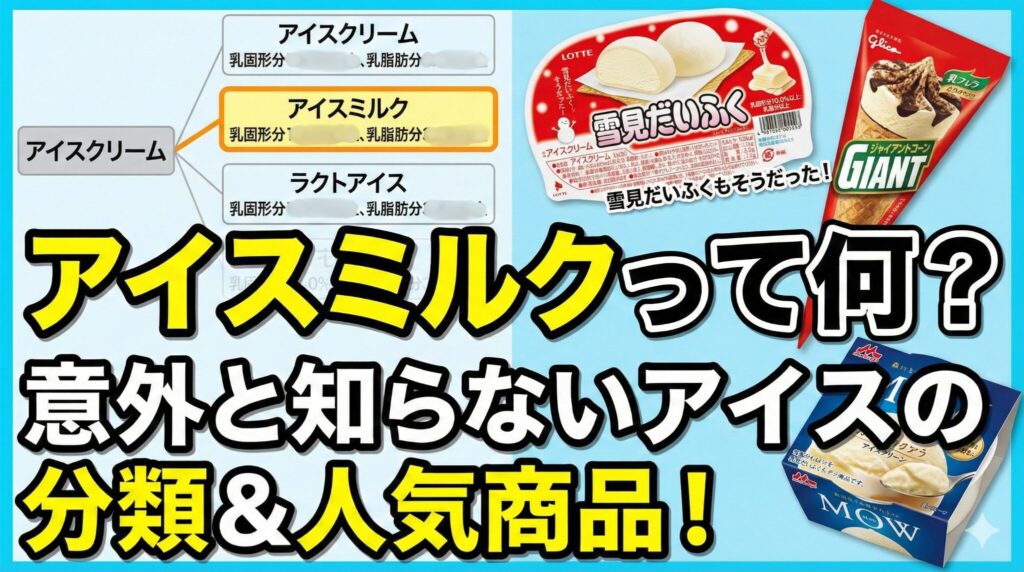加工食品の『栄養成分の量及び熱量』|かんたん説明【食品表示基準】

加工食品の食品表示ルール
栄養成分の量および熱量とは?【食品表示における意味】
栄養成分表示とは、食品にどんな栄養がどれくらい入っているかを示した情報です。あわせて、「熱量(カロリー)」も記載されています。
これは、食べる人が健康を守るためにとても大切な情報です。たとえば、「太らないように気をつけたい」「塩分をとりすぎたくない」「子どもに必要な栄養を考えたい」といったときの目安になります。
表示が義務付けられている基本の5項目
日本の法律では、袋や容器に入った加工食品について、次の5つの栄養成分を必ず表示しなければならないと決められています。
| 表示名 | 意味 | 単位の例 |
|---|---|---|
| エネルギー | 食品からとれる力のこと(カロリー) | kcal(キロカロリー) |
| たんぱく質 | 体を作る材料。筋肉、皮ふ、髪などに必要 | g(グラム) |
| 脂質 | エネルギーになるあぶら分。とりすぎ注意 | g |
| 炭水化物 | 体や脳のエネルギー源。糖やでんぷんなど | g |
| 食塩相当量 | 含まれるナトリウムを塩の量に換算したもの | g |
※「ナトリウム」とは、塩に含まれる成分のこと。表では「どのくらいの塩と同じか」が分かるように「食塩相当量」で表示します。
栄養成分の表示方法と単位
食品の種類によって、どの単位で表示するかが決まっています。よくある単位は次の通りです。
- 100gあたり:クッキーやチョコレートなど重さで管理しやすいお菓子
- 100mlあたり:ゼリーや飲み物など液体ややわらかい食品
- 1個(1包装)あたり:プリン、カップゼリーなど1つずつ食べる商品
- 1食分あたり:お弁当やレトルトカレーなど「1回で食べる量」
例えば下記のように表示します。
栄養成分表示(1個あたり)
エネルギー:150kcal
たんぱく質:2.5g
脂質:8.0g
炭水化物:17.0g
食塩相当量:0.2g
※「1個あたり」と書くときは、「その1個の重さ(例:80g)」も一緒に書くのが基本です。
任意で表示できる栄養成分
ビタミンやミネラルなど、一部の栄養成分は任意表示といって、表示するかどうかはメーカーの自由です。
よく表示される項目
- ビタミン類(ビタミンC、ビタミンB1、B2、Eなど)
- ミネラル類(カルシウム、鉄、亜鉛など)
- 食物繊維
- 飽和脂肪酸・トランス脂肪酸
※健康志向の商品では、これらの表示があると選びやすくなります。
「0」と表示される栄養成分
実は、少しだけ含まれていてもごくわずか(基準より下)なら、「0」と書いていいルールがあります。
たとえば、「ゼロカロリー飲料」などは、100ml中に5kcal未満であれば「0kcal」と表示できます。
エネルギー:0kcal
脂質:0g
食塩相当量:0g
推定値としての成分表示
すべての食品を検査して栄養を調べるのは大変なので、次のような方法で「推定値(おおよその数字)」として表示することも認められています。
主な推定方法:
- 原材料の栄養データから計算する
- 似た食品のデータを使って計算する
その場合は、必ず次のような注意書きを入れます。
※この表示値は、目安です。
また、その計算に使ったデータや根拠は、会社で保管しておく必要があります。
栄養成分表示をチェックするときのポイント
消費者として、次のような点を意識して見るとよいでしょう。